共有名義の底地を売却する方法~共有状態はトラブルのもと~|底地の売却・相続
共有名義の底地を売却する方法~共有状態はトラブルのもと~
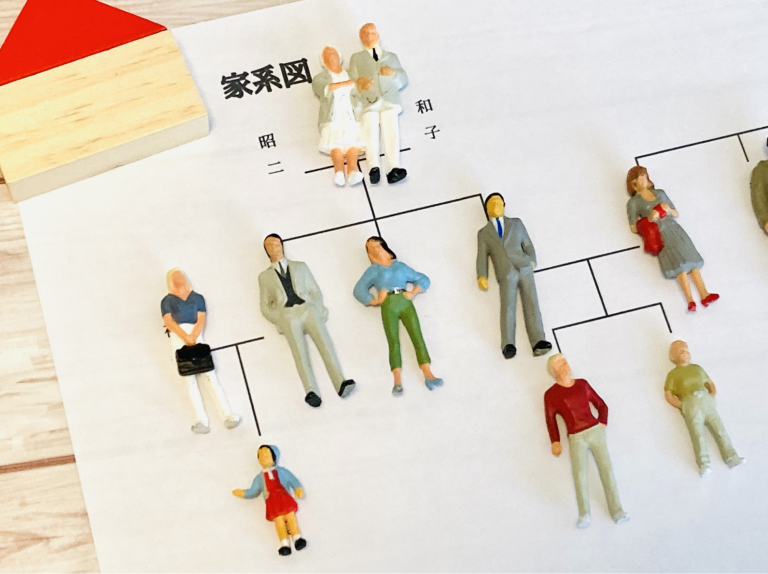
底地上は、土地を利用する権利を持つ借地人がいるので、権利関係が複雑な土地です。この底地を共有のまま放置しておくと、トラブルのもとになってしまいます。
この記事では、底地を共有名義にしておくリスクや、共有状態を解消する方法について解説します。また、底地を高値で売却する方法も紹介します。
本記事を読むことで、相続で共有名義の土地を相続した場合の適切な行動がわかりますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
1. 共有名義の底地とは
底地とは、借地権がついている土地のことです。借地権がついているということは、土地の所有者が土地を自由に利用できず、活用権限が大きく制限されているといえます。
また、底地の共有状態とは、底地を各共有者全員が自己の持分割合で共同所有していることを指します。底地が共有状態になっていると、自身の持分のみを売却することはできますが、底地全体を売却するには、共有者全員の同意が必要になります。
底地は、借地人との関係で複雑なのにもかかわらず、共有状態になることでさらに複雑化してしまうのです。
1-1 底地が共有名義になるきっかけ
底地が共有名義になるきっかけの約9割は相続が原因です。
たとえば、底地を単独で所有している被相続人がなくなり、3人の子どもが底地を相続すると、相続分は1/3ずつになり共有状態になります。また、その子どもにも相続が発生すると、さらに共有者が増え、一層権利関係が複雑になってしまいます。このように、相続により底地の共有状態が発生することが多いのです。
また、相続人同士で収益を取り合ったり、売却時に話がまとまらないという理由で、底地の共有相続を嫌がる相続人が増えています。底地は、土地を相続しても自由に利用できず処分に困ることからも、底地を共有することが敬遠されているのです。
2. 底地を共有名義で所有するリスク
底地を共有名義で所有するとリスクが大きいことを解説しましたが、具体的にどのようなリスクがあるのでしょうか。ここでは、底地を共有名義で所有するリスク5つを紹介します。
2-1 借地人への対応で意見が分かれる
底地を共有名義で所有すると、底地の活用や借地人への対応を巡って、共有者間で意見が分かれてしまうことがあります。共有者それぞれが抱えている問題や経済状況で、意見が変わるのです。
たとえば「地主Aは譲渡承諾しないと言っているが、地主Bは譲渡承諾すると言っている」というケースが起こることがあります。この場合、地主Bはまとまったお金が必要なため、譲渡承諾して承諾料を得たいと思っているかもしれません。しかし、地主Aは借地人の変更に不安を持っているため、譲渡承諾しないことがあるのです。
他にも「借地非訟の裁判で、地主Aが介入権を行使すると言っているが地主Bは介入権を行使しないと言っている」や「地代の集金や更新業務を任されているAが、“管理費”の名目で地主Bより地代を多くもらう」などのことが起こる可能性があります。
共有者が底地に関するそれぞれの役割を持っていることがあるため、このような意見の食い違いが発生します。借地人への対応で意見が分かれて、話がまとまらないことが共有名義のリスクのひとつです。
2-2 他の共有者の同意がないと売却や借地契約の変更ができない
共有名義の底地の売却や借地契約の変更をするためには、他の共有者の同意が必要です。そのため、所有権を持っているにもかかわらず、自分が思う通りに土地を活用できないことがあるのです。
共有名義の底地を売却することは、民法251条により共有者全員の合意が必要です。また、地代の値上げなど借地契約の内容変更は、民法252条により共有持分の過半数を超える共有者の合意が必要となります。
したがって、自ら所有している土地でも共有名義になっていることが原因で、独断での売却や契約内容変更ができないことも底地の共有名義のリスクです。
2-3 勝手に持分を売却する共有者が出てくる
底地の共有名義は、共有物全体の売却に全員の同意が必要ですが、自身が持っている共有持分のみを売却することは可能です。よって、自らの持分を勝手に売却し、いつのまにか知らない人と底地を共有していることがあります。
たとえば、他の共有者が持分を売却した先が、悪意のある業者だった場合、他の共有者に対して、共有部分の売却を相場より著しく低い金額で迫ってくることがあります。また、共有者同士が良好な関係を築けていたにもかかわらず、見知らぬ第三者が所有することで関係が崩れて、トラブルや裁判が起こってしまうこともあり得るのです。
このように、1つの土地を複数人が共有して所有することは、それぞれが単独で第三者に売り渡せるというリスクにつながります。
2-4 共有者の相続によって権利関係が複雑になる
現状、共有者同士が良好な関係を築けていたとしても、将来的に相続が発生してしまうと、共有名義人が増えさらに権利関係が複雑になってしまいます。
共有名義人の相続人が1人であれば、これ以上共有名義人は増えませんが、相続人が複数の場合は名義人が増えてしまいます。さらに、相続が進めば進むほど枝分かれ式に共有名義人が増え、最終的には手に負えないほどの人数になることがあります。
現状のままで底地を運営するのであれば問題ありませんが、底地の地代変更や売却を検討しだした際に初めて発覚することが多く、トラブルに発展することがよくあります。したがって、共有者の相続によって権利関係がさらに複雑化してしまうことも共有名義のリスクといえます。
2-5 税金や管理費を巡って共有者間でトラブルになる
底地を所有すれば、借地人から地代を得られるというメリットがあります。しかし、一方で固定資産税や都市計画税、不動産会社に支払う管理費などの支払いが発生します。これらの支払いや受け取る金銭の割合を巡ってトラブルになることがあるのです。
たとえば、支払うべき固定資産税を共有者の誰かが滞納すると、他の共有者に支払いの告知がされます。そうなると、共有者は納税の負担からは逃れられないので、支払い割合に不公平が発生してしまいます。また、共有者の1人が管理をする代わりに他より地代を多く得ていたとすると、共有名義人が変わった際にトラブルが発生するかもしれません。
このように、底地を所有する中で支払うべき金銭や得られる地代を巡って、共有者間でトラブルになることも、共有名義のリスクです。
3. 底地の共有状態を解消する5つの方法
底地を共有名義で所有するリスクにはさまざまなものがありましたが、共有状態を解消したい場合、どのようにすればいいのでしょうか。
3-1 借地人に売却する
底地の共有状態を解消したい場合は、借地人に売却することを検討してみましょう。借地人にとっては底地を購入することで多くのメリットを得られるのです。借地人に底地全体を売却する際は、共有者全員の同意が必要になることが必要ですが、売却条件によってはトラブルなく底地持分のみ譲渡することができます。
借地人が底地全体を購入することで得られるメリットとしては、高額な地代や更新料を毎月払わなくて済む点や、第三者に売却する際に借地権と比べて高値で売れる可能性が高いことです。また、土地を所有することで土地を自由に活用できるので、分割したり造成もできるようになります。
ただし、底地の売却をいきなり持ちかけては、借地人が困惑してしまうので、借地の更新時期や増改築のタイミングを見計らって、相談するのがベストです。
3-2 底地の買取業者に安値で売却する
底地の共有状態を解消する方法として、底地の買取業者に売却する方法があります。個人ではなく専門の買取業者に買い取ってもらうことでスムーズに手続きが進むのです。
底地買い取りの専門業者の中には底地の持分のみを購入する買取業者もいますので、購入した底地の活用ノウハウを駆使し権利調整を経て、確実に現金化していきます。
しかし、底地買い取りの専門業者だとはいえ、相場より極端に低い買取価格を持ちかけられることがほとんどで、適正価格で売却するためには、専門業者に根拠を持った買取価格を提示してもらうことが重要です。
3-3 借地権を購入して底地と同時売却する
借地人から借地権を購入して、完全所有権として売却することも、共有名義を解消する方法です。この方法は共有者全員と借地人の同意が必要であるため難易度が高いですが、買い手は土地を自由に活用できるので、高額で売却することができます。
この方法の注意点は、他の共有者と分け前を巡ってトラブルを起こさないようにすることです。事前に売却額の分配について打ち合わせをしなければ、不公平感が出てもめてしまうかもしれません。
借地人が借地権の売却に同意することが前提ですが、このように共有者で借地権を購入して底地を売却することは、有効な手段だといえます。
3-4 底地と借地権を等価交換して売却する
底地と借地権を等価交換すれば、スムーズに売却ができます。この方法には、共有者全員の同意と、借地人の協力が必要です。
ただし、この方法の前提条件として、借地上に建物がない更地部分が一定の広さで存在することに加えて、共有者全員で土地を分割しても問題ないほど十分な敷地がある、ということがあげられます。
等価交換の手順はおおまかに下記のとおりです。
- 底地と借地権の評価額を調べ、交換する割合を決める
- 分筆登記を行う
- 所有権移転登記を行う
中でも、等価交換する割合を決めることが一番難易度が高いといえます。割合を巡ってもめることがないように、専門家の意見を取り入れながら進めるとよいでしょう。
3-5 共有者間で持分を売買する
底地の共有者間で持分を売買することも有効な方法です。共有者が他の持分を買い取れば、底地を単独所有にしたり、底地の持分割合が多いことで受け取れる地代が増えるというメリットがあるからです。
この方法は、共有者に買い取る意思があれば、第三者に売却するよりスムーズに手続きが進むため、難易度が低く確実な方法です。注意点としては、共有者に売却するには交渉が必要なことや、適切な金額で売却できるように十分準備することなどがあげられます。
3-6 第三者に自己持分のみを売却する
一番現実的な方法としては、第三者に自己持分のみを売却することです。自己持分の売却には共有者の同意は不要です。よって、自身が選んだ相手に共有持分を売却できれば、共有状態を解消することができます。
ただし、個人や一般の不動産会社では底地や共有持分に関する知識が乏しく、断られる可能性が高いので、底地売却の専門仲介業者に相談するようにしましょう。専門業者であれば、蓄積された活用ノウハウや成約事例があるため、安心でスムーズな売却ができるでしょう。
4.底地を高額売却する3つのポイント
底地の共有名義を解消する方法を詳しく解説しましたが、ここからは、底地を高値で売却するためのポイントを紹介します。
4-1 底地専門の不動産仲介業者に相談する
底地かつ共有の場合、借地人だけでなく共有者との関係もあり、権利関係が非常に複雑です。そのため、自分が思うタイミングで売却することが難しくなってしまいます。また、売却に関して他の共有者の同意が取れている場合とそうでない場合など、状況によって進め方が異なってきます。
自身で底地の売却方法がわからない場合は、底地を専門に取り扱いそれに加えて共有持分の売買にも特化した専門仲介業者に売却を依頼すれば、共有者との交渉をすることなく、1ヶ月以内に共有持分を売却できます。
また、底地専門の仲介業者は、他の共有者との交渉も行ってくれます。面倒事が多い底地の共有名義ですが、専門業者であればこれまでの経験や知識を活かしてスムーズに買主を探し手続きが進みます。
さらに、個人では判断しにくい、共有名義の適正な評価をしてもらえるというメリットもあります。予想以上の価格で売却できる可能性もあるので、複数の専門業者に査定を依頼することをおすすめします。そして安易に買取業者の言い値で安く売ることは避けましょう。
4-2 共有者の権利関係や借地契約の内容を明確にする
底地を高額で売却するためには、共有者の権利関係や借地契約の内容を明確にしておく必要があります。また土地全体の確定測量図を作成して“キレイな土地”の状態にしたうえで、底地に関連する内容を明確にしておくと、第三者が購入を検討する際の安心感につながり、高値で売れやすくなるのです。
底地の購入希望者は、購入にあたり底地に至った経緯や地代、契約期間や他の共有者の権利関係を知りたいと考えます。また、それらの内容が契約書に明記されているかも重要です。もし契約書に詳しい契約内容の記載がない場合は、借地人に内容を確認し新たに契約書を作成するようにしましょう。
その際に重要なポイントは、地代や更新料などの費用関係、借地権設定期間、建て替え・増改築時の承諾料などをかならず記載することです。もし契約書の作成方法がわからない場合は、底地専門の不動産仲介業者へ相談をしてみましょう。
4-3 底地の売却前に地代を増額しておく
底地の購入者は、購入しても実際に土地を利用できるわけではないので、投資目的で購入する人がほとんどです。つまり、得られる地代や更新料が多いほど高値で売れる可能性が上がりますので、契約内容を変更して地代を値上げすればいいのです。
ただし、地代を値上げするためには正当な理由が必要です。たとえば「土地にかかる税金が上昇した」や「土地を維持する費用が上がってしまった」などの理由です。しかし、地代の交渉に失敗すれば借地人との関係が悪化してしまうので、十分な準備が必要です。
地代の交渉のコツは、曖昧な理由を語るのではなく、根拠が明記された資料を作成し堂々と交渉することです。明確な理由があれば、借地人は納得し地代の値上げに同意してくれるでしょう。
まとめ
共有名義で底地を所有している場合、気をつけなければいけないポイントが多く、放置しているとトラブルになることがあります。最悪のケースは、トラブルが原因で裁判にまで発展し、時間も費用も取られてしまうことです。そのようなことにならないよう、底地の共有名義がわかった時点で、底地に強い専門業者への相談が不可欠です。
中央プロパティーでは、不動産鑑定士による正しい評価をもとに、共有持分や底地の売却をサポートしています。CENTURY21のネットワークを活かした当社独自の入札制度(ポスティングシステム)により、他社よりも高値での売却に成功した実績が多数ございます。
また、複雑な権利関係が絡む底地の取引を安心して行えるよう、専任の社内弁護士が立ち会いのもと、最適なご提案から売買契約締結までをおこないます。さらに、取引後のトラブルを防ぐため、専門の弁護士が事前に契約書のチェックを行い売主様の不安要素を取りのぞきます。
底地の共有持分の売却なら、ぜひ中央プロパティーへご相談ください 。

この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。





