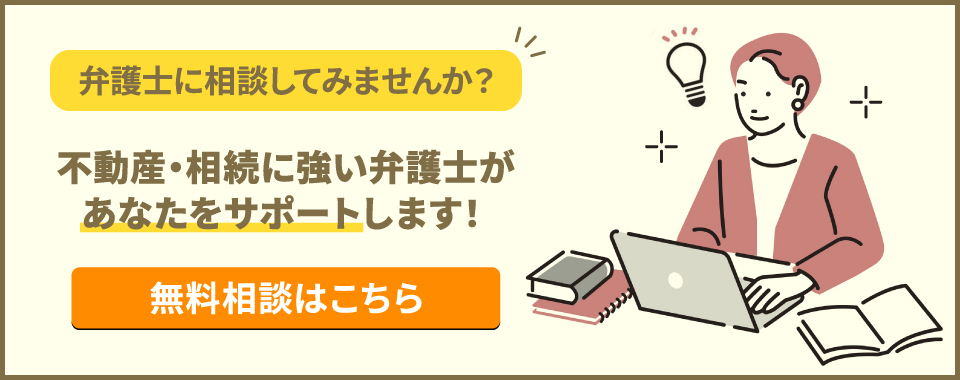普通借地権とは?定期借地権とどう違うのかも解説|借地権の基礎知識
普通借地権とは?定期借地権とどう違うのかも解説

目次
借地権には、普通借地権や定期借地権などさまざまな種類があります。
当記事では、普通借地権の概要や定期借地権との違いに加え、借地権付き物件のメリット・デメリットについて詳しく解説します。借地権付き物件の購入や運用を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

1.普通借地権とは?借地権の種類
借地権とは、建物所有を目的として土地を借りるための権利を指します。具体的には、マイホーム建設のために他人が所有している土地を借りる場合などに利用できる権利です。
借地権には、普通借地権と定期借地権の2種類があります。ここでは、それぞれの内容について詳しく解説します。
1-1.普通借地権
普通借地権は、1992年に制定された借地借家法で定められている権利です。借地借家法に定めのある借地権の中で、定期借地権でないものはすべて普通借地権とされています。
借地権の存続期間は30年以上と定められており、契約満了時には更新が可能です。1回目の更新では期間を20年以上、2回目以降の更新では期間を10年以上とする必要があります。
借地契約は、居住用建物を建てるために締結されることが多いです。地主側から簡単に契約解除ができると、借地権者は住む場所を失うことになります。そのため、借地権によって土地を貸した地主は、正当事由がない限り一方的な契約解除はできません。
「正当事由」の内容は条文にも明記されており、火災による建物滅失などが当てはまります。
1-2.定期借地権
定期借地権とは期間が定められている借地権であり、契約更新がないのが特徴です。
定期借地権は、以下の3つの種類に分類されます。
一般定期借地権
- 建物用途:制限なし
- 存続期間:50年以上
- 特徴①:更新、建物再建による延長、建物買取請求はいずれも不可とされている
- 特徴②:期間満了後は借主が建物を取り壊して土地を返還しなければならない
事業用定期借地権
- 建物用途:事業用建物に限る
- 存続期間:10年以上50年未満
- 特徴:更新、建物再建による延長、建物買取請求は基本的に不可
- (存続期間が30年以上の場合、公正証書による契約で定めることで不可にできる)
建物譲渡特約付借地権
- 建物用途:制限なし
- 存続期間:30年以上
- 特徴①:契約満了時に地主が建物を買い取らなければならない
- 特徴②:借地権消滅後、借主は賃貸借契約を締結することで建物を使用できる
2.普通借地権と定期借地権の違いは?
普通借地権と定期借地権には、さまざまな違いがあります。具体的な内容は以下の通りです。
- 更新の可否
- 契約方法
- 地代の相場
- 借地権の価値
契約後のトラブルを回避するためにも、契約前に普通借地権と定期借地権の違いを押さえておきましょう。
ここでは、それぞれの内容について詳しく解説します。
2-1.更新の可否
普通借地権では、地主側に土地の返還を求める正当事由がない限り、契約が自動的に更新されるのが特徴です。
土地の返還を求める理由によっては、借主に立ち退き料を支払わなければならないケースも少なくありません。また、借主に建物買取請求権を行使されると、建物を時価で買い取る必要があります。
対して、定期借地権は更新がなく、契約終了時には建物が取り壊された状態で土地が返還されます。
普通借地権では半永久的に土地を貸し出すことになりますが、定期借地権であれば期間が明確に定められているため、地主に有利な契約と言えるでしょう。
2-2.契約方法
普通借地権を締結する際には、契約方法に制限がありません。しかし、定期借地権は書面にて契約を交わす必要があります。
また、一般定期借地権では公正証書以外の契約書も利用可能ですが、事業用定期借地権では必ず公正証書によって契約を交わさなければなりません。
特に公正証書による契約は公正性が高いため、契約者双方にとってより安心できる契約と言えます。
2-3.地代の相場
一般的な地代相場は、定期借地権のほうが高く、普通借地権は安くなる傾向があります。
定期借地権に基づいて借りた土地に住宅を建てた場合、地代相場は土地価格の2〜3%程度です。しかし、普通借地権の場合は「固定資産税の3倍」が相場であるため、土地価格に置き換えると1%にも満たない金額となります。
普通借地権の地代が安く設定されている理由は、契約存続期間の長さです。普通借地権では半永久的な契約が前提となっているため、多くの場合は通常の地代相場を下回る金額設定となっています。
また、普通借地権の契約の際には、借主から地主に対し「借地権料」としてある程度まとまった金額の支払いが必要です。借地権料が地代の先払いのような役割を果たすことで、その後の支払い金額が安くなっています。
2-4.借地権の価値
借地権は、権利そのものを売買することが可能です。何十年という単位で長期間土地を利用できる権利であるため、経済的な価値があります。
定期借地権は存続期間が限定されており、更新や延長が認められていないことから、高値での売却は期待できません。また、売却時点での契約の残存期間によって、借地権価格も大きく変動します。基本的には、残存期間が短ければ、その分価格も安くなります。
対して普通借地権は更新を行うことができ、半永久的な契約となるため、借主にとってメリットが大きく、売却価格も高くなりやすいです。
3.借地権付き物件のメリットとデメリット
借地権付きの物件には、さまざまなメリットとデメリットがあります。借地権付きの物件の建設・購入を検討する場合には、メリットとデメリットの両方を十分に理解しておくことが重要です。
ここでは、借地権付き物件のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
3-1.借地権付き物件のメリット
借地権付き物件のメリットは、以下の2つです。
価格が安い
借地権付き物件の大きなメリットとして、土地の購入費用が不要である分、価格が安く済むことが挙げられます。
普通借地権では、契約の際に借地権料としてまとまった金額の支払いが必要です。しかし、借地権料の支払い金額を考慮しても、土地を購入する場合の6〜8割程度の価格で物件を取得できます。
また、借地権付き物件の所有権はあくまで地主にあるため、土地にかかる税金は地主負担となります。借主は固定資産税や都市計画税を支払う必要がありません。
立地が良い場合が多い
人気エリアや交通アクセスに優れた土地は、借地になっていることが多い傾向にあります。借地権付き物件を購入することで、需要の高い便利な土地に住むことが可能です。
3-2.借地権付き物件のデメリット
借地権付き物件のデメリットは、以下の2つです。
さまざまな費用がかかる
借地権付き物件を利用している間は、土地の地代を支払い続けなければなりません。契約内容によっては、地代の他に更新料が必要となるケースもあります。
また、物件の建て替えや増改築を行う場合、工事の規模によっては地主に対する許諾料の支払いが必要です。
地主の許可が必要な場面が多い
借地権付き物件の土地は、あくまで地主のものです。物件の床面積が増えると土地の税金に影響することから、出産や介護などライフステージの変化を機に増改築・リフォームをしたい場合には、必ず地主の許可が必要です。
いざという時の交渉がスムーズに進むよう、地主とは日頃から適度なコミニュケーションを取り、良好な関係を築いておくのがポイントです。
まとめ
借地権とは、建物の所有を目的として土地を借りる権利です。借地権には普通借地権と定期借地権があり、それぞれ更新の有無や契約方法が異なります。また、普通借地権は地代が安く、権利自体の価値が高いのに対し、定期借地権は地代が高く、権利自体の価値が低い傾向にあります。
借地権付き物件のメリットは、価格が安いことや立地が良いことです。一方で、さまざまな費用が必要となること、地主の許可を得なければならない場面が多いことがデメリットとして挙げられます。
借地権付き物件のデメリットが気になり、借地権の売却を検討している方は、ぜひ中央プロパティーにご相談ください。専門家が売却のサポートを行うため、安心して取引を行えます。

この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。