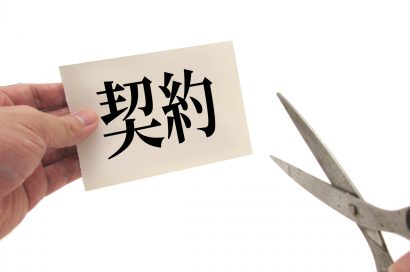地代の値下げ交渉はできるのか?

目次
地代は、地主と借地人双方の合意によって決まるため、一度決まった後でも交渉の余地があります。
本記事では、借地契約において地代の増額または減額を求める場合の基礎知識、具体的な交渉の流れや注意点を紹介します。

地代の増減額請求とは?
賃料、つまり地代の増額・減額については、借地借家法で以下の通り定められています。
「地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」
引用元 借地借家法第11条
地代は、地主と借地人の利害が対立しやすいため、借地契約においてトラブルの原因となりやすい要素の一つです。
なぜなら、少しでも地代を上げたい地主と、できるだけ安く抑えたい借地人とでは、利益が相反するからです。
しかし、一方的に値上げや値下げを請求された側は「そんな話は聞いていない」と戸惑ってしまいます。
そのような無用な事態を避け、公平性を保つため、地代の増額・減額については借地借家法で明確なルールが定められているのです。

借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫
地代の増減額請求増減額請求が認められる3つの要件
地代の増減額請求が認められる要件は、以下の3つです。
- 租税その他の公課の増減
- 土地価格の上昇・低下や経済事情の変動
- 近隣の類似した土地の地代との比較
借地借家法第11条をもとに見ていきましょう。
地代増減額請求が認められる要件①:租税その他の公課の増減
「土地に対する租税その他の公課」とは、主に、その土地にかかる固定資産税や都市計画税のことをいいます。
これらの税金が大幅に増減した場合、地代増減の理由として認められることがあります。
地代増減額請求が認められる要件②:土地価格の上昇・低下や経済事情の変動
「その他の経済事情の変動」とは、バブル崩壊やリーマンショックのような大きな経済変動を指します。
ただ、単に「景気が悪い」といった主観的な理由だけでは認められず、客観的な基準で判断されます。
その判断基準として、消費者物価指数、政策金利、労働賃金指数等の経済指標の変動がこれに該当します。
地代増減額請求が認められる要件③:近隣の類似した土地の地代との比較
「近傍類似の土地の賃料との比較」とは、土地が存在する周辺地域で、利用状況などが類似した土地の地代と比較することを言います。
例えば、住宅地の地代を比較する際に、近隣の商業地の地代を参考にすることは適切ではありません。
借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫
地代の増減額請求における注意点
上記3つの要件を満たす場合も、1つ注意点があります。
それは借地借家法第11条の但し書き「・・・ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」という点です。
契約時に当事者間で一定期間地代を増額しない旨の特約がある場合には、たとえ相場と乖離があってもそちらが優先されます。
ここでの重要なポイントは、但し書きが適用されるのは「増額しない」特約の場合のみで、「減額しない」という記述がない点です。
つまり、「一定期間、地代を減額しない」という特約があったとしても、借地人はその特約に縛られることなく、地代の減額を請求することができます。
これは、借地借家法が、社会的・経済的な立場が弱いことが多い借主を保護することに主眼が置かれているためです。
地代が減る分には借主には有利に働きますが、地代が増額されてしまうと借主は地代を払えなくなり、住む家がなくなってしまう可能性もあります。
そのため、借地人に不利となる地代の増額には厳格な要件が課されており、安易に変更できないようになっているのです。
借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫
適正な地代の算定方法
地代の増減を交渉するにあたり、まずは現在の地代が適正なのかを把握する必要があります。
地代相場の簡易的な目安
地代の相場は「固定資産税・都市計画税の2~3倍」とよく言われます。
これは、地主が支払う固定資産税・都市計画税(公租公課)を賄った上で、一定の利益(純賃料)を確保するという考え方に基づく簡易的な計算方法です。
あくまで目安の一つのため、正確な価格を算出するには、次に紹介する方法で評価したり、不動産鑑定士に依頼したりする必要があります。
不動産鑑定で用いられる評価方法
不動産鑑定士が用いる代表的な算定方法には、以下のものがあります。
- 差額配分法:土地と建物を一体として生み出される収益から諸経費を差し引き、残った利益を地主と借地人で配分する方法。
- スライド法:現在の地代を基準に、その後の経済変動などを考慮して調整する方法。
- 利回り法:更地価格に一定の利回りを掛けて地代を算出する方法。
- 賃貸事例比較法:近隣の類似した土地の賃貸事例と比較して地代を算出する方法。
- 公租公課倍率法:固定資産税などの公租公課に一定の倍率を掛けて地代を算出する方法。
いずれの方法にも長所・短所があるため、実際には複数の方法を組み合わせたり、一つの方法を基準に他の要素を考慮したりして総合的に判断されます。
裁判所で地代を算定する際も、同様に複数の計算方法を用いて総合的に判断するケースが多くなっています。
借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫
地代増減額請求の手続きと流れ
地代増減額請求の流れは、主に以下の通りです。
- 当事者間での交渉
- 簡易裁判所での調停
- 地方裁判所での訴訟
STEP1. 当事者間での交渉
まずは、当事者間で交渉することが原則です。
地代変更の交渉をし、ここでうまく折り合えれば、地代は無事変更されます。
すんなり変更に応じてくれればよいのですが、通常はそうならない場合が多いので、根拠となる資料は念入りに用意しておいた方がよいでしょう。
具体的には、固定資産税評価証明書、近隣の地代相場がわかる資料、過去の契約書などを準備すると、交渉を有利に進めやすくなります。
合意した内容は、後々のトラブルを防ぐため、必ず「地代変更に関する合意書」などの書面で残しましょう。
STEP2. 簡易裁判所での調停
当事者間の交渉がうまくいかない場合には、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に地代減額調停を申し立てることになります。
調停は、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が中立な立場で間に入り、当事者双方の言い分を聞きながら、話し合いによる円満な解決を目指す手続きです。
ここで合意が得られれば、その内容を記した調停調書が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ちます。
なぜいきなり裁判ではないのかと思う方もいるかもしれませんが、地代に関する争いは「調停前置主義」が採用されており、原則として、訴訟を起こす前にまず調停を経なければなりません。
STEP3. 地方裁判所での訴訟
調停でも合意に至らない(不成立となった)場合には、いよいよ地方裁判所に訴訟を提起することになります。
訴訟では、主張を裏付けるための客観的な証拠資料(不動産鑑定書など)が極めて重要となり、手続きも複雑になるため、弁護士への依頼が一般的です。
また、判決までには長い時間と費用がかかるため、できれば調停までの段階で解決を図ることが望ましいでしょう。

賃料増額請求・減額請求の判例
地代の増減をめぐっては争いが多く、参考となる判例も数多くあります。
ここでは、代表的なものを2つご紹介します。
| 【参考判例1】最判平16年6月29日判決(地代のケース) 【要旨】たとえ契約書に「消費者物価指数が下がっても地代は減額しない」という特約があっても、それは借地人に不利なものとして無効であり、借地人は地代の減額を請求できる、とされました。 |
| 【参考判例2】最判平15年10月21日判決(家屋のケース) 【要旨】賃料を自動的に増額する特約がある場合でも、その後の事情の変更により賃料が不相当となった場合は増減額請求が認められる、とした上で、その判断においては契約時の経緯や当事者の事情なども含めて総合的に考慮すべきである、とされました。 |
これらの判例からもわかるように、一定期間の地代を増額しない特約は有効ですが、期間が不特定(例:「契約終了まで」など)であったり、借地人に一方的に不利な内容であったりする場合は、無効になる可能性がある点には注意が必要です。
借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫
センチュリー21中央プロパティーなら、地主との交渉もスムーズに代行可能
本記事で解説した地代交渉のように、借地権には地主との複雑なやり取りがつきものです。
ご自身での交渉は精神的な負担も大きく、法的な知識も必要となります。
地代の交渉の他にも、「地主が売却や更新を認めてくれない」「空き家の地代をこれ以上払いたくない」「地主との関係構築が面倒で、子に相続させたくない」など、借地権に関するお悩みをお持ちなら、専門家への売却相談が解決の近道です。
当社センチュリー21中央プロパティーは、ご相談&トラブル解決実績4万件超を誇る、借地権の専門家集団です。
借地権に関するトラブルの解決・高額売却ノウハウは業界でも随一であり、経験豊富な専門家が地主との交渉も円滑に代行いたします。
また、借地権専門の社内弁護士が常駐しているため、法的なトラブルを未然に防ぎながら、安心・安全にお手続きを進めることが可能です。
ご相談から売却まで、料金は一切いただいておりませんので、借地権のトラブルや売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。