借地権は売却可能!売却を成功に導く地主への交渉術・流れを徹底解説
借地権は売却可能!売却を成功に導く地主への交渉術・流れを徹底解説

目次
「借地権は売却できない…」そう諦めていませんか?
確かに借地権の売却には地主の承諾が必要ですが、交渉次第でスムーズに売却を進めることは可能です。
本記事では、借地権の売却を成功に導くための4つの売却方法や具体的な交渉術、流れを徹底解説します。
トラブルを避け、少しでも高く借地権を売却するためのポイントを知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
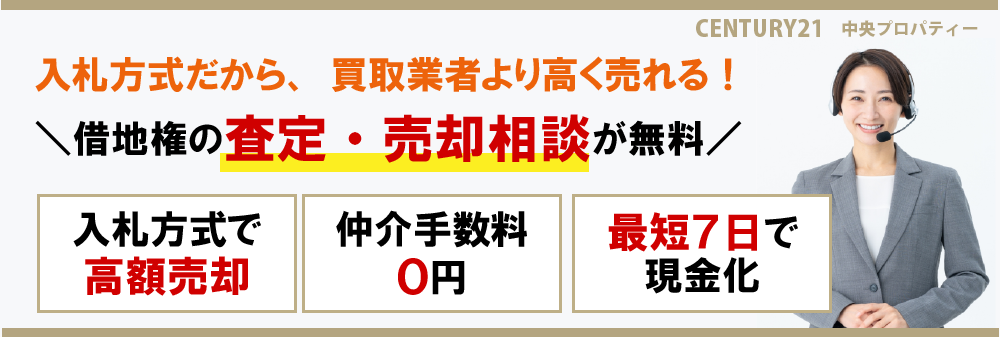
借地権の売却は可能!しかし地主の「譲渡承諾」が必要
借地権付きの建物を売却すること自体は、法律で認められた正当な権利です。
しかし、その際には土地の所有者である地主から「借地権を第三者に譲渡しても良い」という承諾を得る必要があります。
これを「譲渡承諾」と呼びます。
地主が承諾をためらう背景には、「新しい借地人が地代をきちんと払ってくれるか不安」「土地の利用方法をめぐってトラブルが起きないか心配」といった経済的・関係的な懸念があります。
中には、過去の経緯から感情的な理由で反対されるケースも少なくありません。
そのため、普段から地代の支払いを滞りなく行い、良好な関係を築いておくことが、スムーズな売却の第一歩となります。
借地権の売却相場
借地権の売却相場は、画一的に決まるものではなく、「誰に売るか」そして「土地の条件」によって大きく変動します。
一般的に、借地権の価格は更地価格(所有権の土地としての価格)の60%~70%程度が目安とされていますが、これはあくまで参考値です。
例えば、商業地や人気の住宅地など、土地の利用価値が高いエリアでは70%~80%になることもあります。
相場に影響を与える主な要因は以下の通りです。
- 売却相手:地主に売るか、第三者に売るか、地主と共同で売却するかで価格は大きく変わります。一般的に、第三者への売却が最も高くなる傾向があります。
- 土地の立地と条件:路線価、駅からの距離、周辺環境、土地の形状(整形地か不整形地か)などが価格を左右します。
- 借地権の残存期間と地代:残りの契約期間が長いほど、また地代が相場より安いほど、資産価値は高くなります。
正確な売却価格を知るためには、これらの要因を総合的に評価できる、借地権に精通した不動産会社に査定を依頼することが不可欠です。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
借地権の売却方法は4種類
借地権の売却方法は、主に以下の4種類です。
- 地主に買い取ってもらう
- 第三者に売却する
- 地主と「等価交換」を行い第三者に売却する
- 借地権と底地を第三者に「同時売却」する
借地権の売却方法①:地主に買い取ってもらう
地主に建物ごと借地権を買い取ってもらう方法です。
地主にとっては、土地の完全な所有権を取り戻せるという大きなメリットがあります。
地主が建物を買い取る場合、土地上にある建物の解体費用をどちらが負担するかは協議によって決まります。
一般的には、建物を活用する地主がそのまま買い取るか、地主負担で解体するケースが多いですが、建物の状態によっては借地人に解体費用の負担を求められることもあり、事前の協議が重要です。
借地権の売却方法②:第三者に売却する
借地権を地主以外の第三者に売却する方法です。
この方法のメリットは、地主に売却するよりも高値で売却できる点です。
地主に借地権の買取を依頼する場合、高く売りたい借地人と安く買いたい地主は、利益相反の関係にあります。一方、第三者に売却する場合は、不動産市場における需要と供給の原理が働きやすくなります。借地権の価値を適正に評価してくれる買い手を見つけることで、地主との交渉で得られる額よりも高値での売却が期待できる可能性があります。
ただし、売却には地主の承諾が不可欠という大きなハードルがあり、承諾を得るために譲渡承諾料を支払うのが一般的です。
この第三者への売却を成功させる上で最も重要なのが、「誰に売却の相談をするか」という点です。
相談先には大きく分けて「買取業者」と「仲介業者」の2種類があり、どちらを選ぶかで売却結果が大きく変わります。
両者の決定的な違いは、ビジネスの“目的”にあります。
「買取業者」は、借地権を売主から直接安く買い取り、付加価値をつけて高く転売することで利益を得ます。
そのため、できるだけ安く仕入れたい買取業者と、高く売りたい売主とでは、利益が相反してしまいます。
一方で「専門仲介業者」は、売主と買主の間に入って売買を成立させ、その成功報酬として仲介手数料を得ます。
この仲介手数料は売却価格に比例するため、高く売れるほど仲介業者の利益も増えます。つまり、売主と「高く売りたい」という目的が一致するのです。
この違いから、専門の仲介業者に依頼すると、以下のようなメリットが期待できます。
- 市場価格に近い、適正な価格での売却を目指せる。
- 売主の代理人として、有利な条件になるよう価格交渉を行ってくれる。
- 複数の購入希望者を探し、その中から最も良い条件の相手を選べる。
大切な資産である借地権を少しでも有利な条件で売却したいのであれば、売主と同じ目的を持ってくれる専門の仲介業者に相談することが賢明な選択と言えるでしょう。
当社センチュリー21中央プロパティーは、借地権専門の不動産仲介会社です。
これまでに延べ4万件を超えるご相談・売却実績があり、膨大なノウハウの蓄積がございます。
地主との交渉代行が可能なほか、可能な限り好条件での売却をサポートさせていただきますので、「借地権の売却は絶対に失敗したくない」という借地人様こそ、ぜひお気軽にご相談ください。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
借地権の売却方法③:地主と「等価交換」を行い第三者に売却する
借地人と地主がそれぞれの権利(借地権と底地)の価値に応じて土地を分筆し、所有権を交換する方法です。
例えば、借地権と底地の価値割合が6:4であれば、土地全体の面積の6割を借地人の完全所有権の土地に、残りの4割を地主の完全所有権の土地にする、といった形です。
交換によって得た完全所有権の土地は、地主の承諾なく自由に売却できます。
等価交換後に土地や建物を売却する場合、完全所有権の不動産となっているため資産価値が高くなり、借地権単独で売却するよりも高い価格での取引が期待できる点がメリットです。
一方、権利の価値評価や土地の分筆など、多くの手続きや交渉が必要で、時間と労力がかかる点がデメリットです。
借地権の売却方法④:借地権と底地を第三者に「同時売却」する
借地人と地主が協力して、借地権(付き建物)と底地をセットで第三者に売却する方法です。
一般的に、借地権付き建物や底地単体での売却は、活用に制限があるため購入希望者を見つけにくいのが実情です。
しかし、借地権と底地を同時に売却すれば、土地と建物を一体の「完全所有権」の不動産として売却できるため、資産価値が大幅に高まり、買主が見つかりやすくなります。
売主(借地人と地主)にとってはそれぞれ単体で売るよりも高く売れ、買主にとっては自由に活用できる不動産を取得できる、双方にメリットの大きい方法です。
デメリットとしては、売却益の配分(借地人と地主の取り分)を巡ってトラブルになる可能性がある点が挙げられます。
そのため、売却活動を始める前に、専門家を交えて配分割合を明確に決めておくことが不可欠です。
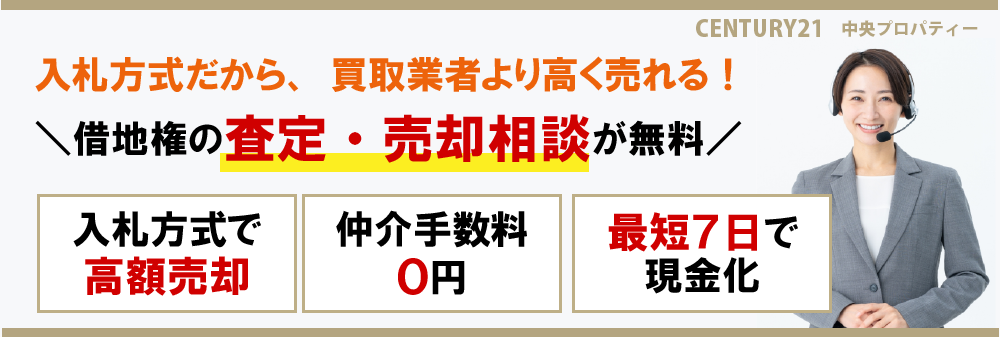
借地権売却の流れ
借地権の売却は、一般的に以下の流れで進みます。
- 借地権専門の不動産会社へ相談
- 借地権の評価・査定を行う
- 地主に交渉し譲渡承諾を得る
- 地主と譲渡承諾の内容(承諾料など)を協議する
- 不動産会社と媒介契約を結び、販売活動を開始する
- 買主が見つかったら、売買契約を締結する
- 代金決済と借地権の引き渡しを行う
借地権の売却を検討する場合、まずは借地権付き建物の査定を行いましょう。
不動産会社によっては、市場価格よりも大幅に低い価格で査定額を提示してくる可能性もあります。
言いなりにならないためにも、複数の会社に相談し、借地権売買の適正価格を把握しておきましょう。
中でも最も重要なのが「地主への交渉」です。
どのように交渉を進めるかによって、承諾がもらえる確率が変わりますので、ご自身で動く前に、まずは地主への交渉前に、借地権専門の不動産会社に相談し、方向性について検討するのが良いでしょう。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
借地権の売却時にかかる費用と税金
借地権の売却にかかる主な費用と税金は、以下の通りです。
- 仲介手数料:不動産の売買契約が成立した際に、仲介を行った不動産会社へ支払う成功報酬。
- 登記費用:不動産の所有者が変わったことなどを法的に記録(登記)する手続きにかかる費用で、登録免許税という税金と、手続きを代行する司法書士への報酬からなります。
- 印紙代:不動産売買契約書など、法律で定められた文書を作成する際に必要となる収入印紙の購入費用。
- 測量費用:土地の正確な面積を測定したり、隣地との境界線を明確にしたりするために専門家(土地家屋調査士)に支払う費用。
- 残置物撤去費用:売却する建物内に残された家具・家電・私物などの不要物を、専門業者に依頼して処分してもらうための費用。
- 解体費用:既存の建物を取り壊して更地にするための工事費用。
- 弁護士費用:法律に関する相談や、交渉・法的手続きの代理を弁護士に依頼した際に支払う報酬。
- 地主への承諾料:借地上の建物を第三者に売却する際に、その許可の対価として土地の所有者である地主に支払う費用。
- 借地非訟の裁判費用:地主が借地権の売却を承諾しない場合に、地主の承諾に代わる許可を裁判所に求める手続き(借地非訟)を申し立てる際にかかる手数料や郵便切手代などの実費。
税金については規定がありますが、仲介手数料をはじめとする不動産会社に支払う費用は、依頼する業者によって大きく異なります。
各社の情報を比較して、できるだけ手出しを少なく、借地権を手放せる手段を探しましょう。
なお、センチュリー21中央プロパティーでは、初回のご相談から売却にいたるまで、すべての料金を0円とさせていただいております。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
借地権を高額売却!買主との「価格交渉」のコツ
借地権売却時における、買主との「売買価格」の交渉のコツは、以下の通りです。
- 相場をもとに交渉する
- 売却希望価格は、値下げされる前提でやや高めに設定する
- 値下げの下限額を決めておく
- 売り出すタイミングを見計らう
- 値引き交渉された場合は、理由を確認し慎重に検討する
借地権の売却時には、「早く売りたい」というお気持ちもあるでしょう。
少々安くても、スピードを重視するか、時間は掛かっても、良い条件で購入してくれる買い手を待つかは、売主の戦略です。
借地権は、大切な資産ですので、時間が許されるのであれば、売り出すタイミング等も見計らい慎重に交渉しましょう。
ただし、借地権の交渉についての注意点は、前提として「借地権は買い手が見つかりにくい」ということを理解しておく必要があります。
借地権は、通常の所有権と比べて、何かと地主の承諾が必要になったり、地代や更新料の負担があったりするため、完全所有権の不動産と比べて、購入希望者が少なく、売買価格も低くなりがちです。
価格交渉をするのは、売主の自由ですが、「買ってもらう」という謙虚なスタンスで売買取引に臨むことを心得ておきましょう。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
地主から譲渡承諾を得るために押さえておくべきポイント
前述の通り、借地権の売却には地主からの「譲渡承諾」が必要です。
借地人が、地主からの譲渡承諾を得るために押さえておくべきポイントは、以下の通りです。
- 日頃からの丁寧な付き合いで、信頼関係を築く
- 地主の不安を解消し、メリットも合わせて提示する
- 当事者での交渉が難しい場合は、専門家への依頼を検討する
地主から譲渡承諾を得るための工夫①:日頃からの丁寧な付き合いで、信頼関係を築く
交渉を円滑に進めるための礎となるのが、地主との良好な信頼関係です。
テクニックを駆使する以前に、普段からの丁寧なコミュニケーションが交渉の成否を大きく左右します。
- 地代の支払いは期日を厳守する:信頼関係の根幹をなす、最も重要な責務です。
- 定期的な挨拶や近況報告を心がける:建物の状況や家族構成の変化など、地主が関心を持つであろう事項について適宜報告することで、誠実な人柄が伝わります。
- 契約内容の遵守:無断での増改築など、契約に反する行為は信頼を著しく損ないます。必ず事前に相談・承諾を得ることが重要です。
借地契約は数十年にわたる長期的な関係です。
普段からの誠実な対応の積み重ねが、重要な交渉の場面で大きな力となります。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
地主から譲渡承諾を得るための工夫②:地主の不安を解消し、メリットも合わせて提示する
実際の交渉においては、地主の立場を理解し、その懸念に応える形で話を進めることが肝要です。
地主が最も懸念するのは、「新しい借地人は信頼できる人物か」「土地の利用や地代の支払いで問題は起きないか」という点です。
この不安を払拭するため、まずは購入希望者の職業や家族構成、購入に至った経緯などを(プライバシーに配慮しつつ)丁寧に説明し、信頼に足る人物であることを示します。
こうした配慮で地主の心理的なハードルを下げると同時に、譲渡承諾は地主にとってもメリットがあることを伝えるのが重要です。
慣習上、借地権の譲渡を承諾する際には、地主は借地人から「譲渡承諾料」を受け取ることができます。
これを提示することで、地主側にも経済的な利点がある取引であることを理解してもらい、協力的な姿勢を引き出すことができます。
地主から譲渡承諾を得るための工夫③:当事者での交渉が難しい場合は、専門家への依頼を検討する
地主との関係性や、交渉内容の複雑さから、当事者同士での話し合いが困難な場合も少なくありません。
その際は、無理に自分だけで進めようとせず、借地権に精通した専門家(不動産会社や弁護士)に交渉を依頼することが極めて有効な手段となります。
地主との交渉を専門家に代理してもらう利点は、主に以下の通りです。
- 豊富な知識と経験に基づき、法的に適切な交渉を行える
- 第三者が介入することで、感情的な対立を避け、冷静な協議が可能になる
- 譲渡承諾料の金額交渉など、借地人にとって有利な条件を引き出しやすい
交渉が難航する前に、あるいは関係性が悪化する前に、専門家の力を借りるという選択肢を検討すること。
これもまた、売却を成功に導くための重要な工夫です。
当社センチュリー21中央プロパティーには、借地権の専門家が多数在籍しております。
延べ4万件を超えるご相談実績の中で、さまざまなパターンの交渉を経験しており、地主様とのやり取りも円滑に代行させていただく自信がございます。
「自分で地主と話がつけられるか不安…」という借地人様は、どうぞご安心のうえ、ご相談ください。

地主から譲渡承諾を得られない場合の対処法
万全の準備をして交渉しても、地主から承諾が得られないケースもあります。
地主から譲渡承諾が得られない場合の対処方法は、主に以下の3種類です。
- 裁判所の許可を得る「借地非訟手続」
- 改めて専門家に相談し、別の解決策を探る
- 最終手段としての「更地返還」
地主から譲渡承諾を得られない時の対処法①:裁判所の許可を得る「借地非訟手続」
地主との協議が平行線に終わった場合の法的な手段が「借地非訟(しゃくちひしょう)手続」です。
これは、地主に代わって裁判所が「譲渡を許可する」判断を下してくれる制度です。
新しい借地人に変わっても地主に不利になる恐れがないと裁判所が認めれば、地主の承諾なしに売却を進めることが可能になります。
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
引用元:借地借家法第19条
ただし、この手続きは「すでに購入希望者が決まっていること」が申し立ての条件です。
そのため、まずは不動産会社に相談して買主を見つけた上で、弁護士に依頼して手続きを進めるのが一般的です。
地主から譲渡承諾を得られない時の対処法②:改めて専門家に相談し、別の解決策を探る
借地非訟は有効な手段ですが、時間と費用がかかります。
そのため、まずは改めて借地権の専門家(不動産会社や弁護士)に相談し、別の解決策がないか探ることも重要です。
専門家であれば、以下のような別の選択肢を提案してくれる可能性があります。
- 地主へのアプローチ方法を変えて再交渉する
- 一般の第三者ではなく、借地権の買取を専門に行う不動産会社に売却する
- 地主側に借地権を買い取ってもらう、あるいは地主と共同で第三者に売却するといった別の売却方法を提案する
一度断られたからといって、道が完全に閉ざされたわけではありません。借地権に詳しい不動産会社に複数社相談し、自分に最適な解決策を見つけましょう。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
地主から譲渡承諾を得られない時の対処法③:最終手段としての「更地返還」
あらゆる手段を尽くしても売却の目途が立たない場合、最後の選択肢として借地権を放棄し、建物を解体して土地を地主に返す「更地返還」があります。
しかし、これは多額の解体費用がかかる上に、資産である借地権の価値がゼロになってしまうため、借地人様にとっては最も避けたい結末です。
「もう面倒だから…」と諦めて更地返還を選ぶ前に、必ず一度は借地権に詳しい弁護士や不動産会社に相談してください。
これまで解説したように、売却できる手段は複数残されています。大切な資産を守るためにも、安易に諦めないことが肝心です。
借地権の売却時に建物は解体すべき?
借地権を売却する際、建物を「解体する」か、「古家付きでそのまま売る」かは、以下の点を総合的に見て判断します。
- 建物の状態: 築年数、劣化状況、耐震性など。
- 買主の意向: リフォームして住みたいのか、新築を建てたいのか。
- 地主の意向: 土地の将来的な利用計画など。
一般的には、解体費用がかからない「古家付き」での売却から検討するのがおすすめです。
【借地権売却時の選択肢①】建物を解体して更地として売却する
建物が著しく老朽化している場合や、買主が更地での購入を強く希望する場合はこちらを選択します。
解体費用の相場と内訳
建物の解体費用は、主に「建物の構造」と「延床面積」によって決まります。
1坪あたりの費用相場は以下の通りです。
- 木造: 4万~5万円
- 鉄骨造: 6万~7万円
- RC(鉄筋コンクリート)造: 7万~8万円
例えば、30坪の木造家屋なら120万~150万円が目安です。
この他に、ブロック塀の撤去やアスベスト除去費用が別途発生する可能性があり、売却益を上回る「費用倒れ」のリスクも考慮しなければなりません。
解体工事の期間と注意点
解体期間は、一般的な木造住宅で2週間~1ヶ月程度です。
また、2023年10月から法改正により、解体前に有資格者によるアスベストの事前調査と報告が義務化されています。信頼できる解体業者に依頼し、法令を遵守して進めることが重要です。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
【借地権売却時の選択肢②】建物を解体せず「古家付き」で売却する
建物がまだ十分に使える状態であれば、こちらの選択が第一候補となります。
売主にとっては解体費用を負担せずに済み、買主にとっては購入後にすぐに住み始めることができるメリットがあります。
ただし、「古家付き」で売却を成功させるには、買主の不安を解消することが鍵です。
ホームインスペクション(住宅診断)を受け、構造上の欠陥や雨漏り、シロアリ被害がないかなど、専門家による客観的な調査報告書を準備しましょう。
建物の状態が明確になることで、買主は安心して購入を検討でき、価格交渉も有利に進めやすくなります。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
まとめ:借地権売却における成功の秘訣
本記事で解説したように、借地権は売却可能です。
しかし、その方法は「地主への売却」「第三者への売却」「同時売却」など多岐にわたり、どの方法を選ぶかで売却価格は大きく変わります。
譲渡承諾を得るための交渉や承諾料の取り決めなど、専門知識なしに有利な条件で進めるのは至難の業です。「地主が話に応じてくれない」「相続したが交渉が不安」といったお悩みから、最終的に更地返還を選んでしまう方も存在します。
そんな時は、当社「センチュリー21中央プロパティー」にご相談ください。
これまでに4万件以上のご相談&売却実績があり、借地権のノウハウの充実度につきましては、他社の追随を許しません。
借地権のエキスパートが、地主との交渉代行や、有利な条件での売却まで誠心誠意サポートさせていただきます。
また、借地権専門の社内弁護士が常駐しているため、いつでも法的観点からの的確なアドバイスが可能となっております。
ご相談から売却まで、お客様にご負担いただく料金は0円となっておりますので、借地権のトラブルや売却でお悩みの借地人様は、どうぞお気軽にご相談ください。
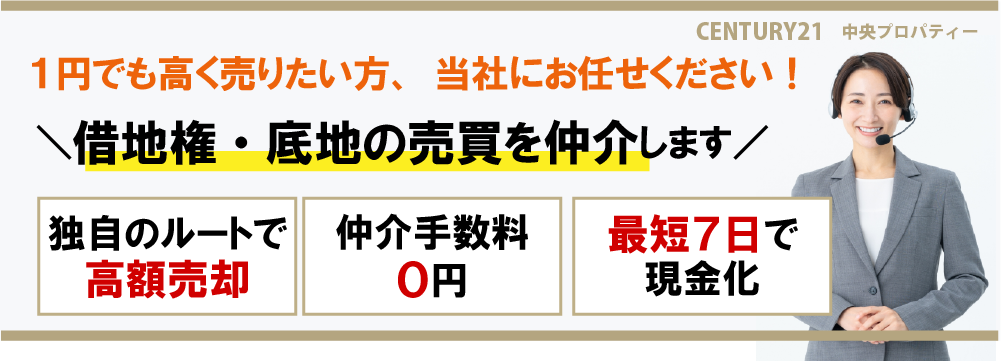
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。





