「地代滞納は10年で時効」は本当?過去の未払い地代を回収する方法
「地代滞納は10年で時効」は本当?過去の未払い地代を回収する方法

目次
地主様にとって、長年にわたり地代が支払われないという状況は、経済的な損失だけでなく、大きな精神的負担となる問題です。
「もう何年も前のことだから、請求できないかもしれない」と諦めてしまうケースも少なくありません。
しかし、法律の正しい知識があれば、過去の未払い地代を回収できる可能性があります。
この記事では、「地代滞納の時効」というテーマに焦点を当て、2020年の民法改正の内容も踏まえながら、大切な資産である土地と権利を守るための具体的な方法を詳しく解説します。
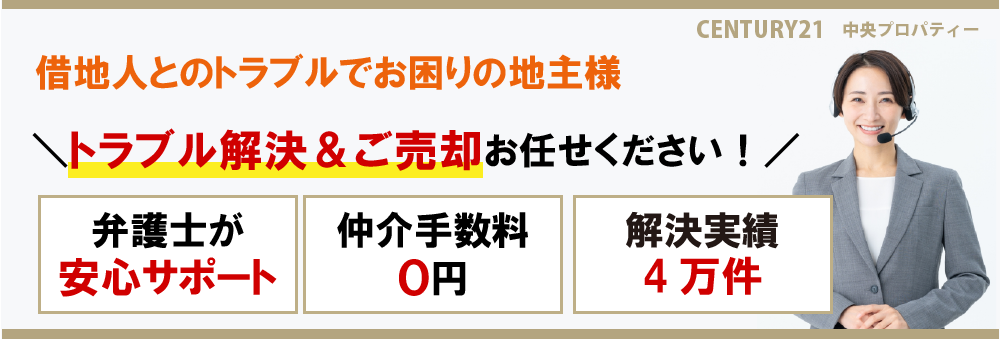
消滅時効とは?
消滅時効とは、権利を一定期間行使しないままでいると、その権利が法律上消滅する制度です。
地代や家賃のような金銭の支払い(債権)も例外ではありません。
2020年4月1日に施行された改正民法により、地代を含む賃料債権の消滅時効期間のルールが明確化されました。
原則として、支払いが滞っている各地代の支払期日の翌日からカウントが始まります。
底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
2020年の民法改正で時効ルールはどう変わった?
2020年4月の民法改正により、消滅時効のルールにおける以下の点が変更されました。
- 時効期間の統一
- 時効が成立する2つの期間(起算点)の明確化
時効ルールの変更点①:時効期間の統一
改正前の民法では、債権の種類によって時効期間が細かく異なっていました。
しかし、改正後は複雑だった短期消滅時効が廃止され、時効期間は原則として以下の2つのいずれか早い方に統一されました。(なお、地代や家賃は改正前から5年の時効期間が適用されていました)
時効ルールの変更点②:時効が成立する2つの期間(起算点)の明確化
現在の民法では、消滅時効が成立する期間の開始日(起算点)が、以下の2パターンに定められています。
- 債権者が権利を行使できることを知ったときから5年(主観的起算点)
- 権利を行使できる時から10年(客観的起算点)
地代の場合、地主様は通常、毎月の支払期日を把握しているため、原則として「支払期日(権利を行使できることを知った時)の翌日から5年」で時効が成立すると考えておきましょう。
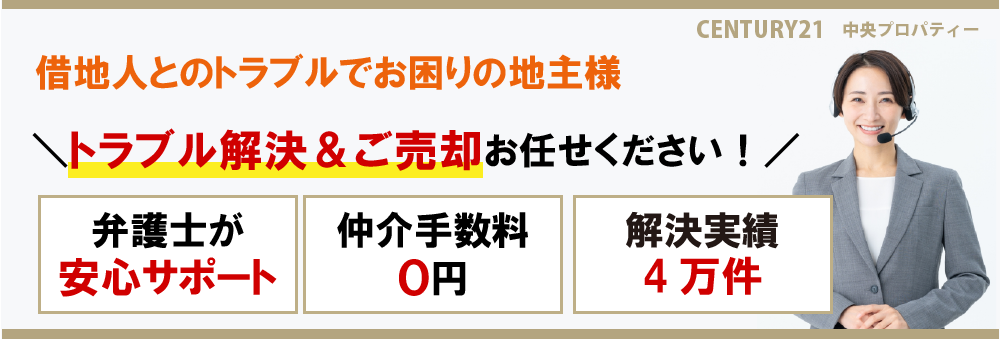
消滅時効の進行を止める・リセットする方法
消滅時効は、先ほど説明した期間が経過すると成立しますが、特定の行動を取ることで、その進行を止めたり、リセットしたりすることができます。
法改正により、従来「時効の中断」と呼ばれていたものは、以下の2点の考え方に整理されました。
- 時効の完成猶予(進行を一時停止する)
- 時効の更新(進行をリセットする)
方法①:時効の完成猶予(進行を一時停止する)
「時効の完成猶予」とは、その名の通り、一時的に時効の成立をストップさせることです。
代表的なのが、内容証明郵便などで行う「催告」です。
催告を行うと、その時から6か月間、時効の完成が猶予されます。
ただし、これはあくまで一時的な措置であるため、この6か月の間に訴訟を提起するなどの次の法的アクションを起こす必要があります。
方法②:時効の更新(進行をリセットする))
「時効の更新」とは、それまで進んでいた時効期間をゼロに戻し、新たにカウントをスタートさせることです。
時効が更新される代表的な事由には、以下のようなものがあります。
- 裁判上の請求(訴訟の提起、支払督促の申立てなど)を行い、権利が確定する
- 強制執行(差押え、仮差押え、仮処分)を行う
- 債務の承認(借地人が支払い義務を認める)
これらの事由が発生すると、その時点で時効の進行はリセットされ、その時から新たに時効期間が進行します。
時効を更新させる重要な行為「債務の承認」とは
時効を更新させる「承認」とは、借地人(債務者)が支払い義務があることを認める行為であり、具体的には下記のようなケースがこれに当たります。
- 「支払います」という内容の債務承諾書(支払約束書)を作成する
- 滞納地代の一部を弁済する
- 支払いの猶予を申し出る
借地人が未払いの事実を認めた場合、これが消滅時効の期間が経過する前であれば、その時点で時効の進行はリセット(更新)されます。
万が一のトラブルに備え、借地人が債務の承認をした場合は、その証拠を必ず書面に残しておくことが重要です。
底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
時効期間が過ぎた後でも地代は回収できる?
では、すでに5年の時効期間が過ぎてしまったら、もう地代は回収できないのでしょうか。
実は、そうとは限りません。
時効が完成した後に、借地人が支払い義務を認める「債務の承認」をした場合、その後に「時効が成立しているから支払わない」と主張すること(時効の援用)は、原則として許されません。
(参考判例:最大判昭和41年4月20日判決)
これは、一度支払う意思を示したにもかかわらず、後から時効を主張して支払いを拒むのは、約束を反故にする行為(信義則違反)とみなされるためです。
つまり、時効期間が過ぎていても、借地人が未払い地代の存在を認めて一部でも弁済した場合、残りの未払い地代を請求できる可能性は高いと考えられます。
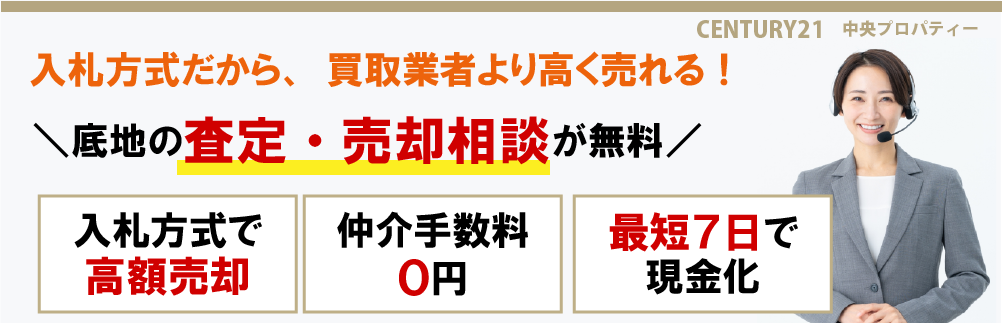
まとめ
本記事では、地代滞納の消滅時効が原則5年であること、そして「催告」や「債務の承認」といった対抗策により、諦めかけていた未払い地代を回収できる可能性があることを解説しました。
しかし、実際に借地人と交渉したり、内容証明郵便を送付したり、さらには支払督促や訴訟といった法的手続きを進めたりすることは、多大な時間と労力、そして精神的な負担を伴います。
どの手続きがご自身の状況にとって最適なのか、判断に迷われることも多いでしょう。
このような複雑でデリケートな地代の問題こそ、底地・借地権を専門に扱うプロの出番です。
センチュリー21中央プロパティは、長年にわたり底地・借地権のトラブル解決に携わってきた専門家集団です。
単なる地代の回収交渉サポートにとどまらず、将来のトラブルを防ぐための管理体制の見直しや、根本的な解決策としての底地売却など、地主様一人ひとりのご状況やご希望に沿った最適なプランをご提案いたします。
一人で抱え込まず、まずは当社の無料相談へお気軽にご連絡ください。専門スタッフが親身にサポートいたします。
底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
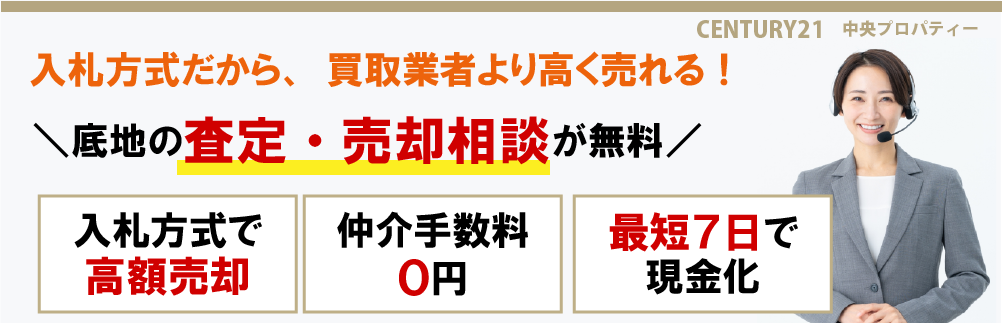
地代に関してよくある質問
地代に関してよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。
Q1.地代を滞納されています。どうしたらいいのでしょうか。
A.地代を滞納された際は、以下の手順で対応するのが基本です。
- 内容証明郵便で地代の支払いを請求する
内容証明を利用するのは、「いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の要求をしたか」を郵便局が証明してくれるため、催告した確実な証拠として残すためです。
将来的に裁判などへ移行する可能性に備え、記録を残す意味でも内容証明郵便の利用を強く推奨いたします。 - 地代滞納が続き、信頼関係が破壊された場合は契約を解除する
長期間(一般的には4~6ヶ月以上が目安)地代の滞納が続き、地主と借地人の間の信頼関係が破壊されたと認められる場合には、借地契約の解除が可能になります。
底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
Q2.時効が成立してしまったら、もう回収は不可能ですか。
A. 時効が成立しても、債権そのものが自然に消滅するわけではありません。
借地人が「時効が成立したので支払いません(時効を援用します)」という意思表示をしない限り、法的な支払い義務は残っています。
そのため、時効期間が過ぎていても、借地人が任意で支払いに応じるのであれば、それを受け取ることは何の問題もありません。
また、前述の通り、時効成立後に借地人が一部を支払うなど「債務を承認」した場合は、時効の援用ができなくなるため、残りの全額を請求することが可能になります。
底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
Q3.内容証明郵便を送っても支払ってくれない場合は、どうすればいいですか。
A. 内容証明郵便による催告を無視された場合は、法的な手続きへ移行することを検討します。
主な手続きは以下の通りです。
- 支払督促
裁判所を通じて、金銭の支払いを督促する手続きです。
相手方が異議を申し立てなければ、訴訟を起こすことなく、強制執行の申立てが可能になります。 - 民事調停
裁判所で調停委員を介して、当事者同士の話し合いによる解決を目指す手続きです。 - 訴訟(少額訴訟・通常訴訟)
最終的な手段として、裁判所に訴えを提起します。
請求額が60万円以下の場合は、原則1回の期日で審理を終える「少額訴訟」を利用できます。
どの手続きが最適かは状況によって異なるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
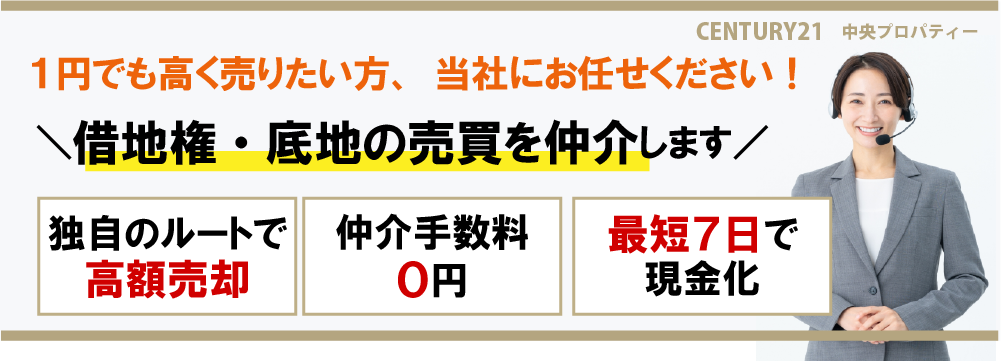
この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で借地非訟手続きや建物買取請求権の行使など今社会問題化しつつある借地権トラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。





