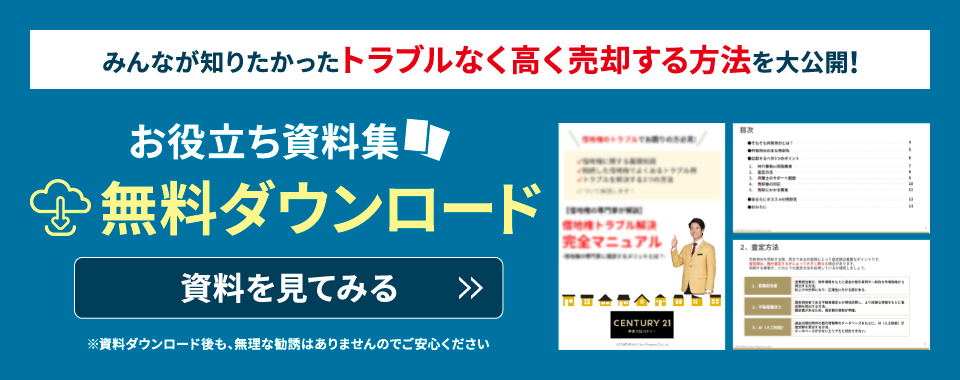借地の家の解体費用が払えない場合の対応策と解体費用を抑える方法を解説|借地権のトラブル
借地の家の解体費用が払えない場合の対応策と解体費用を抑える方法を解説

目次
借地に建っている家を解体する際には、それなりの費用が発生します。費用相場は建物の構造により異なりますが、費用は借地人の負担となるケースが多く、高額な解体費用は払えないと不安に思っている方もいるでしょう。しかし、借家には解体以外にもいくつか手放す方法が存在します。
当記事では、借地の解体費用の負担について詳しく見ていくとともに、借地の処分方法も解説します。借家の扱いにお困りの方はぜひ参考にしてください。

1.借地に建つ家を解体するときの費用負担
借地契約の期間が終了すると、借地人は借りていた土地を地主に返還するか、契約を更新して引き続き土地を借り続けるかを選択することになります。
借地人から地主に土地を返還する場合、借地契約では「原状回復義務」が規定されていることが多く、借地を更地に戻して返還する必要があります。更地に戻すときの建物の解体費用は、原則として借主が負担するのが一般的です。
しかし、契約内容や双方の都合により例外となるケースもあるため、ここでは借地の家を解体するときの費用負担について、いくつかのパターンを解説します。
1-1.借地人の都合で解体する場合
借地人の都合で建物を解体するケースは以下の3つがあり、すべてのケースにおいて原状復帰の解体費用は借地人が負担するのが原則となっています。
契約の更新時に借地人の意思で更新を行わないケース
借地契約の期間が満了し、借地人が借地権の更新を行わない場合、借地に建っている建物を借主負担で解体し、更地に戻して地主に返還します。
借地人の何らかの理由で契約を途中解除するケース
借地契約の途中解除は基本的に認められませんが、やむを得ない事情があれば地主と交渉し、借地人負担で更地にして返還することになります。
契約期間中や更新後に建物を建て直すケース
契約期間中に借地の建物を解体し、新たに建て直す際の処分費用は借地人の負担となります。借地の建物を増改築する場合は、地主の承諾が必要になるケースがほとんどで、地主への承諾料の支払いが必要です。
1-2.地主の都合で解体する場合
地主の都合で解体するケースとは、借主が契約の継続・更新を希望しているにもかかわらず、地主の事情により契約を終了するような場合です。原則として借主が更新を希望した場合は、地主は契約更新に応じなければなりません。
しかし、正当事由があると認められた場合は、借主に「立ち退き料」を支払い、地主が解体費用を負担して更地に戻すことになります。
また、地主側の都合で借地契約が更新されず、かつ借地契約の満了を迎えるタイミングであった場合は、借主が「建物買取請求権」を行使することができます。
建物買取請求権とは、借地の上に建てた建物を時価で地主に買い取ってもらうことができる権利です。
ただし、借主に「地代の未払い」や「借地権の無断譲渡」など契約違反と見なされる理由があれば、地主側からの申し出であっても解体費用は借主の負担となります。
2.解体費用の相場と安く抑えるコツ
借地の建物を解体する費用の相場は、建物の構造によって以下のような金額が想定されます。
| 木造 | 鉄骨造 | RC造 |
|---|---|---|
| 3~4万円/坪 | 4~6万円/坪 | 5~8万円/坪 |
解体費用には、「人件費」「重機使用料」「廃材処分料」といったコストが含まれています。解体現場の立地条件により、警備員を多く配置しなければならなかったり、重機が入れず手作業での解体が必要になったりする場合は、費用が上乗せになることもあるでしょう。
また、建物にアスベストが使われている場合、飛散しないよう集じん・排気装置の設置など、特殊な除去作業が必要になります。アスベストが含まれる廃棄物は処分方法も一般の廃材とは異なるため、費用も高額になる可能性があるでしょう。
解体費用を少しでも安く抑えるためには、家具や電化製品などの不用品はできるだけ自分で処分しましょう。敷地内の庭木や雑草なども処理しておけば、コストカットにつながります。さらに、一部の地域では空き家対策や地域活性化などを目的として、解体工事に補助制度を設けている自治体もあります。補助金を受け取る条件は自治体によって大きく異なるため、事前に確認しておきましょう。

3.解体費用を払えないときはどうする?借地権の処分方法4選
解体には大きな費用がかかるため、借主としては負担をできるだけ減らしたいところです。解体費用は払えないものの、借地上の建物を手放したいときは、解体以外にもさまざまな選択肢があります。それぞれの選択肢について、メリットやデメリットを紹介します。
3-1.地主に買い取ってもらう
借地を手放したい場合、建物や借地権を地主に買い取ってもらうという選択肢があります。地主が「借地を取り戻したい」と考えている場合、地主に買い取ってもらうのがベストな方法だと言えるでしょう。地主が借地権を買い取る場合は譲渡承諾料が発生しないため、借主にとってもメリットが大きくなります。
借地権は明確な取引相場がなく、売買価格は地主との交渉によって決まります。また、「建物も一緒に買い取ってもらうのか」「解体するとすれば費用はどちらが負担するのか」など、さまざまな条件についても意見の調整が必要です。
借地人が自ら地主へ交渉しても、話し合いが難航するケースが多いため、借地権専門の不動産会社に交渉の代行を依頼しましょう。
3-2.底地と合わせて売却する
借主と地主の双方が土地を手放すことを考えているのであれば、借主が持つ「借地」と地主が持つ「底地」を合わせて売却する方法がおすすめです。借地と底地を同時に売りに出すことで、それぞれ単独で売却するよりも高い価格になる傾向があります。ただし、売却価格の配分でトラブルが起こるケースも多いため、お互いによく話し合うことが必要です。
また、買い手は借主・地主の両方と契約を結びます。そのため手続きが複雑になり、多大な時間と労力を費やすこともあります。素人だけで行わず、専門業者に依頼して契約を進めたほうがスムーズに進むでしょう。
3-3.第三者に売却する
地主が借地の買い取りや処分を希望しない場合は、借地権を建物と第三者に売却するという方法も考えてみましょう。借地権を売却する場合、地主に対して「譲渡承諾料」を支払います。また、建物のリフォームを前提として売却するのであれば、「建替承諾料」や「増改築承諾料」が別途必要です。
加えて、売却する建物に住宅ローンが組めるよう、地主に対して建物や借地が担保になることを承諾してもらわなくてはなりません。このように、第三者への譲渡はさまざまな交渉や承諾料が必要になります。
3-4.賃貸として貸し出す
建物や借地権の売却が難しい場合は、借地上の家を第三者に貸し出すという方法もあります。借地権に建つ家を賃貸物件として活用することは法律上の問題もなく、地主の承諾も必要ありません。大規模な改修やリフォームを行う場合は地主の承諾が必要ですが、経年劣化による壁の補修など軽度なものであれば借主の判断のみで行えます。
しかし、地主の承諾が必要な工事については明確な基準があるわけではありません。お互いの信頼関係を保つためにも、事前に相談しておくほうが安心だと言えるでしょう。
借地権の解体費用が払えずお困りの方は、中央プロパティーへご相談ください ≫
4.地主とのこんなトラブルに要注意!
建物の解体をめぐって、地主とのトラブルで多いのは、以下の2つです。
- 解体費用の負担の認識違いがある
- 借地権の売却で地主から多額の承諾料を要求される
借地契約が終了すると、借地人は借地上にある建物を解体して更地で返還しなければなりませんが、その必要性についてはあまり知られていません。
地主と借地人の間で借地の取り扱いに関する認識違いが、トラブルを招くことになります。
また、借地権の売却に関してもトラブルになりやすいポイントです。
借地権付き建物は、借主である借地人が売却できます。しかし、借地は地主にとって収益であるため、売却されると収益源が途絶えてしまい困ります。そのため、借地権の売却では、地主からの承諾と、地主への承諾料の支払いが必要です。
承諾料とは、地主に売却を承諾してもらう費用です。承諾料は法律で金額が定められていないため、高額な承諾料を請求されるトラブルがあります。
ただし、建物を売却する時、地主からの許可の必要性は、借地権が地上権なのか賃借権なのかによって変わります。地上権の場合は、地主からの許可なしに借地権を売却できますが、賃借権の場合は、許可が必要です。
弁護士Q&A
まとめ
借地に建てた家の解体費用は原則借地人の負担となり、建物の構造にもよりますが1坪あたり3~8万円程度の費用がかかります。ただし、地主の都合によって借地契約を解消する場合は建物買取請求権や立ち退き料を請求できる場合もあるため、困ったときは専門家に確認するようにしましょう。また、借地を手放す際は解体以外にも、借地の売却や建物を賃貸として貸し出すといった方法もありますが、いずれにしても地主とのコミュニケーションが不可欠です。

この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。