借地権の相続時にかかる税金はいくら?相続税の計算方法を解説
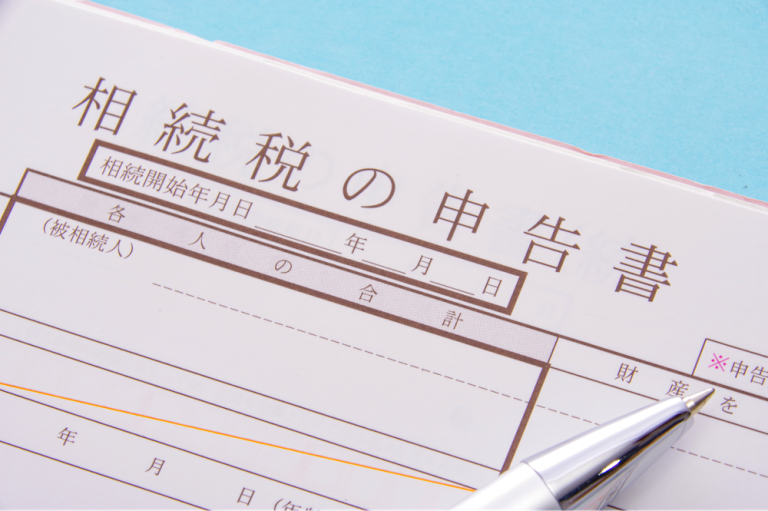
目次
借地権の相続時には、相続税、登録免許税などの税金がかかります。
本記事では、借地権を相続した際にかかる可能性のある税金の種類、特に大きな影響を与える相続税の計算方法について、分かりやすく解説します。
【無料相談】相続した借地権の活用方法や売却でお悩みの方はこちら ≫
借地権とは
借地権は、主に「普通借地権」と「定期借地権」の二つに分類されます。
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
■ 普通借地権(更新できる借地権)
- 原則30年以上の契約期間
- 更新が可能
- 地主は “正当事由” がない限り更新拒否ができない
- 契約終了時には 建物買取請求権が使える
借地人に非常に強い権利が認められているため、評価額も比較的高くなりやすいのが特徴です。
■ 定期借地権(更新できない借地権)
- 契約更新なし
- 契約満了で建物を解体して更地返還
- 建物買取請求権は基本的に使えない
- 立退料なども請求できない
さらに細かく以下の3タイプに分類されます。
- 一般定期借地権:期間50年以上
- 事業用定期借地権:30年以上50年未満
- 建物譲渡特約付借地権:30年以上+終了時に建物を譲渡
借地人の権利が弱い分、評価額は低くなる傾向 があります。
【4万件超の実績とノウハウ】借地権の高額売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
借地権が相続税の課税対象になる2つの条件

借地権が相続税の対象になる条件は、主に以下の2つです。
- 借りた土地が更地ではなく建物がある状態
- 地代の支払いがある状態
それぞれ詳しく解説します。
条件①:借地に建物が建っている
借地権とは「土地に建物を建てられる権利」のことです。
そのため、建物を建てている場合は 財産として評価され相続税が発生します。
逆に、
- 資材置き場
- 駐車場
のように建物がなければ、借地権として評価されないケースがあります。
条件②:地代を支払っている
地代の支払いがある=権利として成立しているため 相続税が発生。
しかし以下のような場合は課税されません。
- 無償で土地を借りて住んでいる
- 親族間で土地を無料貸借している(使用貸借)
つまり、建物の有無 × 地代の有無が課税の判断材料です。
普通借地権の相続税の計算方法
ここでは、普通借地権の相続税の計算方法について解説します。
まず、借地権の相続税を計算は、以下の3ステップで進めます。
- 自用地としての評価額と借地権割合を調べる
- 借地権の相続税評価額を算出する
- すべての相続財産と合わせて最終的な相続税額を算出する
Step1.自用地としての評価額と借地権割合を調べる
普通借地権の相続税評価額の計算式は、以下の通りです。
| 借地権の相続税評価額 = 自用地としての評価額 × 借地権割合 |
借地権の相続税評価額を求めるためには、以下の2つを確認する必要があります。
- 自用地としての評価額
- 借地権割合
a.自用地としての評価額
自用地としての評価額とは、その土地が更地であった場合の評価額です。
自用地としての評価額は、路線価方式または倍率方式で求めることができます。
路線価方式は、市街地など路線価が定められている地域で用いられます。
| 自用地としての評価額 = 路線価 × 土地の面積 × 各種補正率 |
路線価は、道路に面した土地1平方メートルあたりの価格で、国税庁が公表しています。
土地の面積は、そのまま相続する土地の面積です。
各種補正率とは、土地の形状(不整形地、間口狭小など)、奥行き、傾斜などに応じて適用される補正率です。
倍率方式は、路線価が定められていない地域(主に郊外や農地など)で用いられます。
| 自用地としての評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率 |
固定資産税評価額とは、市町村が固定資産税を課税するために評価した土地の価格です。納税通知書などで確認できます。
倍率は、国税庁が地域ごとに定める倍率です。路線価や倍率は、国税庁のウェブサイトで確認することができます。
参考:https://www.rosenka.nta.go.jp/
b.借地権割合
借地権割合とは、その土地の更地価格に対する借地権の価格の割合を示すものです。
これは、地域や借地契約の内容などによって異なりますが、国税庁が地域ごとに30%から90%の間で定めて公表しています。
借地権割合は、一般的に以下の要素を考慮して決定されます。
- 賃料の額: 一般的な相場と比較して高いか低いか。
- 権利金等の授受の有無: 借地契約締結時に権利金などが支払われているか。
- 契約期間: 残存期間が長いほど割合が高くなる傾向があります。
- 地域の慣行: その地域の借地権取引の慣習。
借地権割合も、国税庁のウェブサイトで路線価図などに併記されていることが多いので確認しましょう。
Step2.借地権の相続税評価額を算出する
自用地としての評価額と借地権割合が確認できたら、以下の計算式に当てはめて、借地権の相続税評価額を算出します。
- 借地権の相続税評価額=自用地としての評価額×借地権割合
ここでは、270Dを例にあげてみます。Dの借地権割合は60%です。
路線価図の表記が270Dであれば、1㎡あたりの単価は27万円です。土地の広さが300㎡であれば、27万円×300㎡=8,100万円になります。
そのため、8,100万円×60%=4,860万円が、借地権の相続税評価額となります。
Step3.すべての相続財産を合わせて相続税を算出する
最後に、ほかの相続財産と合算する必要があります。遺産総額を算出し、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額が、相続税の課税対象というわけです。
相続税は、以下の手順で算出します。
- 課税価格の計算:
相続財産から債務・葬式費用を差し引きます。 - 基礎控除額の計算:
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) で計算します。 - 課税遺産総額の計算:
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引きます。 - 相続税の総額の計算:
課税遺産総額に法定相続分と税率を乗じて計算した各相続人の税額を合計します。 - 各相続人の納付すべき税額の計算:
相続税の総額を、各相続人が取得した財産の割合に応じて按分します。 - 税額控除の適用:
配偶者控除や未成年者控除などの税額控除を適用し、最終的な納付額を算出します。
複雑な計算となるため、税理士などの専門家への相談が推奨されます。
定期借地権の相続税の計算方法
定期借地権の価額は、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額で評価されます。
計算方法は非常に複雑 です。
- 残存期間
- 地代
- 建物の価値
- 経済的利益
などを総合して算定しますが、国税庁の通達でも明確な計算式がありません。
国税庁では、定期借地権の相続税の計算式として以下の内容を紹介しています。
画像引用:No.4611 借地権の評価|国税庁
定期借地権の相続税については、借地権に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
【不動産鑑定士とAIのダブル査定】借地権の無料査定サービス ≫
借地権の相続税を軽減する2つの控除枠
借地権の相続税評価額を軽減する方法は、以下の2つです。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者控除の活用
それぞれ詳しく解説します。
控除枠①:小規模宅地等の特例
居住用や事業用の宅地を対象に、一定の要件を満たすことで宅地の評価額を最大80%軽減できる特例です。
相続税の支払いが原因で、残された方が住む家や土地を失ってしまう酷な状況を避けるために導入されました。
適用要件(居住用宅地の場合の概要):
- 被相続人(亡くなった方)が居住していた宅地であること。
- 相続人が配偶者であるか、あるいは一定の条件を満たす親族であること。
- 適用面積:330㎡(100坪)までの部分が対象となります。
詳しくは、国税庁の「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」をご覧ください。
控除枠②:配偶者控除の活用
配偶者控除の活用により、配偶者の法定相続分、または1億6,000万円のいずれか大きい額までの相続税が非課税になります。
この制度を活用することで、借地権の評価額が高くても、そもそも相続税を支払わないで済むケースも少なくありません。
これらの特例の適用には厳密な要件があり、申告期限までの分割手続きが必須となるなど注意点も多いです。
詳しくは、国税庁の「No.4158 配偶者の税額の軽減」をご覧ください。
借地権をトラブルなく・高く売る方法を大公開!資料ダウンロード【無料】はこちら ≫
借地権の相続で相続税以外にかかる税金
借地権の相続で相続税以外にかかる可能性のある税金は、以下の通りです。
- 登録免許税
- 不動産取得税
税金①:登録免許税
登録免許税は、借地権の名義変更登記を行う際に課税される税金です。相続を原因とする借地権の移転登記には、登録免許税がかかります。
税額は、固定資産税評価額に一定の税率(通常は0.4%)を乗じて計算されます。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
ただし、税率は法令改正などにより変更される可能性がありますので、登記申請の際には最新の情報を確認することが重要です。
税金②:不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した際に課税される税金ですが、相続によって借地権を取得した場合は、原則として課税されません。
不動産取得税は、売買や贈与など、有償または無償の移転に対して課税されるものであり、相続はこれに含まれないとされています。
したがって、借地権の相続において、相続税以外に考慮すべき主な税金は登録免許税となります。
借地権をトラブルなく・高く売る方法を大公開!資料ダウンロード【無料】はこちら ≫
相続した借地権を手放す4つの方法

相続によって借地権付き建物を取得したものの、居住や賃貸など活用の見込みがないケースも少なくありません。
しかし、借地権を保有するだけでも以下のコストやリスクが発生します。
- 地代の支払い義務
- 建物の固定資産税の負担
- 空き家管理の手間や老朽化リスク(火災、倒壊、植栽の越境など)
これらの負担を回避するためには、借地権を手放す手段を検討することが重要です。
主な方法として以下の4つが挙げられます。
- 地主に買い取ってもらう
- 第三者に売却する
- 更地にして地主に返還する
- 底地と併せて同時売却する
方法①:地主に買い取ってもらう
借地権の最も手軽な手放し方は、地主による買取です。
地主にとって、土地を再取得して活用できる機会は限られており、タイミング次第では買い取りに応じてもらえる可能性があります。
ただし、借地権の市場価格は一般的に通常の不動産市場よりも低く評価される傾向があります。
したがって、売買価格交渉は借地権の取り扱いに精通した専門の不動産会社を仲介に立てることが推奨されます。
ポイント
- 買取価格は市場相場より低くなるケースが多い
- 交渉は専門会社を通すことで適正価格での売却が可能
方法②:第三者に売却する
地主買取が困難な場合や、可能な限り高額で売却したい場合は第三者への売却が現実的です。
具体的には、不動産仲介会社を通じて買主を探すか、買取業者に直接買い取ってもらう方法があります。
借地権付き建物は通常の不動産売買に比べ専門性が高いため、取扱経験が豊富な不動産会社に依頼することが重要です。未経験の会社では取り扱いを断られることもあります。
注意点
- 借地権売買には契約内容や残存期間、権利金など評価要素が多岐に渡る
- 経験豊富な専門業者を選定することが成功の鍵
方法③:更地にして地主に土地を返還する
借地権を売却せず建物活用も難しい場合、建物を解体し更地に戻して地主に返還する方法があります。
この場合、借地人は解体費用を負担するのが一般的ですが、地主との交渉により費用負担を軽減できる可能性もあります。
建物を所有したままでは、固定資産税や地代負担、管理の手間が継続するため、長期的には不経済となるケースが多いです。
実務上の留意点
- 解体費用の見積もりと地主との費用分担交渉が必要
- 更地返還後の敷地条件に関する契約条項を確認
方法④:底地と併せて同時売却する
借地権だけでなく底地所有者(地主)と協力して、土地全体を第三者に売却する方法もあります。
この場合、完全所有権として取引されるため、買い手にとって魅力が増し、売却価格も高くなる傾向があります。
ただし、同時売却には地主との合意が不可欠です。売却後の取り分や権利関係を事前に明確にしておかないと、後々トラブルの原因となるため注意が必要です。
メリット
- 完全所有権として取引できるため買い手が付きやすい
- 売却価格が単独売却より高額になりやすい
まとめ
本記事では、借地権を相続する際の相続税に関して解説しました。
借地権の相続で相続税がかかるのは、以下の2パターンです。
- 借りた土地が更地ではなく建物がある状態
- 地代の支払いがある状態
借地権付き建物を相続する場合は、基本的に相続税が発生すると覚えておきましょう。
センチュリー21中央プロパティーは、借地権を専門に取り扱う売買仲介会社として、売却やトラブルのサポートを通じて、これまで多くのお客様のお悩みを解決してきました。
相続した借地権の扱いでお困りの方・売却を検討している方は、ぜひ中央プロパティーへご相談ください。
【無料相談】相続した借地権の活用方法や売却でお悩みの方はこちら ≫

地主とのトラブル、借地権の売却にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
税理士
税理士。東京税理士会品川支部所属。日本税務会計学会訴訟部門所属。福島健太税理士事務所代表。不動産デベロッパーから税理士に転身した経歴をもつ不動産と税のスペシャリスト。借地権を相続される方が相続税を、また相続した借地権を売却した際に発生する所得税について相談する税理士として多くの顧客を得る。趣味は釣り。






