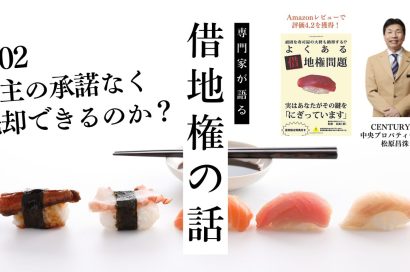【借地権のトラブル事例5選】地主との争いを回避するトラブル解決のポイント

目次
借地権は、土地と建物の所有者が異なる特殊な権利のため、地主との間でさまざまなトラブルに発展しがちです。特に地代や更新料、立ち退きや売却を巡っては、思わぬ問題に直面することも。
本記事では、よくある借地権トラブル事例を厳選して5つご紹介します。
【4万件超の実績とノウハウ】借地権のトラブル解決はお任せください! ≫
借地権のトラブル事例1:突然の地代値上げ要求に困惑したAさんのケース
都内に長年住む70代のAさんは、父親から相続した普通借地権付きの自宅に、奥様と二人暮らし。地代は20年以上据え置きで月3万円を支払っていましたが、ある日突然、地主から「地代を月6万円に値上げする」という通知書が届きました。
年金収入が主な生活費であるAさんにとって、地代が2倍になるのは死活問題です。地主に電話で交渉しようとしましたが、「相場より安いから当然だ」と聞く耳を持ってもらえず、どうすればよいか途方に暮れていました。このままでは自宅を失うのではないかと、眠れない日々が続いていたそうです。
具体的な相談内容
Aさんからのご相談は、「地主の言う通り地代を2倍にしなければいけないのか?」「支払えない場合、この家を出ていかないといけないのか?」という切実なものでした。Aさんのご希望は、「現在の地代に近い金額で、自宅に住み続けたい」という一点にありました。
地主との直接交渉に疲弊していたため、法的な専門知識を持つ弁護士に間に入って解決してほしいというご要望でした。
トラブル解決のポイント
Aさんのケースにおける地代値上げトラブル解決の最重要ポイントは、「安易に地主の要求に応じないこと」と「法的根拠を持った主張をすること」です。
まず、借地借家法第11条に基づき、地代の値上げには「租税公課の増減」「近隣地代との不相当性」「経済事情の変動」といった正当な理由と、相当な金額が求められます。20年据え置きからの2倍への突然の値上げは、著しく不相当である可能性が高いです。
具体的な対応として、決して地主の要求を鵜呑みにせず、従前の地代を支払い続けることが肝心です。もし地主が受け取りを拒否した場合でも、法務局へ地代を供託することで、滞納による契約解除のリスクを回避できます。この「地代供託」は、借地人の権利を守る上で極めて有効な手段です。
次に、地主に対し、値上げの具体的な根拠(資料)の提示を求め、交渉を行います。この交渉は感情的になりやすいため、借地権に強い弁護士や専門の不動産会社といった第三者(専門家)に間に入ってもらうことが不可欠です。専門家は、客観的な適正地代を算出し、法的な根拠に基づいた冷静な交渉を進めます。交渉がまとまらなければ、裁判所に地代増減額請求調停を申し立て、公正な判断を仰ぐことも可能です。
【無料相談】地代の交渉や更新料の支払いでお悩みの方はこちら ≫
借地権のトラブル事例2:契約更新を拒否され立ち退きを命じられたBさんのケース
都心に建つ築50年の借地権付き自宅に住むBさんは、50代の会社員。親から相続したこの家には、幼い頃からの思い出が詰まっています。借地契約の期間満了を3ヶ月後に控え、地主から「老朽化がひどいので、契約は更新しない。土地を更地にして返してほしい」という通知書が届きました。
Bさんは「住み慣れた家を離れたくないし、建て替える資金もない」と、不安と怒りでいっぱいでした。地主は「正当事由がある」と主張し、立ち退きを強硬に迫ってきていました。
具体的な相談内容
Bさんからのご相談は、「地主の言う通り、この家を出ていかなければならないのか?」「老朽化を理由に、自宅を守る方法はないのか?」というものでした。Bさんの最大の希望は、「何としてでも自宅に住み続けたい」というものでした。また、地主との関係が悪化しているため、直接交渉ではなく、専門家が間に入って解決してほしいというご要望でした。
トラブル解決のポイント
地主からの借地契約更新拒否には、借地借家法が定める厳格な「正当事由」が必要です。建物の老朽化だけでは不十分な場合が多く、裁判所は双方の土地利用の必要性、過去の経緯、立ち退き料の有無などを総合的に判断します。長年居住していれば、借地人の権利が強く守られる傾向にあります。
万が一、正当事由が認められ更新が拒否されても、借地人には、地主に建物を時価で買い取るよう請求できる「建物買取請求権」という強力な権利があります。これにより、ご自身で解体費用を負担せず、金銭的補償を得られます。
また、地主との交渉がまとまらない場合は、裁判所に「更新拒絶に対する異議申立て」を行う「借地非訟手続き」も視野に入れます。裁判所が客観的に判断し、契約更新や立ち退き料の支払いを命じるなど、公正な解決が期待できます。
借地権のトラブル事例3:高すぎる更新料を提示され困惑したCさんのケース
地方都市に住む60代のCさんは、親から相続した借地権付きの自宅で一人暮らし。借地契約の期間満了が迫り、地主から更新に関する通知が届きました。その中に記載されていた更新料は、なんと500万円。
Cさんの契約書には更新料に関する記載がなく、過去に更新料を支払った経験もありませんでした。年金生活でまとまった貯蓄もないCさんは、この高額な請求に驚き、「支払わなければ更新できないのか?」「自宅を失うことになるのか?」と途方に暮れていました。
具体的な相談内容
Cさんからのご相談は、「契約書に書いていない更新料を支払う義務があるのか?」「100万円という金額は妥当なのか?」「支払わない場合、契約を更新してもらえないのか?」というものでした。Cさんのご希望は、「法的に適正な金額で契約を更新し、自宅に住み続けたい」というものでした。地主との直接交渉は避けたいという意向も強くありました。
トラブル解決のポイント
まず、更新料の法的義務は契約書に記載がなければ原則としてありません。
地域慣習で請求される場合もありますが、相場は借地権価格の3〜10%程度、または更地価格の数%とされ、500万円は高額な可能性が高いです。
次に、地主が更新料を請求する根拠を明確にしてもらうよう交渉が必要です。Cさんが直接交渉を望まない場合、弁護士などの専門家を通じて交渉を進めるべきでしょう。
もし地主が不当な更新料を主張し、更新に応じない場合は、Cさんは裁判所に「借地非訟」を申し立てることができます。これは、地主と借地人の意見が対立した際に裁判所が介入し、借地契約の更新を許可する制度です。裁判所が更新料の要否や金額、期間を判断するため、Cさんは法的に適正な金額で契約を更新し、自宅に住み続けられる可能性が高まります。
【社内弁護士が常駐】借地権のトラブル解決はお任せください! ≫
借地権のトラブル事例4:借地権付き建物の売却を地主が承諾してくれないDさんのケース
地方都市に住む40代のDさんは、親から相続した借地権付きの自宅の売却を検討していました。転勤が決まり、急遽自宅を売却する必要が生じたため、仲介業者を通じて買主も見つかり、売買契約の寸前まで進んでいました。
しかし、地主に対し、借地権の譲渡の承諾を求めたところ、「見ず知らずの人には貸せない」「この土地は将来自分で使いたい」という理由で、承諾を断られてしまいました。売却できなければ、転勤先での二重の生活費に苦しむことになるため、Dさんは非常に困惑していました。
具体的な相談内容
Dさんからのご相談は、「地主が承諾してくれないと、この借地権は売却できないのか?」「何とか売却を完了させる方法はないか?」というものでした。地主との関係性をこれ以上悪化させずに、円滑に解決したいという意向もありました。
トラブル解決のポイント
借地権の譲渡には、借地借家法19条1項により原則として地主の承諾が必要であり、これがなければ売却は困難です。地主の「見ず知らずの人には貸せない」といった理由は、正当な理由として認められにくいですが、承諾しない自由は地主にあります。
解決策の一つとして、承諾料による交渉が挙げられます。地主が金銭的な理由で承諾を渋っている場合、借地権価格の10%程度とされる承諾料の支払いで解決に至る可能性もあります。ただし、明確な相場はないため交渉次第です。
交渉が難航し、地主が不当に承諾を拒否する場合、Dさんは裁判所に「借地権譲渡の許可申立て」を行うことができます(非訟事件手続法121条)。これは、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出す手続きです。裁判所はDさんの不利益や地主の主張を総合的に判断し、許可の要否を決定します。許可が出れば、地主の承諾なしに借地権を譲渡できますが、地主には「介入権」があり、借地権を買い取ることを希望すればそれが優先される場合があります。
この種のトラブルは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に早めに相談し、適切なアドバイスと支援を受けることが、円滑な解決には不可欠です。
借地権の安全・スムーズな売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
借地権のトラブル事例5:無断増改築を理由に契約解除を通知されたEさんのケース
郊外に住む60代のEさんは、築30年になる借地権付きの自宅に住んでいます。数年前、高齢になった母親との同居のため、費用を抑える目的で地主には無断で離れを増築し、母屋と繋げました。しかし、先日、地主が土地を見に来た際に増築が発覚。地主からは「無断増改築は契約違反だ。直ちに建物を撤去し、更地にして土地を返還してほしい。応じなければ契約を解除する」という内容証明郵便が届きました。
Eさんは、良かれと思って行った増築が、まさか契約解除にまで発展するとは思わず、寝耳に水でした。母親も高齢で、今から引っ越しや解体の費用を工面に悩んでいました。
具体的な相談内容
Eさんからのご相談は、「無断で増築したことは認めるが、契約解除されてしまうのか?」「建物を撤去する費用もなく、どうすれば良いのか?」「地主との関係をこれ以上悪化させずに、この家に住み続けることはできないのか?」というものでした。Eさんの最大の希望は、「増築を理由に契約解除されることなく、この家に住み続けたい」というものでした。
トラブル解決のポイント
まず、無断増改築が直ちに契約解除につながるとは限りません。
借地契約では増改築に地主の承諾が必要な場合が多いですが、裁判所は無断増改築の規模や地主への影響、そして最も重要な信頼関係の破壊の程度を総合的に判断します。軽微な違反で信頼関係が破壊されたとまでは言えない場合、解除が認められないこともあります。
次に、地主が求める原状回復(増築部分の撤去など)の費用をEさんが負担できない場合でも、解決策はあります。地主との交渉を通じて、増改築承諾料を支払って増築部分を合法化する、あるいは将来的な建物の撤去費用を地主が負担するといった代替案を模索することが考えられます。
交渉がまとまらない場合は、Eさんは裁判所に「増改築の許可申立て」を行うことができます(借地借家法17条)。これは、裁判所が増改築の必要性や地主の拒否理由などを考慮し、許可を出す手続きです。許可が得られれば、地主の承諾に代わる法的効果が生じ、無断増築が原因での契約解除を阻止できる可能性があります。
【無料相談】地主から建て替え・増改築の承諾が得られずお困りの方はこちら ≫
借地権トラブルの相談はセンチュリー21中央プロパティー
借地権トラブル解決の鍵は、問題が小さいうちの早期対応と正確な知識です。地主からの要求を鵜呑みにせず、自身の権利(借地借家法)を理解しましょう。また、地主との交渉は感情的にならず、客観的な根拠に基づき行うことが重要です。
そして何より、借地権に強い弁護士や専門の不動産会社など、プロの力を借りて最適な解決策を見つけることが大切です。
センチュリー21中央プロパティーは、借地権専門の不動産会社として、これまで4万件以上のトラブルを解決してきた実績があります。社内には、借地権に弁護士が在籍しているため、法的な視点からトラブル解決のアドバイスが可能です。
借地権のトラブルでお悩みの方は、まずはご相談ください。
センチュリー21中央プロパティーに所属する借地権の専門家はこちら ≫

地主とのトラブル、借地権の売却にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
社内弁護士
当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。