借地借家法をわかりやすく解説!歴史や借地権の種類も紹介

目次
借地借家法は、建物と土地の貸し借りにおいて重要なルールを定める法律です。
しかし、その複雑さから、内容を深く理解できていない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、借地借家法について、その制定に至る歴史的背景や、法律の基本的な特徴、そして借地権の種類などを分かりやすく解説します。特に、土地を貸している地主の方や、借地権をお持ちの借地人の方は、日頃の疑問や将来の不安を解消するための一助として、ぜひご活用ください。
借地権の安全・スムーズな売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
借地借家法とは?

借地借家法とは、土地を借りる賃借人(借地人)と、土地や建物の権利を持つ貸主(地主・家主)双方の立場の差を埋めるために作られた、土地の貸し借りに関する法律です。
民法上は誰もが対等に契約を結べますが、通常の契約だと土地を所有している貸主(地主)よりも賃借人(借地人)は弱い立場になってしまうことが多いため、賃借人を守る目的で作られました。
法律の分野では、私人同士の権利関係などについてまとめた民法は「一般法」にあたり、借地借家法は「特別法」として区別されています。
特別法とは、ある特定の事項について、一般法よりも優先して適用される法律のことです。
特別法である借地借家法は、建物の所有を目的とする借地契約、または借家契約を行うときに適用されます。
借地借家法が制定されるまでの歴史
現在の借地借家法が1992年に施行されるまでには、社会経済状況の変化に伴い、借地人や借家人を保護するための法整備が段階的に進められてきました。借地借家法が誕生するまでの過程は以下の通りです。
- 建物保護ニ関スル法律の制定(1909年)
- 借地法・借家法の制定(1921年)
- 借地法の改正(1941年)
- 借地法の改正(1966年)
- 借地借家法の制定(1992年)
建物保護ニ関スル法律制定(1909年)
明治時代に制定されたこの法律は、借地権保護の重要な一歩となりました。
民法上、借地権を第三者に対抗するためには地上権または賃借権の登記が必要でしたが、この法律により、借地上の建物に登記があれば、借地権の登記がなくとも第三者に対して借地権を主張できるようになりました。
これにより、借地人の地位が強化されました。
借地法と借家法の制定(1921年)
大正時代に入り、都市部への人口集中など社会状況の変化を背景に、「建物保護ニ関スル法律」を基礎としつつ、借地人と借家人をより強力に保護するため、それぞれ独立した法律として「借地法」と「借家法」が制定されます。
特に借地法は、建物所有を目的とする土地利用権の保護を強化し、現在の借地制度の原型となりました。
この時点で、地主が更新を拒絶するには「正当事由」が必要である旨の規定が盛り込まれました(旧借地法第4条)。
借地法の改正(1941年)
戦時体制下において国民生活の安定を図る必要性が高まったことなどを背景に、借地法が改正されました。
この改正では、借地契約の更新拒絶における地主の「正当事由」の要件がより厳格化され、借地人の居住や事業の継続が一層強く保護されることになりました。
これにより、一度土地を貸すと返還を求めることが非常に困難になるという、地主にとって不利な状況も生まれました。
借地法の改正(1966年)
高度経済成長期を経て、借地権の財産的価値が高まる中、借地権の譲渡や転貸に関する規定が整備されました。
地主の承諾が得られない場合でも、借地人が裁判所に申し立て、許可を得ることで借地権の譲渡や転貸が可能となる道が開かれました(借地非訟)。
借地借家法の制定(1992年)
従来の借地法、借家法、そして建物保護ニ関スル法律の3つの法律を統合し、現代の社会経済情勢に合わせて内容を全面的に見直したのが、現行の借地借家法です。
この新法施行に伴い、旧来の3法は廃止されました。
ただし、旧法に基づき交わされた借地契約や借家契約については、原則として旧法の規定が引き続き適用される点に注意が必要です。
借地借家法では、以下のような制度の見直しや新たな制度の創設が行われました。
- 借地権の存続期間の見直し(普通借地権の当初期間を原則30年とするなど)
- 契約の更新がない「定期借地権」制度の創設
- 普通借地権の更新後の存続期間の短縮(2回目以降は10年)
もともと借地権は、権利を持つ地主に有利な制度でしたが、明治期以降、借地人の権利は徐々に強化されてきました。
特に昭和期の借地法改正では旧法では、借地人保護の色彩が非常に濃くなり、地主にとっては一度貸した土地の返還が極めて難しいという側面がありました。
バブル経済期などを経て、土地利用の硬直化や新規の借地供給の停滞といった問題も指摘されるようになり、より合理的で多様なニーズに対応できる借地借家関係の実現を目指して、現行の借地借家法が制定されました。
借地権をトラブルなく・高く売る方法を大公開!資料ダウンロード【無料】はこちら ≫
借地借家法で定められている借地権の種類

借地借家法で定められる借地権とは建物の所有目的で土地を借りる権利を指します。
この借地権は、契約の更新が可能かどうかという観点から、大きく「普通借地権」と「定期借地権」の2つに分類されます。
この二つの権利は、更新の有無だけでなく、存続期間や契約終了時の取り扱いなど、様々な点で特徴が異なります。
ここでは、普通借地権と定期借地権について詳しく解説します。
普通借地権
普通借地権は、契約の更新が予定されているタイプの借地権です。
当初の存続期限は最短30年と定められており、契約者同士の合意によって30年以上の期間を定めることも可能です。
契約期間が満了し、借地人が更新を希望する場合、1回目の更新では20年以上、2回目以降の更新では10年以上の期間を改めて設定し、契約を継続することができます。
また、地主が契約の更新を拒否するためには「正当な事由」が必要とされ、この正当事由が認められない限り、借地人が希望すれば原則として借地契約は更新されます。
正当事由の有無は、主に以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。
- 建物の滅失があった場合
- 地主がほかに土地を所有しておらず、自分の居住のために土地が必要な場合など
万が一、正正当事由が認められて契約が終了することになった場合、借地人は地主に対し、建物を時価で買い取るよう請求することができます(建物買取請求権)。
この請求があった場合、地主は原則として購入を拒否できず、建物の売買契約が成立したものとみなされす。
定期借地権
定期借地権は、普通借地権とは異なり、更新がない借地権です。
これにより、契約期間が満了すれば確実に土地が地主に返還されるため、地主にとっては土地活用の計画が立てやすくなるメリットがあります。
定期借地権は、存続期間や利用目的により以下の3種類に分けられます。
- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権等
- 建物譲渡特約付借地権
一般定期借地権
存続期間は50年以上、借地上に所有する建物の使用目的の制限が設けられていない定期借地権です(居住用でも事業用でも可)。
契約期間満了時、借地人は建物を取り壊し、土地を更地に戻したうえで所有者に返還する必要があります。
一般定期借地権を設定する際には、以下の3つの特約を必ず書面(公正証書などの書面が望ましい)で定める必要があります。
- 契約の更新を行わないこと(更新請求や法定更新を排除する)
- 建物再建による契約の延長をしないこと
- 期間満了後の建物買取請求を認めないこと
事業用定期借地権
借地人が店舗などの事業用建物を所有する場合にのみ設定できる賃借権のことです。
存続期間は10年以上50年未満で設定できます。
事業用定期借地権等では以下の通り、存続期間に応じて契約内容の取り扱いが一部異なります。
- 存続期間が30年以上50年未満の場合:一般定期借地権と同様の3つの特約(更新しない、期間延長しない、買取請求しない)を定めることができる
- 存続期間が10年以上30年未満の場合:上記の3つの特約は、契約による定めがなくとも、法律上当然に適用される
なお、事業用途であっても50年以上の長期契約を希望する場合は、一般定期借地権が適用されます。
建物譲渡特約付借地権
借地契約の存続期間を30年以上とし、契約期間満了時に、地主が借地上の建物を相当の対価で買い取ることをあらかじめ約束する特約が付いた借地権です。
この借地権では、借地上の建物の用途に制限はありません。
契約満了時に地主が借地権者の建物を買い取ることにより、借地権は消滅します。
この特約は口頭でも有効ですが、紛争防止のため書面で明確にしておくことが推奨されます。
【借地権に強い不動産会社】センチュリ-21中央プロパティーがおすすめの理由 ≫
借地権は更新できる?
借地権には、契約期間満了後に更新できるものと、できないものがあり、その違いは設定された借地権の種類によって決まります。。
借地権の種類の違いによる契約更新の可否は以下の通りです。
| 契約更新の可否 | |
| 旧借地法に基づく借地権 (借地借家法施行前) | できる |
| 普通借地権 | できる |
| 定期借地権 (一般・事業用・建物譲渡特約付) | できない |
借地借家法が施行される前の旧借地法に基づいて設定された借地権(旧法借地権)や、現行法における普通借地権は、契約の更新を前提としています。
一方、定期借地権では契約の更新ができない代わりに、存続期間が長めに設定されています。
旧借地権や普通借地権を更新する方法としては、主に以下の3つがあります。
- 合意更新
- 更新請求
- 法定更新
合意更新
地主と借地人が双方の合意のもとで契約内容(更新後の期間、更新料の有無や金額、地代など)を協議し、契約を更新する最も一般的な方法です。
更新請求
借地契約の期間満了に際し、借地人が地主に対して契約の更新を請求する方法です。
借地上の建物が存在する場合、地主側に更新を拒絶する「正当事由」がなければ、原則として従従前と同一の契約内容を引き継ぐ形で更新されます(ただし存続期間は更新後の法定期間となる)。
法定更新
借地契約の期間が満了した後でも、以下の条件を満たせば、法定更新という仕組みにより契約が自動更新されます。
- 借地上に建物があり、借地人が使用を継続している
- 地主が正当事由に基づく異議を申し立てていない
【無料相談】地代の交渉や更新料の支払いでお悩みの方はこちら ≫
借地借家法が適用されている借地権が消滅することはある?
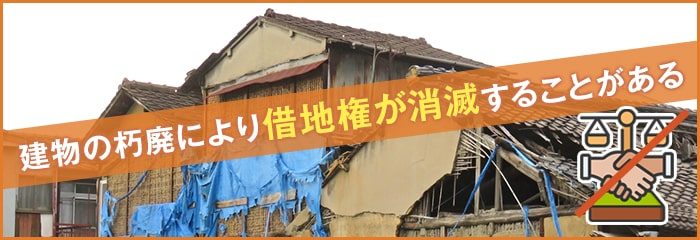
一度設定された借地権は、契約で定められた期間中は原則として存続しますが、一定の事由により期間中や期間満了時に消滅することがあります。
注意すべき点として、旧借地法に基づく借地権の場合、借地上の建物が朽廃(きゅうはい)すれば残存期間内であっても借地権が消滅するとされていました。
朽廃とは、建物が老朽化し、雨風など自然の作用によって社会経済的な効用を失い、居住や使用に適さない状態になることを指します。
単に屋根の一部が損傷している、法定耐用年数を超過しているといっただけでは、直ちに朽廃とは認定されません。
一方、現行の借地借家法に基づく普通借地権であれば、建物が朽廃しても当然に借地権が消滅するわけではありません。
ただし、契約で別途の定めがある場合や、朽廃後の土地利用状況などによっては、契約の更新時に正当事由の判断に影響を与える可能性はあります。
なお、建物が地震や火災、取り壊しなどによって物理的に「滅失(滅失)」した場合でも、借地権そのものは直ちに消滅しません。
借地人は、一定の条件のもとで建物を再築し、借地権を維持することができます(ただし、地主の承諾やそれに代わる裁判所の許可が必要な場合があります)。
これら以外に借地権が消滅する主なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 契約期間の満了と更新の不存在:定期借地権の場合や、普通借地権で更新がなされなかった場合。
- 更新拒絶の正当事由:普通借地権の更新時に、地主側に更新を拒絶する正当事由が認められた場合。
- 契約違反による解除:地代の不払いが継続した場合や、地主に無断で借地権を譲渡・転貸した場合など、借地人に重大な契約違反(信頼関係を破壊する行為)があった場合、地主は契約を解除し、借地権が消滅することがあります。
- 合意解約:地主と借地人が双方の合意により借地契約を解約した場合。
- 混同: 借地人が底地(地主の所有権)を買い取るなどして、借地権と所有権が同一人に帰属した場合。
ただし、借地人に賃料不払いなどの契約違反があった場合でも、その程度や背景にある事情などを踏まえて借地権の消滅が認められないケースもあります。
当事者間の信頼関係が破壊されたと言えない「特段の事情」がある場合には、契約解除が制限されることも判例上示されています。
まとめ
本記事では、借地借家法の仕組みや多様な借地権の種類、存続期間、建物の用途制限といった重要点を解説しました。
これらの内容は複雑で分かりにくい部分もありますが、借地権が予期せず消滅してしまうケースも存在します。
借地人の方は、ご自身の権利を適切に守るためにも、これらの知識を理解しておくことが非常に大切です。
なお、弊社センチュリー21中央プロパティでは、社内弁護士をはじめとした専門家による、借地権トラブルの解決・売却についての無料相談を随時行っています。
適切な権利評価や査定ができる経験豊富な専門家が多数在籍しておりますので、借地権や底地の相続・トラブル・売却などでお困りの場合は、ぜひ安心してご相談ください。
CENTURY21中央プロパティー

地主とのトラブル、借地権の売却にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。






