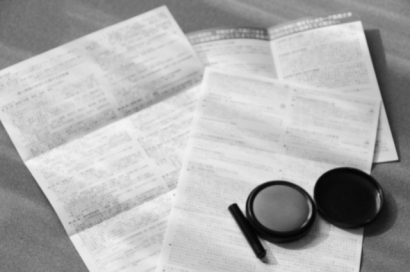借地権が消滅するのはどんなとき?具体事例でわかりやすく解説
借地権が消滅するのはどんなとき?具体事例でわかりやすく解説

目次
借地権は存続期間があっても、消滅してしまうケースがあります。
最悪のケースでは借地権が消滅しているのに、地主から土地の賃料を請求されてしまうこともあります。
また住宅を建て替え・増改築後すぐに借地権が消滅してしまい、地主から立ち退きを命じられて、費用が無駄になってしまうケースも考えられます。
本記事では、借地権が消滅するケースについて詳しく解説します。
<この記事でわかること>
- 旧借地法と借地借家法の借地権の考え方
- 建物が滅失したときの考え方
- 借地権の消滅時効
1. 借地権の消滅とは
借地権の消滅とは、契約期間の満了などの事情によって、地主から土地を借りる権利がなくなることです。借地権の消滅について詳しく理解するために、ここでは以下の2つについて解説します。
- 借地権とは
- 朽廃と滅失の違い
1-1 借地権とは
借地権とは、借地人が地代を支払い地主から土地を借りて建物を自由に建てられる権利です。つまり、建物の所有を目的に土地を借りる権利とも言えます。
借地権は「賃借権」と「地上権」の2つの権利に分けられ、以下のような違いがあります。
| 賃借権 | 土地の賃貸借契約に基づき、借りた土地を借地人が自由に使える権利。地主の許可がなければ、第三者に建物の売却・賃貸ができない。 |
|---|---|
| 地上権 | 借地人が建物の所有を目的に、地主の土地を使える権利。地主の許可がなくても、第三者に建物の売却・賃貸ができる。 |
どちらも借地人が地主の土地を使える権利ということは共通していますが、地上権は地主にとって不利な契約のため、一般的に採用されるケースは少ないです。
また借地権を規定する法律には「旧借地法」と「借地借家法」があります。
どちらも土地や建物の賃貸借契約について定めた法律ですが、地主と借地人の権利関係について違いがあります。
1-1-1 旧借地権とは
旧借地法は1992年7月31日に廃止されており、規定された旧借地権は「1度土地を貸すと、2度と帰ってこない」と言われるほど借地人の権利が強く守られていました。
契約期間の下限は建物の種類によって異なり、非強固な建物(木造)と強固な建物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造)によって分けられています。
| 非強固な建物 | 強固な建物 | |
|---|---|---|
| 期間を定めていないときの存続期間 | 30年 | 60年 |
| 存続期間 | 20年 | 30年 |
| 更新後の期間 | 20年 | 30年 |
契約期間の下限も借地人の権利を守るために、現在よりも長めに設定されていました。期間を定めていないと、強固な建物であれば契約期間が60年もの長期間になります。
また建物が滅失した場合は、借地権を第三者に対して主張することができないとされていました。つまり建物がなくなってしまうと「借地人が地主から借りている土地だ」と、第三者に対して主張できなくなるということです。
1-1-2 新法とは
旧借地法は「土地を貸したら2度と帰ってこない」と言われるほど、借地人の権利が強かったため、土地を貸すことを躊躇する地主も現れました。
そのような状況では土地が利用されず放置されたままになるため、土地の活用を促すため地主の立場が守られた借地借家法(新法)が1992年8月1日に施行されました。
借地借家法の最も大きな特徴は、普通借地権の他に「定期借地権」が制定されたことです。
定期借地権とは契約期間を定めて、契約期間を過ぎたら地主に特別な事情がなくても借地人から必ず土地を返してもらえる権利です。つまり契約の更新がない借地権とも言えます。
また定期借地権は目的によって以下の3つに分けられています。
- 一般定期借地権:利用目的に制限がない一般的な借地権
- 事業用定期借地権:利用目的が事業用に限られている借地権
- 建物譲渡特約付借地権:利用目的に制限はないが、契約期間後は建物を地主に譲渡・売却する借地権
普通借地権と定期借地権の存続期間の違いを下記の表にまとめました。
| 存続期間 | |
|---|---|
| 普通借地権 | 30年以上 |
| 一般定期借地権 | 50年以上 |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 |
借地借家法では、滅失しても借地権は消滅しません。つまり何らかの理由で借地上にあった建物が滅失しても、第三者に対して借地権を主張できるということです。
1-2 朽廃と滅失の違い
滅失と似た言葉に朽廃(きゅうはい)があります。朽廃は、時間経過が原因で建物がボロボロに老朽化することです。滅失は外的な要因によって、建物がなくなることを言います。
朽廃は建物全体が腐敗しており、通常の修繕では建物としての機能が回復しないかが判断基準です。例えばいつ倒壊するかわからない状態の建物、建物として使用するためには新築と同様の費用がかかる建物が朽廃していると判断します。
滅失は、台風・地震・火事・取り壊しなどによって建物がなくなった状態です。建物が滅失した場合は、建物滅失の登記を行わなければなりません。1ヶ月以内に登記手続きを行わないと、10万円の過料が課される可能性があります。
また建物の「朽廃」では借地権は消滅しますが、建物の「滅失」では借地権は消滅しません。
2. 建物が滅失したら借地権は消滅するの?
建物が滅失(壊れて無くなること)しただけでは、借地権が消滅することはありません。ここでは建物の滅失と再建築について以下の3つを解説します。
- 建物が滅失するケース
- 滅失後に再建築することは可能
- 再建築で借地権の存続期間が変わる
2-1 建物が滅失するケース
建物が滅失するケースは以下のような場合が考えられます。
- 解体
- 火災
- 地震
- 津波
- 洪水
- 土砂崩れ
- 噴火
- 大雪
- 大雨
- 台風・竜巻
上記からも分かるように、建物が滅失したと認められるためには外的要因によって、建物がなくなる必要があります。
2-2 滅失後に再建築することは可能
建物が滅失しても借地権は消滅しないため、建物の再建築や増改築が可能です。まだ1度も更新していない最初の契約期間中は、地主の承諾は取る必要がありません。
基本的に建物が滅失すると、借地人は住む場所がなくなってしまいます。住む場所は、生活を営む上で非常に重要なため、再建築や増改築によって住む場所を確保することは、地主の承諾なく行えます。
ただし1度でも借地契約を更新した場合は、地主の承諾がないと建物の再建築や増改築は行えないため注意が必要です。
また仮に地主から承諾が得られない場合は、以下2つの対処法が考えられます。
- 裁判所から地主の承諾に代わる「代諾許可」を受ける
※代諾許可とは、地主に代わって裁判所が出す許可のことです。 - 土地賃貸借契約を終了して新たな住まいを探す
裁判所から代諾許可が得られた場合は、承諾料に相当する金額を支払います。建替承諾料の相場は更地価格のおよそ3%〜5%です。
2-3 再建築で借地権の存続期間も変わる
建物が滅失した場合、地主から許可を得て建物を再建築すると、借地権の存続期間が「地主の承諾があった日」または「再建築日」から20年延長されます。
また地主の許可は「実際に承諾」以外にも「みなしの承諾」も認められます。
みなしの承諾とは、借地人が地主に対して再建築の通知を行った日から2ヶ月以内に地主から反対意見がなければ、承諾したとみなすことです。
そのため、本来の借地権契約の存続期間が切れるタイミングで建物の再建築を行ったとしても、建物が滅失している状態で地主から許可を得て再建築をすると、本来の契約期間よりも長く土地を借りられます。
ただし建物が滅失していても地主から許可を得ないで再建築した場合は、借地権の存続期間は変わりません。
また定期借地権の場合も、地主から再建築の許可を得ていても、存続期間の延長は認められません。定期借地権の契約満了日には、建物を取り壊して借りた土地を更地にして地主に返却する必要があります。
定期借地権の契約期間があまり残っていないときに建物が滅失した場合は、再建築するか借地契約の解除をするかを考える必要があります。
3. 借地権の消滅時効
借地権が消滅しても未払い賃料の支払いを免れるわけではありません。ここでは、賃料支払いの時効について以下の2つを解説します。
- 賃料支払い請求権は5年間有効
- 過去の地代を地主に請求された場合
3-1 賃料支払い請求権は5年間有効
賃料請求権とは、地主から借地人に対し賃料の支払いを請求できる権利のことです。
民法166条1項1号によると地主の賃料請求権は、5年間有効とされています。言い換えると、地主が借地人に賃料の支払い請求を5年間行わなければ、借地人に賃料を支払う義務はなくなるという意味です。
ただし地主から賃料の支払い催促が行われている場合は、賃料支払い請求権の時効まで逃げ切ったとしても賃料の支払い義務からは免れない可能性があります
賃料支払い請求権の時効は、以下3つのいずれかのことを行うと、時効の成立が猶予されるためです。
- 賃料支払いの催告
- 裁判上の請求
- 賃料の支払いについて協議する旨の合意が書面でなされていること
参考:民法147条
そのため、借地人が当初の賃料支払い請求権の時効まで逃げ切ったとしても、賃料の支払い義務から逃れることは難しいです。
3-2 過去の地代を地主に請求された場合
珍しいケースですが、地主が5年間賃料の請求を忘れていることもあるでしょう。消滅時効が成立している賃料を借地人が支払う義務はありません。
しかし、消滅時効が成立した未払い賃料の「支払い義務」はありませんが「支払ってはいけない」という決まりもありません。そのため消滅時効が成立している賃料を支払ってしまっても、後から返金してもらうことはできません。
またいくら支払い義務がないと言っても賃料を支払わないと、地主との関係が悪化してしまう可能性が高いです。長期間借地を利用する予定であれば、時効が消滅している賃料を支払い、地主との関係を良好にしておくことも選択肢の1つです。
まとめ
この記事では借地権の消滅について解説しました。
借地借家法では、建物が滅失しただけでは借地権は消滅しません。また1度も土地の賃貸借契約を更新していなければ、建物を再建築・増改築することで「地主の承諾を得た日」または「建物を再建築・増改築した日」から20年間存続期間が延長されます。
また仮に借地権が消滅しても、賃料の支払い義務は時効が成立しないとなくなりません。地主の賃料支払い請求権は5年間有効のため、支払いを避けるために時効を待つことは有効ではありません。
借地権が消滅しているのに賃料支払いの請求を受けている方は、専門家に頼るのがおすすめです。
中央プロパティーは、数ある不動産会社の中でも借地権を専門に取り扱う不動産仲介会社です。借地権のことで悩んでいる方は、ぜひご相談ください。

この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で借地非訟手続きや建物買取請求権の行使など今社会問題化しつつある借地権トラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。