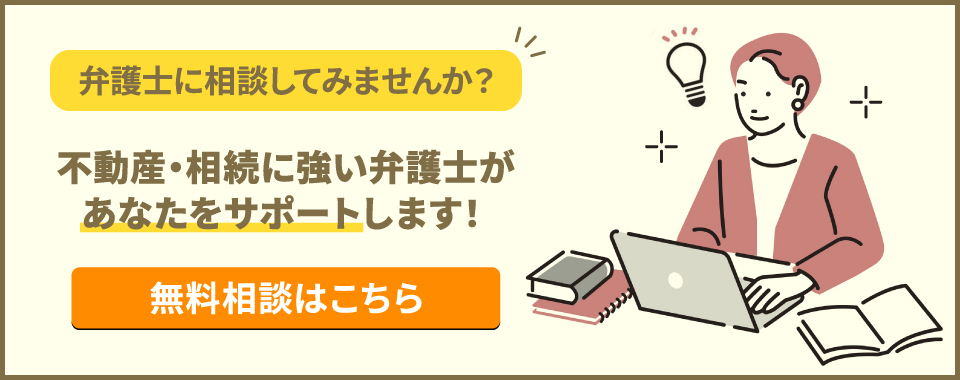準共有借地権とは?借地権の共有状態を解消すべき理由
準共有借地権とは?借地権の共有状態を解消すべき理由
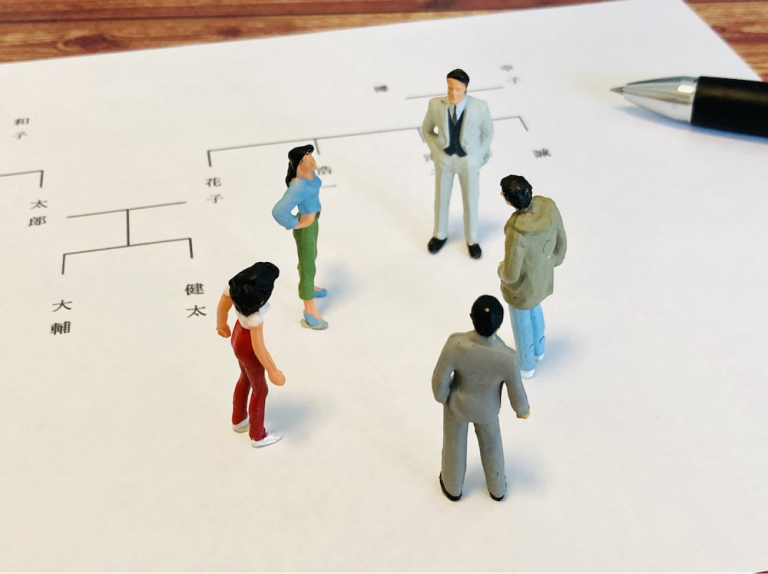
「準共有」とは、借地権や賃借権といった”所有権以外の権利”を複数人で分け合って持っている状態を指します。
似た言葉に「共有」がありますが、その違いや法的な意味合いを正確に理解されている方は少ないかもしれません。
特に「準共有借地権」は、その権利関係の複雑さから相続人間や地主との間で予期せぬトラブルを招いたり、いざ売却しようとしても買い手が見つかりにくいといった課題を抱えがちです。
放置することで、問題がさらに深刻化する恐れもあります。
本記事では、主に借地権を相続し準共有状態になってしまった(または、なる可能性のある)方々に向けて、その基本的な知識から具体的な注意点、そして望ましくない準共有状態を解消するための具体的なステップまで、専門的な知見を交えながら詳しく解説します。
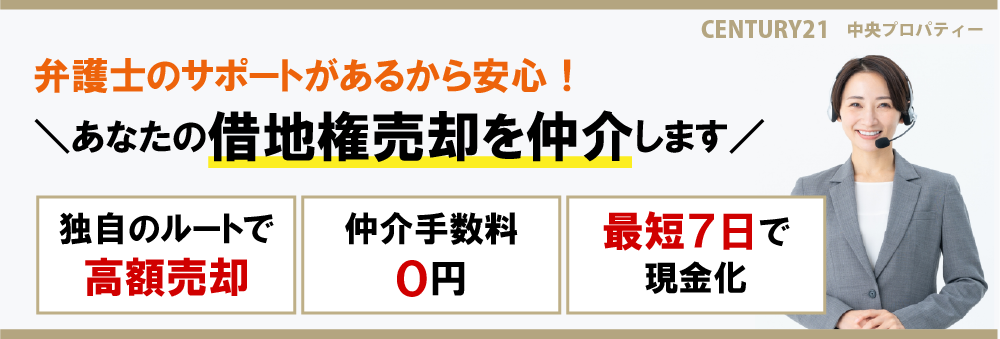
準共有とは
準共有(じゅんきょうゆう)とは、複数の人が一つの財産権を共同で所有する「共有」の考え方を、所有権以外の財産権について準用するものです。
以下の2項目に分けて、詳しく解説します。
- 準共有と共有の違い
- 準共有が発生する主なケース
「準共有」と「共有」の違い
準共有と共有の主な違いは、複数人で分け合って持つ権利の種類にあります。
準共有とは、所有権以外の財産権(例えば、借地権、賃借権、抵当権、特許権、著作権、営業権、さらには金銭債権など)を複数人で共同して有している状態を指します。
一方、共有とは、一つの物(不動産や動産など)の所有権そのものを複数人で分け合って所有している状態を言います。
| 準共有 | 共有 | |
| 対象となる権利 | 所有権以外の財産権 | 所有権 |
| 権利の具体例 | 借地権、賃借権、特許権、著作権、商標権、抵当権、地上権、永小作権、入漁権など、金銭債権も含む | 所有権 |
| 権利の持ち方 | 一つの権利(所有権以外)を、あたかも共同で所有しているかのように複数人で持ち合う状態 | 土地、建物などの不動産、動産など、有体物の所有権 |
| 法的根拠の例 | 民法第264条(共有の規定の準用) | 一つの所有権を、複数人で分け合って持つ状態。 |
| 権利行使の原則 | 各準共有者は、原則として持分に応じてその権利を行使できる。管理行為や変更行為については、共有と同様の多数決や全員の同意が必要となる場合がある。 | 各共有者は、持分に応じて共有物を使用できる。管理行為は持分割合の過半数、変更行為は全員の同意が必要。 |
| 持分 | 原則として各準共有者は均等と推定されるが、別段の合意も可能。 | 原則として各共有者は均等と推定されるが、別段の合意も可能。 |
| 分割 | 共有と同様に、原則としていつでも分割請求が可能(ただし、法令や契約で制限がある場合を除く)。 | 原則としていつでも分割請求が可能(ただし、法令や契約で制限がある場合を除く)。 |
例えば、地主から土地を借りて、その土地の上に自宅を建てたケースを考えてみましょう。
この自宅を子2人が相続した場合、土地を利用する権利である借地権は相続人間で「準共有」の状態となり、建物である自宅の所有権は「共有」の状態となります。
上記の例における借地権のように、土地を借りる権利などを複数人で有している場合、これを単に「共有している」と表現すると、主に有体物の所有権を対象とする「共有」と混同される可能性があります。
そのため、所有権以外の財産権を複数人で有している状態を明確に示すために、「準共有」という法律用語を用いることで権利関係の明確化が図られています。
また、準共有には、基本的に共有に関する民法の規定が準用されます(民法第264条)。
つまり、権利の行使方法や持分割合、分割請求などについては、多くの場合、共有と同様の法的取り扱いがなされます。
借地権で準共有が発生する主なケース
借地権において準共有が発生するケースとしては、以下のようなものがあります。
- 借地権を複数人で相続した場合
- 借地権付きマンションを購入した場合
借地権を複数人で相続した場合
最も一般的なのは、借地権を複数人の相続人で相続するケースです。
例えば、被相続人(亡くなった方)が所有していた借地権を、複数の子が共同で相続する場合、その借地権は相続人全員による「準共有」の状態となります。
この際、借地権の名義人が変わることになりますが、相続を理由とする借地権の取得・名義変更については、原則として地主の承諾を得る必要はありません。
ただし、相続が発生した旨を地主に報告し、今後の地代の支払方法などを協議しておくことは、円滑な関係維持のために不可欠と言えるでしょう。
借地権付きマンションを購入した場合
もう一つの代表例が、借地権付き分譲マンションを購入するケースです。
分譲マンションでは、各住戸(専有部分)の所有権とは別に、そのマンションが建っている敷地を利用する権利(敷地利用権)を各区分所有者が持分割合に応じて有しています。
この敷地利用権が借地権(または地上権)である場合、その借地権を区分所有者全員で「準共有」していることになります。
一方で、敷地利用権が所有権の場合は、土地の所有権を共有している状態(敷地権共有)となります。
ご自身のマンションが借地権付きかどうかは、購入時の重要事項説明書やマンションの管理規約、登記事項証明書(登記簿謄本)、または物件概要で確認できます。
敷地権の種類として「借地権(準共有)」や「一般定期借地権(準共有)」といった記載があれば、敷地の借地権を準共有していることになります。
この場合の準共有借地権は、マンションの専有部分と一体化しており、原則として分離して処分することはできません(建物の区分所有等に関する法律)。
借地権専門の仲介業者:センチュリー21中央プロパティーなら借地権の売却を無料でサポート ≫
準共有借地権はトラブルになりやすい
準共有状態の借地権は、権利者が複数存在することから意思決定が難しく、権利関係も複雑になるため、残念ながらトラブルが発生しやすいという側面があります。
準共有借地権で起こりがちなトラブルとしては、主に以下の2種類があります。
- 相続人同士のトラブル
- 地主とのトラブル
相続人同士のトラブル
準共有者間、つまり多くは相続人間で意見がまとまらず、トラブルに発展するケースは後を絶ちません。
最も大きな原因は、準共有借地権全体を売却したり、借地上の建物を建て替えたりするような重要な決定(法律上の「変更行為」)には、原則として準共有者全員の同意が必要となる点です(民法第251条の準用)。
一人でも反対すれば、これらの行為は実行できません。
例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人の子供が、親の残した「借地上の自宅」と「借地権」を準共有で相続したとしましょう。
AさんとBさんは、自宅も古く、借地権もまとめて売却して現金化し、それぞれ分けたいと考えています。
しかし、Cさんはその家に愛着があり、住み続けたいと希望し、売却に反対しています。
この場合、AさんとBさんが多数派であっても、Cさんの同意がない限り、借地権全体を売却することはできません。
借地権は、立地や条件によっては数百万~数千万円以上の価値を持つこともあり、その処分方法を巡っては、しばしば準共有者間で深刻な対立が生じます。
売却だけでなく、地代や管理費の負担割合、将来的な建て替えの方針など、様々な場面で意見の衝突が起こり得ます。
このような準共有者間でのトラブルを未然に防ぐためには、遺産分割協議の段階で、借地権を特定の相続人が単独で相続するよう努めることが最も望ましい方法です。
例えば、代表相続人が借地権を相続し、他の相続人には代償金を支払う「代償分割」や、全員の合意のもとで売却して金銭で分ける「換価分割」なども有効な手段です。
相続人が一人であれば、活用や処分の方針決定で意見が割れることはありません。
地主とのトラブル
準共有者間だけでなく、土地の所有者である地主との間でもトラブルが生じることがあります。
相続によって借地人の名義が変わる際、地主から「名義変更料(譲渡承諾料とは異なる、相続に伴うもの)」の支払いを求められたり、これを機に地代の値上げや、場合によっては借地の返還を要求されたりするケースが見受けられます。
中には、「契約したのは亡くなった親であり、相続人とは新たに契約条件を協議したい」と考える地主もいるかもしれません。
しかし、法律上、相続によって借地権を取得した場合、地主の承諾を得る必要はなく、名義変更料(この場合の「名義書換料」のようなもの)を支払う義務も原則としてありません。
借地契約は相続人にそのまま引き継がれます。
とはいえ、地主の要求に法的な義務がないからといって、全てを一方的に拒絶することが得策とは限りません。
借地人と地主は、土地の賃貸借契約を通じて長期的な関係が続きます。
将来、建物の建て替えや大規模修繕、あるいは借地権を第三者に売却する際には地主の承諾が必要となり、その際に地主の協力が得られにくくなる可能性があります。
そのため、相続時のトラブルを避け、今後も地主と良好な関係を維持するためには、以下のような点を意識すると良いでしょう。
- 相続が発生した旨を速やかに地主に報告し、挨拶を欠かさない。
- 今後の地代の支払方法や連絡窓口となる代表者を明確に伝える。
- 地主からの要望については、法的な妥当性を確認しつつも、無下に断るのではなく、話し合いの機会を持つ。
- 相続後の契約条件(特に地代支払者など)について、地主との間で覚書を取り交わす。
借地権の準共有状態を解消する方法
借地権の準共有状態を解消する方法は、以下の4種類です。
- 準共有者間で持分を売買する
- 第三者に自己持分のみを売却する
- 借地権を地主に売却する
- 借地権全体を第三者に売却する
準共有者間で持分を売買する
一つ目の方法は、準共有者間で借地権の持分を売買し、特定の1人に権利を集約させる方法です。
これにより借地権の準共有状態は解消され、最終的には一人の準共有者が単独で権利を持つ状態へと移行します。
この方法において、持分を売却する側には、その持分に応じた現金等の対価を得られるというメリットがあり、同時に複雑な権利関係から解放されるという利点も享受できます。
一方、持分を購入する側にとっては、自身の持分が増加し、将来的には単独で権利を所有することになるため、借地権の利用や処分に関する意思決定の自由度が高まるというメリットがあります。
準共有者が共有物に対して行える行為は、その内容によって必要な同意の度合いが異なり、これは借地権の準共有にも準用されます。
共有している借地に対する行為の種類は以下の表の通りです。
| 概要 | 具体例 | 必要な同意 | |
| 保存行為 | 共有物の現状を維持する行為 | 建物の軽微な修繕固定資産税の支払い | 各準共有者が単独で行える |
| 管理行為 | 共有物の性質を変えない範囲での利用・改良行為 | 第三者への賃貸(※地主の承諾が別途必要) | 各準共有者の持分価格の過半数の同意が必要 |
| 変更行為 | 共有物の物理的な変更や法律的な処分行為 | 借地権全体の売却借地上の建物の建て替え契約解除 | 準共有者全員の同意が必要 |
例えば、ある準共有者が他の準共有者から持分を買い取り、その結果、持分価格の過半数を有するに至れば、他の準共有者の反対があっても、地主の承諾を別途得ることを前提に、借地権(上の建物など)を第三者に賃貸する決定が理論上は可能になります。
さらに、全ての持分を1人の準共有者に集約できれば、その借地権は実質的に単独所有の借地権と同様の扱いとなり、その後の利用、建て替え、売却なども(地主の承諾が必要な範囲はありますが)自身の判断でスムーズに進められるようになります。
第三者に自己持分のみを売却する
2つ目の方法は、自身の借地権持分のみを、他の準共有者以外の第三者に売却することです。
この方法であれば、他の共有者の同意は必要なく、単独で売却を進められます。
借地権の譲渡にあたるため、原則として地主の承諾(そして承諾料の支払い)は必要となりますが、他の共有者に気兼ねせず、自分の都合に合わせて資産を整理できる点が大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、借地権の持分のみの売却は、一般的に成立しにくい取引と言えます。
なぜなら、持分の一部だけを購入しても、購入者はその土地を単独で自由に使用・収益・処分することができず、他の準共有者全員の同意がなければ大規模な変更(例:建物の建て替え)も行えないからです。
また、他の準共有者との間で地代の支払いや管理方法などを巡って意見が対立するリスクも抱えることになります。
そのため、借地権の共有持分を売却する際は、センチュリー21中央プロパティーのような、専門の不動産仲介会社を利用することを強くおすすめします。
私たちは借地権・共有持分に関する複雑な権利関係や市場性をよく理解しており、あなたの状況に合わせたベストな売却プランを提案できます。
他の共有者との関係を保ちつつ、あなたの資産をスムーズに現金化するための一つの有効な選択肢として、借地権共有持分の売却を考えてみてはいかがでしょうか。
借地権専門の仲介業者:センチュリー21中央プロパティーなら借地権の売却を無料でサポート ≫
例外的なケース:分譲マンションの敷地利用権としての準共有借地権
上記のような「持分のみ」の売却の難しさとは異なり、分譲マンションの敷地利用権としての準共有借地権は、比較的スムーズに第三者へ売却できるケースが一般的です。
これは、マンションの専有部分(住戸)とその敷地利用権(準共有借地権の持分)が法律上(建物の区分所有等に関する法律)一体として扱われ、原則として分離して処分することができないためです。
つまり、この場合の「準共有借地権の持分の売却」とは、実質的には「マンションの一室(専有部分)の売却」を意味し、それに伴って敷地利用権の持分も一体として買主へ移転します。
購入者にとっては「マンションの一室を購入する」ことと「その敷地の準共有借地権の持分を取得する」ことが同義であり、通常のマンション売買と同様の市場で取引されるため、買い手が見つかりやすいのです。
ただし、借地権付きマンションの売却には、地代、更新料(定期借地権の場合は除く)、借地期間の残存期間など、特有の留意点があります。
そのため、売却を検討する際は、借地権や区分所有法に詳しい不動産仲介会社に相談し、適切な査定や販売戦略について助言を受けることが望ましいでしょう。
安易に専門知識のない業者に依頼すると、適正価格での売却が難しくなったり、後々買主との間でトラブルが生じたりする可能性も否定できません。
借地権を地主に売却する
3つ目の方法は、準共有者全員の合意のもと、借地権そのものを地主に売却する(買い取ってもらう)ことです。
この方法は、地主側・借地人にとってそれぞれ以下のようなメリットがあります。
| 地主のメリット・・・ 底地(借地権の付着した土地所有権)と借地権が一体化し、完全な所有権として土地を自由に利用・処分(再開発、高値での売却など)できるようになる。契約期間満了を待つ必要がなくなる。 |
| 借地人(準共有者)のメリット・・・第三者に売却する場合に比べて、地主が直接の相手であるため交渉が比較的スムーズに進む可能性がある。また、地主にとっては土地の有効活用に繋がるため、市場価格に近い、あるいは状況によっては有利な条件で買い取ってもらえることも期待できる。借地契約に伴う様々な制約や義務からも解放される。 |
しかし、地主には借地権を買い取る法的な義務はありません。
あくまで地主の経営判断や資金状況、将来の土地利用計画などによるため、交渉次第では買い取ってもらえないことも十分にあり得ます。
また、地主が買い取りに前向きな場合でも、買取価格については慎重な交渉が必要です。
借地権全体を第三者に売却する
4つ目の方法は、準共有者全員の同意を得た上で、借地権全体を地主以外の第三者に売却することです。
これは、個々の持分ではなく、一体としての借地権(借地権全体)を市場で売却する形となります。
この方法の最大の前提は、準共有者全員が売却に同意し、売却価格や条件についても合意していることです。
全員の足並みが揃えば、法的には通常の単独所有の借地権を売却するのと同様の手続きで進められます。
売却価格の相場も、個別の持分を売却する場合のような大幅な減価はなく、市場の評価に基づいたもの(市場価格)となります。
ただし、借地権の売買は、所有権の不動産売買と比較して以下のようなハードルがあります。
| 地主の承諾が必要・・・ 借地権を第三者に譲渡(売却)するには、原則として地主の承諾が必要であり、その際には譲渡承諾料(一般的に借地権価格の10%程度)を地主に支払う必要があります。 |
| 活用の自由度が低い・・・ 借地権を購入しても、土地の所有権は地主にあります。そのため、建物の建て替え、大規模な増改築、契約条件の変更(例:堅固な建物への変更)、第三者への転貸など、重要な行為については地主の承諾と承諾料が必要となる場合があります。 |
| 住宅ローンの利用が難しい・・・ 借地権付き建物の購入に対しては、金融機関が住宅ローンを提供しにくい、あるいは条件が厳しくなる場合があります。 |
これらの理由から、特に一般の個人が買い手となる場合、所有権の物件に比べて購入希望者が見つかりにくいことがあります。
そのため、準共有状態の借地権全体を売却する際は、借地権取引に精通し、広範な販売チャネルを持つ、センチュリー21中央プロパティーのような不動産仲介会社に依頼することをおすすめします。
借地権専門の仲介業者:センチュリー21中央プロパティーなら借地権の売却を無料でサポート ≫
準共有借地権の売却時の注意点
準共有借地権を売却する際の注意点は以下の通りです。
- 売却には地主の承諾が必要
- 地主に対する承諾料の支払いが必要
- 借地権は購入希望者が少ない
売却には地主の承諾が必要
借地権(または借地上の建物)を第三者に売却(譲渡)する場合、原則として地主の承諾が必要です。
これは借地契約書にも通常明記されています。
地主に無断で売却してしまうと、重大な契約違反とみなされ、地主から借地契約を解除されてしまうリスクがあります(民法第612条)。
万が一、地主から正当な理由なく売却の承諾が得られない場合には、借地権者は裁判所に対して、地主の承諾に代わる許可(通称「代諾許可」または「借地非訟」)を求める申し立てを行うことができます(借地借家法第19条)。
裁判所は、主に以下の点を考慮し、地主に著しく不利にならないと判断すれば、許可を与えるのが一般的です。
その際、裁判所は、地主への財産上の給付(譲渡承諾料に相当するもので、一般的に借地権価格の10%程度が目安とされますが、事案により異なります)の支払いを条件とすることが多いです。
- 譲受人(購入者)が具体的に決まっていること。
- 譲受人が反社会的勢力に該当しないなど、信頼性に問題がないこと。
- 譲渡によって地主が著しく不利になる恐れがないこと(例:譲受人の地代支払い能力に問題がない、土地の利用方法が契約に反しないなど)。
ただし、この代諾許可の手続きは、申立てから許可(または不許可)の決定が出るまでに数ヶ月(一般的に3ヶ月~半年程度、事案によってはそれ以上)かかることがあります。
相続税の納付期限が迫っているなど、早期に現金化が必要な場合は、時間的な制約を考慮しなければなりません。
このような状況では、借地権取引に詳しい専門の不動産業者に相談し、地主との交渉を円滑に進めるためのサポートを受けることが有効な手段となり得ます。
専門家は、地主への説明や条件交渉を代行し、承諾を得やすくするための助言を提供できます。
中央プロパティーなら売買契約時に弁護士が同席するから安心! ≫
地主に対する承諾料の支払いが必要
前述の通り、借地権を第三者に売却する際には、地主の承諾を得る必要がありますが、それに伴い、譲渡承諾料(または名義変更料とも呼ばれます)を地主に支払うのが一般的です。
この譲渡承諾料の金額は、法律で一律に定められているわけではありません。
借地契約書に規定がある場合はそれに従いますが、規定がない場合は地主との協議によって決定されます。
一般的には、借地権価格(売買価格ではないことに注意)の10%程度が相場とされていますが、地域や個別の事情によって変動します。
借地人側が相場とされる承諾料の支払いを申し出ても、地主が売却自体に難色を示したり、より高額な承諾料を要求したりして、承諾が得られないケースも残念ながら存在します。
そのような場合には、前述の代諾許可制度の利用を検討するか、あるいは地主との間で承諾料の増額を含めた条件交渉を試みることになります。
ただし、地主からの要求が社会通念上あまりにも法外である場合には、専門家(弁護士など)に相談し、対応を検討する必要があるでしょう。
借地権は購入希望者が少ない
借地権は、主に以下の理由で購入希望者を見つけにくい傾向があると言われています。
- 更新料の負担や更新時期の問題
- 契約の残存期間の短さ
- 権利関係の複雑さと利用上の制約
- 住宅ローンの利用の難しさ
借地権の購入希望者が少ない理由①:更新料の負担や更新時期の問題
借地契約の更新時期が迫っている物件は、購入希望者にとって敬遠される要因の一つとなります。
なぜなら、購入後すぐに契約更新の手続きと更新料の支払い(一般的に更地価格の3~5%程度が目安とされますが、契約や地域により異なります)が発生する可能性があるからです。
また、更新後の地代がどの程度になるかなど、契約条件が不確定な点も買い手にとってはリスクとなります。
このため、購入直後の予期せぬ金銭的負担や交渉の手間を懸念する購入希望者は少なくなりがちです。
(※これは主に普通借地権の場合であり、契約更新のない定期借地権の場合はこの限りではありません。)
借地権の購入希望者が少ない理由②:契約の残存期間の短さ
借地契約の残存期間が短い場合も、購入希望者を見つけるのが難しくなります。
残存期間が短いということは、購入後まもなく契約期間の満了を迎え、上記のような契約更新の手続きや更新料の支払い、地代改定の交渉といった問題に直面することを意味します。
買い手にとっては、長期的な利用計画が立てにくく、不安定な要素と映るでしょう。
特に、定期借地権(契約更新がなく、期間満了とともに土地を更地にして返還しなければならないタイプ)の場合、残存期間の短さは、その土地を利用できる期間が限られていることを直接的に示すため、買い手は非常に限定されます。
借地権の購入希望者が少ない理由③:権利関係の複雑さと利用上の制約
借地権という権利形態そのものが、土地の所有権と利用権が分離しているという点で、権利関係が複雑だと感じられることが多く、これが購入を躊躇させる一因となります。
土地の所有者はあくまで地主であり、借地人はその土地を利用する権利(借地権)を有しているに過ぎません。
その結果、借地上の建物を自由に建て替えたり、大規模な修繕を行ったり、あるいは借地権自体を第三者に売却(譲渡)したり、転貸したりする際には、原則として地主の承諾が必要となり、多くの場合、承諾料の支払いも伴います。
つまり、借地権を持っていても、土地を完全に自由には使えないという制約があります。
さらに、地代の支払い義務が継続し、契約条件によっては将来的に地代が改定される可能性もあります。
また、無断での増改築や長期間の地代滞納など、借地契約に違反する行為があった場合には、地主から契約を解除され、最悪の場合、土地の使用権そのものを失ってしまうリスクもゼロではありません。
これらの複雑な権利関係や制約、潜在的なリスクが、購入希望者にとって心理的なハードルとなり、売却がスムーズに進まない要因となるのです。
借地権の購入希望者が少ない理由④:住宅ローンの利用の難しさ
借地権付き建物の購入を検討する際、多くの購入希望者が直面するのが住宅ローンの利用の難しさです。
一般的に、所有権の不動産と比較して、借地権(およびその上の建物)を担保とする住宅ローンの審査は厳しい傾向にあります。
金融機関が融資を行う際には、万が一返済が滞った場合に担保物件を売却して債権を回収できるか(担保価値)を評価します。
しかし、借地権は以下のような理由から担保としての評価が低くなりがちです。
- 市場価値の相対的な低さ・・・所有権に比べて一般的に売却価格が低い。
- 換価処分の難しさ・・・売却には地主の承諾が必要となるなど、手続きが煩雑で時間がかかる可能性がある。
- 地主との関係・・・地主の協力が得られない場合、売却がさらに困難になるリスクがある。
これらの理由から、金融機関は融資額を低く抑えたり、金利を高めに設定したり、あるいは融資そのものを見送ったりするケースが少なくありません。
全ての金融機関が対応していないわけではなく、一部には借地権付き物件専用のローン商品を用意しているところもありますが、それでも審査基準は厳しいのが実情です。
結果として、住宅ローンを利用しにくいことが買い手の範囲を狭め、現金での購入が可能な層に限定されやすくなるため、売却の難易度を上げる一因となります。
まとめ
準共有借地権は権利関係が複雑で、共有者間や地主との間でトラブルが発生しやすいなど、借地人にとってのデメリットが大きいことがお分かりいただけたかと思います。
とはいえ準共有借地権の取引は需要が低く、スムーズに売却できないケースも珍しくありません。
安心して準共有借地権を売却したい方は、共有不動産を専門にしている不動産会社への依頼をおすすめします。
センチュリー21中央プロパティーは、借地権・共有持分をはじめとした相続不動産に強みを持つ不動産仲介会社です。
社内常駐の専任弁護士に加えて、司法書士や税理士などの専門家とも提携しており、専門的な視点によるトラブル解決と、好条件での借地権売却を信条としております。
さらに、仲介手数料や相談から売却にかかる費用がすべて無料のため、経済的に余裕がない方でも安心して利用いただけます。
準共有借地権の売却についてお悩みの方は、ぜひお気軽にセンチュリー21中央プロパティーまでお問い合わせください。
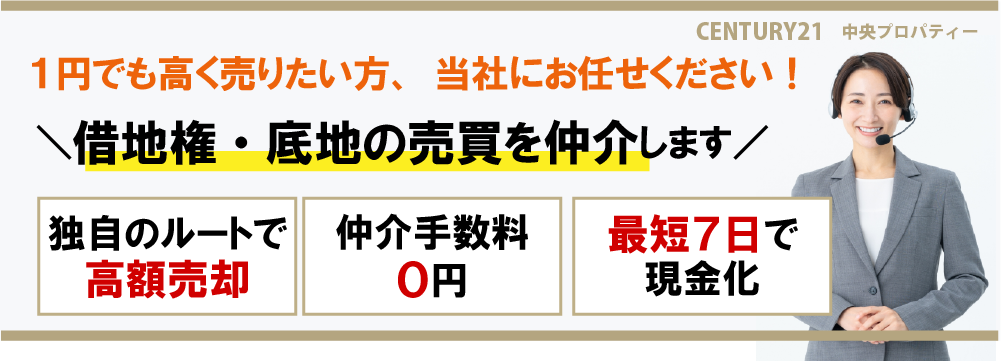
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。