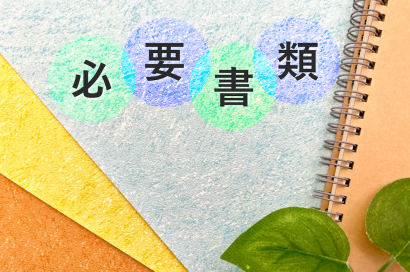借地権でも住宅ローンは利用可能!審査のポイントと金融機関の対応

目次
借地権は一般的な土地の所有権とは異なる性質を持つため、住宅ローン審査でも条件が異なっていたり、金融機関に直接相談したりする必要があります。
本記事では、借地権付き建物で住宅ローンを利用する際のポイントや、金融機関の対応について詳しく解説します。
借地権付き建物の購入を検討している方はぜひ参考にしてください。
【ご相談~売却まで完全無料!】借地権の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
借地権とは

借地権とは、建物を建てる目的で地主から土地を借りる権利です。
借地の上に家を建てる、もしくは借地上の建物を購入する場合、借地権者は建物の所有権を得ることはできますが、土地の所有権は地主が持ち続けます。
借地権には複数の種類があるため、借地上の建物を購入するときはあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
借地権の種類
平成4年(1992年)8月1日以降に成立した借地権は、更新の有無によって「普通借地権」と「定期借地権」に分類できます。
| 普通借地権 | 更新が可能な借地権。 借地権の存続期間は30年以上。 |
| 定期借地権 | 更新がない借地権で、以下の3種類がある。 ①一般定期借地権:土地の使途が自由で、契約期間は50年以上。 ②事業用定期借地権:事業用建物の建設を目的とし、契約期間は10年以上50年未満。 ③建物譲渡特約付借地権:契約終了時に地主が借地上の建物を買い取る特約がある。 |
旧借地権と新借地権
借地借家法は1992年8月1日に改正され、それ以前の契約は「旧借地権」、以降の契約は「新借地権」と呼ばれます。
旧借地権は更新を繰り返すことで半永久的に土地を利用でき、借地人の権利が強いのが特徴です。
一方、新借地権には普通借地権と定期借地権があり、普通借地権は更新可能ですが、定期借地権は契約期間終了後に土地を返還する仕組みで、地主の権利も保護されています。
| 旧借地権 | 新借地権 | |
| 契約適用時期 | 1992年7月31日以前の契約 | 1992年8月1日以降の契約 |
| 契約更新 | 原則更新可能 (半永久的利用可) | 普通借地権は更新可能、定期借地権は更新不可 |
| 土地返還 | 更新拒絶が難しい | 定期借地権は期間満了後に返還必須 |
| 借地人の権利 | 強い | 普通借地権は強い、定期借地権は制限あり |
| 地主の権利 | 制限されやすい | 定期借地権で土地活用がしやすい |
賃借権と地上権
借地権は効力の強さにより、「賃借権」と「地上権」に分類されます。
| 賃借権 | 民法上の債権であり、譲渡には地主の許可が必要。 一般的な借地権は賃借権であることが多い。 |
| 地上権 | 民法上の物権であり、効力が強い。 地主の許可なしで譲渡や登記が可能。 |
借地権付き建物を購入する際の注意点
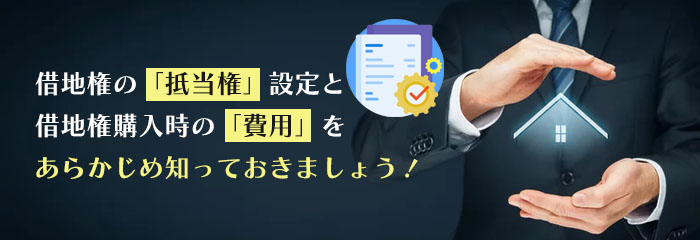
借地権付き建物を購入する際には、土地を所有する場合と異なる点がいくつかあります。
借地権付き建物の購入前に抑えておくべきポイントは、以下の2点です。
- 抵当権の設定
- 購入時の費用
注意点①:抵当権の設定
建物購入時に住宅ローンを借りる際、通常であれば土地と建物に抵当権を設定します。しかし借地権の場合、土地の所有権は地主にあります。
借地権付き建物に抵当権を設定する場合、登記上は建物のみに抵当権が設定されますが、実際は借地権にも抵当権が設定されます。建物及び借地権に抵当権を設定することについて、地主から承諾を得る必要はありません。
ただし、借地契約書に「建物に抵当権を設定する場合は地主の承諾が必要」という旨の記載がある場合は、承諾が必要です。
また、借地権付き建物で住宅ローンを組む際には、地主の署名と捺印がされた「融資承諾書」が必須となります。
注意点②:費用時の費用
借地権付き建物を購入する際には、以下の費用が発生することがあります。
- 権利金:借地権を設定する対価であり、基本的には返金されません。
- 保証金:地代の滞納やその他トラブルがあったときの担保としての金銭で、契約終了時に返還される場合があります。
- 承諾料:建物の譲渡や増改築などを行う際に、地主から承諾を得るために支払う金銭です。
これらの費用は契約内容や地域によって異なるため、事前に確認が必要です。
借地権付き建物のメリット
借地権付き建物には、以下のようなメリットがあります。
- 購入価格を抑えられる:土地を購入する場合と比べて、借地権付き建物は約70~80%の価格で購入できることがあります。
- 土地の税金(固定資産税)の負担が軽減される:土地の固定資産税は地主が負担するため、借地権者は建物部分のみの負担となります。
- 好立地の物件が手に入りやすい:都市部などの好立地にある土地を借りることで、利便性の高い場所に住むことが可能です。
- 普通借地権なら長期居住が可能:普通借地権は更新が認められており、地主に正当事由がない限り契約更新が可能です。
借地権付き建物のデメリット
借地権付き建物のデメリットは以下の通りです。
- 地代や更新料が発生する:地主に地代を支払い続ける必要があり、契約更新時には更新料が発生する場合があります。
- 建て替えや売却に地主の承諾が必要:建物の建て替えや売却を行う際には、地主の承諾が必要であり、承諾料が発生することもあります。
- 住宅ローンの審査が厳しくなる:借地権付き建物は担保価値が低いため、金融機関の住宅ローン審査が厳しくなる傾向があります。
借地権をトラブルなく・高く売る方法を大公開!資料ダウンロード【無料】はこちら ≫
住宅ローンの基本
住宅ローンとは、住宅の購入費用を金融機関から借り入れるローンのことです。
利用するには、借り入れる本人の信用情報や担保となる物件に対して審査を受ける必要があります。
金利には変動金利型や固定金利型があり、借り入れる金融機関によって制度や手数料が異なります。
近年、金利は変動金利・固定金利ともに下落傾向にありました。
しかし、世界的な金利上昇や日本銀行の金融政策により、今後は上昇していく可能性があります。
【ご相談~売却まで完全無料!】借地権の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
借地権付き建物で住宅ローン審査が厳しくなる理由
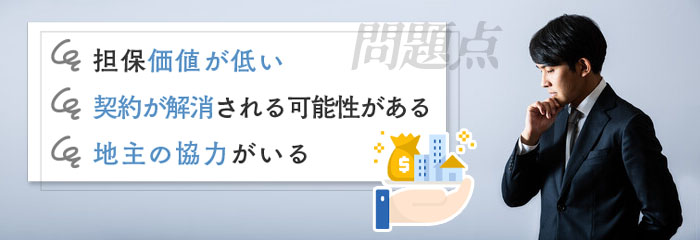
借地権付きの建物を購入する場合、住宅ローンの審査が厳しくなる主な理由は以下の通りです。
- 担保価値が低いため
- 契約解除のリスクがあるため
- 抵当権の設定には地主の協力が必要なため
理由①:担保価値が低いため
借地権付き建物は、土地の所有権がないため、担保価値が低く評価されがちです。
借地権という「土地を借りる権利」を担保にはできるものの、土地そのものを担保とする場合と比べると、担保価値は大きく下がります。
理由②:契約解除のリスクがあるため
借地人が借地契約に違反した場合、地主から契約を解除される可能性があります。
契約違反や建物の使用状況、地主側が建物を必要とする理由によっては「正当事由」が認められ、地主側からの契約解消が可能です。
借地権契約の解除となると、抵当権にも影響が出るため、金融機関はリスクと判断し、審査が厳しくなります。
理由③:抵当権の設定には地主の協力が必要なため
借地権付き建物および借地権に抵当権を設定することについて、契約書に特別な記載がない場合は法律上は地主の承諾は不要です。
しかし、住宅ローンの審査を行う金融機関は、担保価値や債務不履行時のリスク管理の観点から、地主の承諾書を必須としています。
地主の承諾が得られない場合、金融機関は融資に応じないのが実情であり、地主の承諾に代わる裁判所の許可制度も存在しません。
抵当権の設定に難色を示す地主も多く、融資承諾を得られない場合、借地権付き建物の住宅ローン利用は難しくなります。
【借地権に強い不動産会社】センチュリ-21中央プロパティーがおすすめの理由 ≫
借地権付き建物でも住宅ローンを利用できる金融機関
審査が厳しいとはいえ、一部の金融機関では借地権付き建物の購入時に住宅ローンを利用できます。
条件や対応が一般的な建物の購入時と異なる場合もあるため、利用の際は金融機関に一度相談してみるのがおすすめです。
借地権付き建物でも住宅ローンを利用できる金融機関は、以下の通りです。
- 銀行(メガバンク・地方銀行)
- フラット35
- ノンバンク
金融機関①:銀行(メガバンク・地方銀行)
借地権付き土地において一般的な銀行の住宅ローンを利用する場合、その対応は金融機関ごとに大きく異なります。
多くの銀行では、借地権付き物件は通常の所有権付き物件に比べて担保価値が低いと見なされるため、審査が厳しくなりやすい傾向があります。
ただし、普通借地権のみを融資対象とする銀行や、支店ごとに個別判断を行う銀行も存在し、実際の取り扱いについては窓口や電話での事前相談が不可欠です。
融資条件や必要書類、地主からの承諾書の有無など、審査に必要な要件も金融機関ごとに異なるため、まずは希望する銀行に具体的な相談を行い、自身のケースで融資が可能かどうかを確認しましょう。ため、融資をしてもらうには、一度銀行に相談してみましょう
金融機関②:フラット35
フラット35は、住宅金融支援機構が提供する長期固定金利型の住宅ローンであり、借地権付き物件でも一定の要件を満たせば利用できます。
普通借地権の場合は、通常の住宅ローンと同じ借入期間が認められますが、定期借地権や建物譲渡特約付き借地権の場合には、ローンの借入期間と借地権の残存期間を比較し、短い方が上限年数となります。
さらに、フラット35では権利金・保証金・敷金・前払い賃料といった借地権取得費も借入対象に含めることが可能です。
加えて、地主の承諾書がなくても抵当権設定が認められる場合があり、他の金融機関に比べて借地権付き物件への融資が受けやすい特徴があります。
これらの条件を満たすことで、借地権付き物件でも安定した返済計画を立てやすくなります。
金融機関③:ノンバンク
ノンバンクは、融資業務に特化した金融機関であり、銀行に比べて審査基準が柔軟である点が特徴です。
借地権付き建物であっても、ノンバンクであれば融資を受けられる可能性が高まります。
特に、銀行での住宅ローン審査に通らなかった場合や、審査を急ぎたい場合には、ノンバンクの住宅ローンを検討することが有効です。
審査スピードが速いことも大きな利点ですが、その分、金利が高めに設定されるケースも多いため、利用にあたっては返済計画や条件を十分に比較検討することが求められます。
【無料相談】地主から建て替え・増改築の承諾が得られずお困りの方はこちら ≫
借地権付き建物で住宅ローンの審査を通過するためのポイント
借地権付き建物で住宅ローンの審査を通過するためのポイントは以下の通りです。
- 地主との関係を良好に保つ
- 借地契約の内容をしっかりと確認する
- 複数の金融機関に事前相談する
- 明確な資金計画を立てる
- 借地権の専門家に相談する
ポイント①:地主との関係を良好に保つ
借地権付き建物で住宅ローン審査を通過するには、まず地主との関係を良好に保つことが不可欠です。
住宅ローン審査では、借地権に抵当権を設定することが求められる場合がありますが、その際に地主の融資承諾が必要となります。
事前に地主に借地権付き建物の購入計画を伝え、住宅ローンを利用するために抵当権を設定する旨を説明し、理解を得ておくことが大切です。
承諾書を取得し、その中で抵当権設定の同意や承諾料の有無も明記してもらうと安心でしょう。
また、借地料の支払いを滞納しない、地主との日常的なコミュニケーションを大切にするなど、信頼関係を構築することが後のトラブル回避につながります。
ポイント②:借地契約の内容をしっかりと確認する
借地契約の内容を確認することも重要です。
特に確認すべきは契約期間と更新条件です。
普通借地権であれば原則として30年以上の契約期間があり、更新も可能ですが、定期借地権の場合は契約期間が固定されており、更新がありません。
そのため、残りの契約期間が住宅ローンの返済期間を下回ると審査が難しくなる可能性があります。
ポイント③:複数の金融機関に事前相談する
借地権付き建物は金融機関ごとに審査基準が異なるため、複数の金融機関に事前相談を行うことが重要です。
各社の審査条件や金利、対応姿勢を比較することで、自分に最も適した金融機関を見つけられます。
特に、事前審査を実施しておくことで、実際に借り入れを申し込む際の審査通過率が向上します。
また、一社で良い条件が提示された場合、それを基に他社とも交渉できるため、より有利な条件を引き出すことが可能です。
ポイント④:明確な資金計画を立てる
住宅ローン審査では返済能力も重視されます。
そのため、自己資金を多めに用意し、借入額を抑えることで審査が通りやすくなります。
返済比率は年収の25~35%以内に収めることが望ましく、収入証明書や預金通帳のコピーなど、返済能力を証明できる書類も整えておきましょう。
その他の借入(リボ払い、キャッシングなど)はできるだけ整理し、金融機関に「信用力が高い」と評価してもらえるように準備を整えてください。
ポイント⑤:借地権の専門家に相談する
借地権付き建物は通常の不動産取引よりも複雑であり、専門家のサポートを受けることでトラブルを回避できます。
借地権に強い不動産会社は地主との交渉をサポートし、司法書士や行政書士は借地契約の確認や抵当権設定に関する書類の確認を行ってくれます。
さらに、ファイナンシャルプランナーに相談すれば、住宅ローンの返済計画や資金計画の見直しもスムーズです。
こうした専門家の力を借りることで、安心して住宅ローン審査を進めることができます。
弊社センチュリー21中央プロパティーは、借地権を専門とする不動産仲介会社です。
これまでに4万件以上のご相談&トラブル解決実績があり、当社のスタッフは高い交渉スキルや豊富なノウハウを持っています。
他社では解決が難しい案件も、借地権に強い弁護士のサポートにより、円満解決が可能です。
借地権売却だけでなく、「地主からの融資承諾が得られなくて困っている」といったお悩みも、ぜひお気軽にお問合せください。
センチュリー21中央プロパティーに所属する借地権の専門家はこちら ≫
まとめ
借地権付き建物は担保価値が低く、金融機関の住宅ローン審査に通りにくい傾向があります。
また、建物と借地権への抵当権設定には地主の「融資承諾書」が必須であり、地主との交渉が不可欠です。
「地主から融資承諾が得られずに困っている」「住宅ローンを組みたいが審査に通らない」といったお悩みはありませんか?
弊社センチュリー21中央プロパティーは借地権専門の不動産仲介会社として、借地権売却に関するお悩みを受け付けております。
地主とのトラブルや相続した借地権付き建物の建て替え問題など、相談&トラブル解決実績4万件の専門家集団が、社内弁護士と共に円満解決へと導きます。
借地権に関するお悩みは、ぜひ弊社にご相談ください。
【社内弁護士が常駐】借地権のトラブル解決はお任せください! ≫

地主とのトラブル、借地権の売却にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役/宅地建物取引士
都内金融機関、不動産会社での経験を経て、2011年に株式会社中央プロパティーを設立。長年にわたり不動産業界の最前線で活躍するプロフェッショナル。
借地権の売買に精通しており、これまでに1,000件以上の借地権取引や関連する不動産トラブル解決をサポート。底地や借地権付き建物の売却、名義変更料や更新料の交渉など、複雑な借地権問題に従事。
著書に「地主と借地人のための借地権トラブル入門書」など多数の書籍を出版。メディア出演やセミナー登壇実績も豊富で、難解な相続不動産問題も「わかりやすい」と説明力に定評がある。