借地の瑕疵担保責任は誰が負うのか?|弁護士Q&A
借地の瑕疵担保責任は誰が負うのか?

借地人が借地権付建物売却するとのことで、地主も売却を許可し、買主に引渡し後、買主が、地中に埋設物があるのを発見しました。 1. 借地権付建物の売買契約において、土地の欠陥に関する瑕疵担保責任が、売主にあるのでしょうか。 2. 借地権付建物の買主は土地の埋設物の除去を要求していますが、請求は地主である土地の賃貸人にするのでしょうか、それとも借地権付建物の売主にするのでしょうか。

1. 売主は責任を負わない可能性が高い。
2. 賃貸人に土地の埋設物の除去を請求することになる可能性が高い。
1について
「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」
民法612条
とあるように賃貸人の承諾があれば、借地権である土地の賃借権を第三者に譲渡することができます。
賃借権の譲受人は、賃借人の地位を引き継ぐことになります。
民法570条:「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。」
民法566条:「売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。」
とあります。
隠れた瑕疵により契約の目的を達成できない場合、契約の解除ができ、解除ができない場合には、損害賠償の請求をすることができます。
土地の瑕疵か、賃借権の瑕疵か
本件のように土地に欠陥があった場合、瑕疵担保責任はどうなるのでしょうか。借地権付建物売買の目的物は建物と土地の賃借権であり、土地そのものは売買の目的物ではなはないとも考えられます。
参考判例を見てみましょう。
♦参考判例:最高裁平成3年4月2日
判旨:「建物とその敷地の賃借権とが売買の目的とされた場合において、右敷地についてその賃貸人において修繕義務を負担すべき欠陥が右売買契約当時に存したことがその後に判明したとしても、右売買の目的物に隠れた瑕疵があるということはできない。けだし、右の場合において、建物と共に売買の目的とされたものは、建物の敷地そのものではなく、その賃借権であるところ…」
としています。つまり、賃借権付き建物を売買する場合、土地そのものを売買するのではなく、その対象は「借地権」であり、土地そのものの瑕疵とは言えないということです。
よって借地権付建物契約においては、土地は瑕疵の範囲から除かれており、土地の瑕疵補修についての請求はできません。ただし、敷地の面積の不足、敷地に関する法的規制又は賃貸借契約における使用方法の制限等の客観的事由によって賃借権が制約を受けているような場合は借地権の瑕疵となる可能性はあります。
2について
民法601条:「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
民法606条:「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」
とあります。
本件で賃貸人は地主になります。地主は賃貸物の使用収益させる義務があり、その義務を果たすために必要な修繕をする義務を負います。そうすると、土地に賃貸物たる家屋の使用収益に修繕が必要と認められれば、土地の修繕は賃貸人たる地主の負担になります。
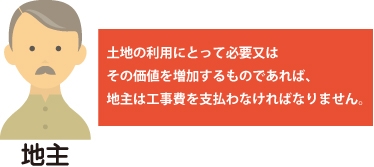

この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で借地非訟手続きや建物買取請求権の行使など今社会問題化しつつある借地権トラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。





