【事例で解説】地代請求権とは~無償の地代を有償に変更したい~
【事例で解説】地代請求権とは~無償の地代を有償に変更したい~

目次
「娘夫婦に土地を無償で貸しているけれど、今からでも地代を請求できるのだろうか?」
大切に思う家族だからこそ、お金の話は切り出しにくいものです。
しかし、土地を無償で貸している「使用貸借」の状態をそのままにしておくと、将来、思わぬ相続トラブルに発展してしまう可能性があります。
この記事では、借地権と底地の専門家が、親子間の土地の無償貸与という状況から、円満に地代を受け取る「賃貸借」へと移行するための具体的な方法と注意点を、実際の相談事例を基に分かりやすく解説します。
将来の家族関係を見据え、トラブルの芽を摘んでおくための第一歩として、ぜひご一読ください。
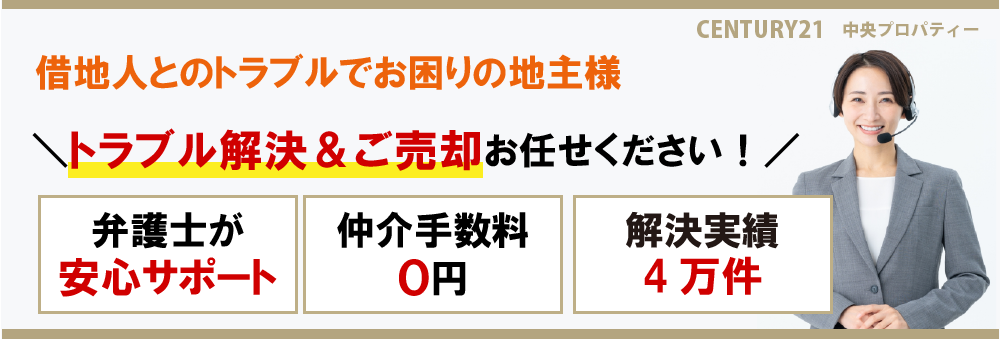
地代請求権とは
地代請求権とは、土地の所有者がその土地を第三者に使用させる対価として、賃料(地代)を請求できる権利を指します。
これは、土地の賃貸借契約に基づいて発生する権利であり、土地の貸し借りが有償であることを前提とします。
民法において、土地の貸し借りの形態には「賃貸借」と「使用貸借」の2種類が定められています。
賃貸借は、地代という対価を受け取ることで土地を使用させる契約であり、貸主には地代請求権が伴います。
一方、使用貸借は、無償で土地を使用させる契約であり、原則として地代請求権は発生しません。
本記事の後半でご紹介する事例のように、親が子に無償で土地を貸している場合は、一般的にこの使用貸借に該当すると考えられます。
底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
【相談事例】無償で貸している土地の地代請求
ここからは、実際の相談事例を基に、地代請求権について分かりやすく解説します。
ご相談内容
私(A)名義の土地に昨年、娘夫婦(B・C)が新居を建築し、今年の4月から住み始めました。
建物の名義は娘(B)とその夫(C)の共有ですが、土地は私(A)の所有であり、登記も済ませています。
最近、「地代請求権」という言葉を初めて聞きました。
建物は昨年の9月に建て始め、完成したのが12月です。
その当時は、地代に関する話し合いをどう進めればよいか全く分からず、結果として現在は無償で娘夫婦を住まわせています。
今からでも娘夫婦と協議して、地代を請求することはできるのでしょうか。

底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
専門家の見解とアドバイス
上記のご相談に対する、専門家の見解をご紹介します。
現在の法律関係:タダ貸しは「使用貸借」
まずは、ご相談者様(A)と娘夫婦(B・C)との現在の法律関係を整理してみましょう。
現在、AはB・Cに土地を貸しておりますが、地代を受け取っていないことから、民法上の「使用貸借」の状態にあると考えられます。
これは簡単に言えば、「タダ貸し」の状態です。
(使用貸借)
民法第593条:「使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」
使用貸借契約の場合、地代は発生しません。
また、使用貸借の場合には、借主を手厚く保護する「借地借家法」の適用がないという点が非常に重要です。
(趣旨)
借地借家法第1条:「この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。」
条文に「賃借権」とある通り、この法律は地代を支払う「賃貸借」を対象としており、「使用貸借」は含まれません。
なぜなら、タダで借りている人と、お金(地代)を支払って借りている人とで保護の範囲が同じというのは不公平だからです(当然、有償契約の借主のほうがより強く保護されるべきです)。
そのため、本件ではそもそも借地借家法の適用はなく、法律関係は民法の規定に従うことになります。
参考までに、使用貸借の終了時期について、民法では以下のように定められています。
(借用物の返還の時期)
民法第597条1項:「借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。」
同条2項:「当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。」
同条3項:「当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。」
本件では、「娘夫婦が家を建てて住む」という目的があるため、一方的に使用貸借契約を終了させることは難しいと考えられます。
底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
地代を請求するには:賃貸借契約への切り替え
さて、ご相談者様(A)が地代を請求したいとのことですが、地代を受け取るようになると、その契約はもはや使用貸借ではなく、「賃貸借契約」に移行します。
よって、現実的な手順としては、まずAからB・Cに対し、現在の使用貸借契約を合意の上で終了し、新たに土地の賃貸借契約を結び直したい旨を提案することが第一歩となります。
娘夫婦からは「今さら地代を払わなければならないの?」といった反発も予想されます。
しかし、もし地代の支払いを拒んだまま土地を使い続けるのであれば、法的には土地を利用する正当な権原(権利)がない「不法占拠」とみなされる可能性もゼロではありません。
その場合、最終的には建物を収去(解体・撤去)するよう求めたり、損害賠償を請求したりすることも法的には可能です。
AとBは親子であり、通常ではここまでの事態は考えにくいかもしれません。
しかし、Aは貸主として、こうした法的な権利を持っているということを知っておくことが重要です。
この権利を背景に、まずは冷静に地代を支払ってほしい旨を伝え、交渉に入ることができます。
地代の相場は、近隣の賃料相場や、土地の固定資産税・都市計画税、路線価などを参考に決定するのが一般的です。
親子間では、まずは土地の固定資産税・都市計画税の年額の2~3倍程度を目安に話し合いを始めるとよいでしょう。
「娘から地代をとるのか!」と感情的な反発を招く可能性もあります。
しかし、例えば適正な地代よりも著しく安く貸し出すと、その差額分が親から子への「贈与」とみなされ、将来の相続時に「特別受益」として扱われる可能性があります。
特別受益があると、その分娘が相続できる財産が少なくなる場合があり、他の兄弟姉妹との間で不公平感を生む原因にもなりかねません。(ただし、他に相続人がいない場合は、この問題は生じにくいです)
話の進め方を間違えると親子関係が悪化することも考えられます。
だからこそ、客観的な判断ができる専門家(弁護士や不動産会社など)を第三者として交え、交渉を進めることが重要です。
この機会を、単なる地代請求ではなく将来の相続まで見据えた財産整理の機会と捉え、親族と真剣に話し合うのも良いかもしれません。
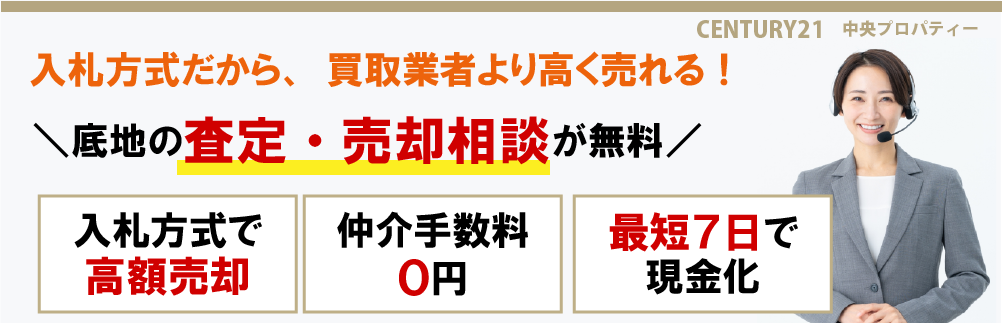
地代請求を円滑に進めるためのポイント
親子という近い関係だからこそ、地代の請求は慎重に進める必要があります。
親子間での地代請求を円滑に進めるためのポイントは、以下の通りです。
- 丁寧な説明と理解を求める姿勢
- 専門家の介入を提案する
- 段階的な地代設定を検討する
- 書面での契約締結を徹底する
- 相続税対策としての地代の考慮
丁寧な説明と理解を求める姿勢
感情的に「地代を払ってほしい」と伝えるだけでは、関係がこじれる原因になります。
なぜ地代が必要なのか、その理由を丁寧に説明することが不可欠です。
例えば、「土地の固定資産税の負担が大きい」「将来の相続で兄弟間の不公平をなくしたい」など、具体的な理由を誠実に伝え、理解を求めましょう。
底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
専門家の介入を提案する
当事者同士の話し合いでは、どうしても感情が先行しがちです。
「お金の話だからこそ、専門家を間に入れて冷静に決めたい」と提案することで、相手も受け入れやすくなります。
弁護士や税理士、不動産コンサルタントといった第三者が入ることで、法務・税務に基づいた客観的な話し合いが可能になり、円満な合意形成を助けます。
底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
段階的な地代設定を検討する
娘夫婦の経済的な負担も考慮し、柔軟な対応を検討することも大切です。
例えば、初年度は固定資産税額程度の低い金額からスタートし、数年かけて段階的に適正な地代に近づけていく、といった方法も有効です。
相手の状況を思いやる姿勢を見せることで、交渉がスムーズに進みやすくなります。
底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
書面での契約締結を徹底する
地代の金額や支払い方法などが決まったら、必ず「土地賃貸借契約書」を作成し、書面で契約を締結しましょう。¥
口約束は、後々の「言った・言わない」のトラブルの原因になります。
契約期間、地代の額、改定のルール、支払い方法などを明確に記載した契約書を双方で保管することで、将来の紛争を未然に防ぎます。
底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
相続税対策としての地代の考慮
実は、無償の「使用貸借」から、地代を受け取る「賃貸借」に切り替えることは、将来の相続税対策として非常に有効な場合があります。
使用貸借の土地は、相続税評価において更地と同じ「自用地」として評価され、評価額が高額になりがちです。
一方、賃貸借契約を結び、適正な地代を受け取っていれば、その土地は「貸宅地」として評価され、評価額が15%~20%程度減額される可能性があります。
これは、将来の相続税負担を軽減する大きなメリットです。
底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫
まとめ
親子間の地代設定のように、土地の貸し借りには契約や交渉など専門的な知識が欠かせません。
このような問題は、地主様や相続人の皆様が抱えるお悩みのほんの一例です。
地代の滞納や増額交渉、煩雑な相続手続きなど、心労の絶えない底地管理にお困りではないでしょうか。
「借地人とのやり取りが面倒」「相続を機に底地を整理したい」とお考えなら、ぜひ当社にご相談ください。
センチュリー21中央プロパティーは、底地・借地権を専門とする不動産仲介会社です。
底地に強い社内弁護士が常駐しており、いつでも法的な観点からの的確なアドバイスが可能。
また、経験豊富な底地の専門家のみが在籍しており、地主様の立場やご心情を理解したうえで、底地トラブルの解決・売却を誠心誠意サポートいたします。
ご相談から売却に至るまで、料金が一切無料となっておりますので、底地のトラブルや売却でお悩みの地主様・相続人様は、ぜひお気軽にご相談ください。
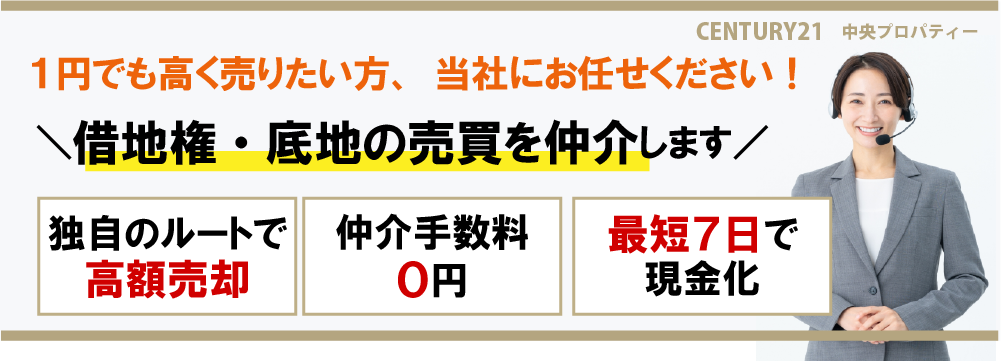
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。





