借地権の地代相場はいくら?計算方法と地代の値上げについて解説

土地の賃貸借において発生する「地代」は、経済情勢や周囲の環境、個別の土地の条件などさまざまな要素によって決まります。
しかし、大まかな相場に関しては計算によって把握することが可能です。
計算のポイントは、貸している、あるいは借りている土地の価値を正しく理解することです。
本記事では、税金の課税額や更地価格などを基準とする5つの計算方法を紹介し、地代相場や適正価格を把握するお手伝いをします。
相場を知り、場合によっては地代の増減交渉も検討するために、ぜひ最後までお読みください。
【無料相談】地代の交渉や更新料の支払いでお悩みの方はこちら ≫
借地権の地代相場の計算方法

地代とは、借地人が地主へ定期的に支払う土地の使用料のことであり、借地料や家賃とは区別されるものです。
土地の持つ価値は、周辺環境の変化などに伴い変動する上、土地の利用方法や面積によっても評価は異なるため、「地代はいくらが適正なのか分からない」人も多いでしょう。
地代を適正な価格で設定することは、地主にとっても借地人にとっても非常に大切です。
地代相場の計算方法は、以下の5つです。
- 公租公課(固定資産税・都市計画税)を基準にする方法
- 更地価格を基準にする方法
- 期待利回りを基準にする方法(積算法)
- 収益性を基準にする方法(収益分析法)
- 周辺の賃貸事例を参考にする方法(賃貸事例比較法)
計算方法①:公租公課(固定資産税・都市計画税)を基準にする方法
土地にかかる公租公課(固定資産税・都市計画税)を元に計算するもので、地代相場を求める際の最も基本的な方法です。
| 年間地代の目安 = (固定資産税 + 都市計画税) × 相場の倍率 |
固定資産税や都市計画税の課税額は、毎年市区町村から送付される固定資産税納税通知書に添付の「課税明細書」に記載されています。
固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の上限税率は0.3%ですが、税率は市区町村によって異なる場合があるため、念のため住所地の役所やインターネットで確認しましょう。
「倍率」に関しては明確な数字は定められていませんが、専門機関の調査結果などを参考にします。
例えば、日税不動産鑑定士会が公表している「継続地代の実態調べ(令和3年度)」によると、東京都の平均倍率は、商業地で4.05倍、住宅地で4.32倍でした。
出典:日税不動産鑑定士会「継続地代の実態調べ」(PDF)
公租公課を用いる方法は、手元の資料で簡易的に相場を知りたいという方におすすめです。
一方で、あくまで目安であるため、より正確さを求める場合には他の計算方法とあわせて検討することが推奨されます。
【無料相談】地代の交渉や更新料の支払いでお悩みの方はこちら ≫
計算方法②:更地価格を基準にする方法
国税庁や国土交通省が公表している土地の評価額を基準にして地代を計算する方法です。
まず土地の評価額から更地として評価した価格を**算出し、その価格に対して期待される利回り(年率)をかけ合わせます。
| 年間地代の目安 = 更地価格 × 期待利回り(1.5~3%程度) |
更地価格を算出するためには、以下の2通りの方法があります。
- 公示価格で計算する場合: 公示価格 × 面積
- 相続税路線価で計算する場合: 相続税路線価 ÷ 0.8 × 面積
公示価格は国土交通省が定めている土地の標準価格で、国土交通省のホームページで調べることができます。
相続税路線価は、相続税や贈与税を計算するために国税庁が定めており、国税庁のホームページから確認可能です。
一般的に、相続税路線価は公示価格の8割程度の水準に設定されているため、0.8で割り戻すことで公示価格に近い水準に修正します。
期待利回りは土地の種別によって異なり、一般的に住宅地で年1.5~3%、商業地で3~5%程度が目安とされます。
ただし、いずれも計算したい土地そのものの価格ではなく、あくまで基準値・標準値などを基にしているため、正確な相場とは言えない点に注意しましょう。
【不動産鑑定士とAIのダブル査定】借地権の無料査定サービス ≫
計算方法③:期待利回りを基準にする方法(積算法)
「積算法」とも呼ばれ、土地を投資用に購入した際に得られるであろう予想収益を基準にした計算方法です。
不動産鑑定評価で用いられる手法の一つです。
| 年間地代 = (更地価格 × 期待利回り) + 必要経費 |
この計算方法では、まず土地の現在の価値(更地価格)を把握する必要があります。
期待利回りや、土地の維持管理にかかる必要経費(公租公課、管理費など)についても、インターネットで正確な金額を調べることは難しく、専門的な知識が必要です。
そのため、不動産鑑定士など、専門家に依頼して算出してもらうのが一般的です。
計算方法④:収益性を基準にする方法(収益分析法)
その土地で事業を行った場合に得られるであろう収益を基準に地代を求めていく方法です。
これも不動産鑑定評価で用いられる手法で、特に店舗やビルなどの事業用の土地の地代を算出する際に活用されます。
| 地代 = (年間の総収益 − 年間の総費用)をもとに、土地に帰属する収益を算出 |
事業によって生み出されると予測される年間の事業収益額を計算した上で、人件費や材料費などの経費を差し引き、最終的に土地に帰属する収益を求めます。
すべての項目において専門的な知識が必要な計算方法です。
地主や借地人だけでは算出が非常に難しく、借地で店舗を運営する場合など、収益性を基に適正な地代を把握するのであれば、不動産会社や不動産鑑定士などの専門業者を介して正確に計算をするようにしましょう。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
計算方法⑤:周辺の賃貸事例を参考にする方法(賃貸事例比較法)
近隣の似たような条件の土地の地代・賃料相場などを参考に計算する方法です。
「賃貸事例比較法」とも呼ばれ、実態に即した分かりやすい方法です。
| 周辺の地代 ± 個別の事情(増減要因) |
周辺の地代に、対象となる土地の個別の事情を加味して増減させながら決めていく方法で、現実的かつ平均的な地代を計算するのに適した方法です。
個別の事情とは、主に景観や地盤の状態、日当たり、周辺建物との距離、道路付け、法令上の利用制限、面積などを総合的に見て判断します。
また、周辺地域の地代を知るためにはできるだけ多くのサンプル(比較対象となる事例)を用意して比較・検討していくことがポイントです。
不動産情報サイトを活用したり、専門家に相談したりして、周辺地域の地代を適切に把握しましょう。
地代の相場は変わる可能性がある
一度決めた地代は、契約期間中ずっと変わらないわけではありません。
経済情勢の変化や、周辺地域の開発、物価や税金の変動などによって、土地の価値は常に変わる可能性があるからです。
当初は適正だった地代が、時間の経過とともに周辺の相場と比べて高すぎたり、安すぎたりする状況になることは珍しくありません。
そのため、法律では貸主と借主の双方に、地代が不相当になった場合にその増額や減額を請求する権利「地代等増減請求権」を認めています。
地代の変更を可能にする「地代等増減請求権」とは
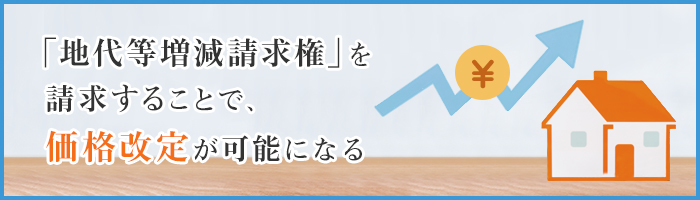
地主や借地人が、現在の地代が不相当になったことを理由に、将来に向かって地代の増額や減額を相手方に求めることができる権利を「地代等増減請求権」といいます。
これは、借地借家法第11条に定められた、当事者の双方に認められている正当な権利です。
地代等増減請求権は、以下の要因などを理由に、現在の地代が近隣の同種の土地の地代に比べて不相当になった場合に行使できます。
- 土地に対する固定資産税などの税金の増減
- 土地の価格の上昇または低下
- そのほかの経済事情の変動
地代等増減請求を行使する流れ
地代増減請求の流れは、以下の通りです。
- 当事者間で話し合い(協議)をする
- 話し合いがまとまらない場合、簡易裁判所に調停を申し立てる
- それでも合意しない場合、地方裁判所に訴訟(裁判)を起こす
まずは当事者間での協議が原則ですが、まとまらない場合は法的な手続きに進みます。
地代増減請求に関する訴訟は、原則として先に調停を申し立てなければならない「調停前置主義」が適用されます。
判決が出るまでの間、借地人は、地主が請求する額ではなく、自身が相当と認める額の地代を支払うことで足ります。
もし地主がその地代の受け取りを拒否する場合は、その地代を法務局の供託所に預ける「供託」という手続きをすることで、債務不履行になるのを回避できます。
判決の結果、支払うべき地代に不足があった場合は、借地人は不足額に対し年1割の利息を付けて支払う必要があります。
地代の増額がされる主なタイミング
地代が増額されるタイミングは、主に以下の通りです。
- 借地契約を更新するとき
- 借地権を相続したとき
- 周囲の類似物件の地代が変動したとき
- 税金や物価が上がったとき
- 土地の価値に変化があったとき
増額のタイミング①:借地契約を更新するとき
最も多いのは、借地権の更新時です。
地主にとって、借地権の更新時は、条件変更等の提案がしやすいタイミングです。地代も含めて契約全体の見直しが入る可能性があります。
増額のタイミング②:借地権を相続したとき
更新時と同様に、地代の値上げのきっかけになりやすいのが相続です。
地主が代替わりした場合や、借地人が借地権を相続した際に、未払いの更新料や承諾料の請求とあわせて、地代の増額などを突然請求されるケースも珍しくありません。
増額のタイミング③:周囲の類似物件の地代が変動したとき
周囲の類似物件の地代に値上がりがあった場合、再開発や新駅の開業といった何らかの市場動向が影響している可能性があります。
近隣の類似物件にくらべてあまりにも地代が安い、というようなことがあれば、近隣の類似物件に合わせた地代を提案される可能性があります。
増額のタイミング④:税金や物価が上がったとき
固定資産税率の変更や都市計画法の改正など、社会情勢が変わるタイミングで、地代も影響を受ける可能性があります。
地主としても土地を維持管理する上で、地代を増額しなければやっていけない、という状況であれば、増額請求をせざるを得ないでしょう。
昨今では、税金以外に物価の高騰も地代に影響を与えることがあります。
増額のタイミング⑤:土地の価値に変化があったとき
例えば、土地開発の計画が近隣で開始されるような場合、将来的に土地の価値向上が期待できます。
地主は、土地の価値に見合った地代への増額を請求してくる可能性もあるでしょう。
【社内弁護士が常駐】借地権のトラブル解決はお任せください! ≫
地代が減額されるケース
借地人から地代の減額を請求することも、法律で認められた正当な権利です。
地代の増額とおおむね反対の状況になった際に、請求できます。
しかし、地代はあくまで地主と借地人の双方の合意によって決まるため、両者での協議・合意が前提となります。
地代が減額されるケースは、主に以下の通りです。
- 不動産の価値が下がったとき
- 契約に変更があったとき
- 貸主の義務の不履行があったとき
- 市場の変動があったとき
減額されるケース①:不動産の価値が下がったとき
土地や建物の価値が減少した場合、地代の減額請求が可能です。
例えば、周辺に高い建物が建って日照が悪くなったり、近隣の工場から騒音や悪臭が発生したりするなど、周囲の環境が悪化して利便性が低下した場合が該当します。
減額されるケース②:契約に変更があったとき
契約によって地代の条件が変更された場合、その変更に基づいて地代の減額請求ができることがあります。
例えば、契約期間中に法律や条例が変更され、土地の利用に新たな制限が加わった場合などが該当します。
減額されるケース③:貸主の義務の不履行があったとき
貸主が契約で負うべき義務を果たさない場合、地代の減額請求が可能です。
例えば、貸主が修繕費用を負担することが契約で定められているにもかかわらず、修繕を怠った場合などが該当します。
減額されるケース④:市場の変動があったとき
地域の地代相場が下落した場合、これに基づいて地代の減額請求ができる可能性があります。
ただし、市場の変動だけでなく、契約内容や物件の状態なども総合的に考慮されます。
地代によるトラブルは、借地権トラブルの中で最も多いものの一つです。
こじれてしまう前に、早い段階で弁護士や不動産会社などの専門家の力を借りる方が、円滑な解決が期待できます。
【社内弁護士が常駐】借地権のトラブル解決はお任せください! ≫
まとめ
地代を決めるには、まず本記事で紹介したような方法で「地代の相場」を把握し、そこから個別の事情を加味して検討を進めていくことが基本です。
地代の増減を交渉する際も、客観的な相場のデータは、相手を説得するための強力な材料となります。
借地権・底地の売却や土地活用問題を解決するには、適切な権利評価や査定ができる経験豊富な専門家の存在が必要不可欠です。
センチュリー21中央プロパティーは、借地権専門の不動産仲介会社です。
借地権トラブルの中でも最も多い【地代に関するトラブル】の解決実績も豊富です。
借地権専門の社内弁護士が常駐しており、法的トラブルを回避しながら安心・安全にご売却のお手続きを進められる点が大きな強みとなっております。
また、不動産鑑定士や司法書士、税理士といった各種士業との強固な連携により、正確な地代相場の把握や、相続関連の手続きもスムーズに・トラブルなく進められます。
買い手探しが難航しがちな借地権付き建物や底地も、センチュリー21グループが誇る広範な”買い手ネットワーク”を活用し、スピーディな売却を実現します。
ご相談~売却まで、料金は一切頂いておりませんので、借地権のトラブルや相続、売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【社内弁護士が常駐】借地権のトラブル解決はお任せください! ≫

地主とのトラブル、借地権の売却にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
地代相場に関してよくある質問
地代相場に関してよくあるご質問とその回答を、いくつかご紹介します。
Q1.地主から一方的に地代の値上げを請求されました。応じる義務はありますか?
A.いいえ、一方的な請求に応じる義務はありません。
地代はあくまで双方の合意によって決まるのが原則です。
ただし、地主には法律(借地借家法)に基づき、地代が不相当になった場合に増額を請求する権利があります。
もし請求額に納得できない場合は、まずは地主と協議しましょう。それでも話がまとまらなければ、調停や裁判といった法的な手続きで適正な地代を決めることになります。
最終的に裁判で地代の増額が認められた場合、それまでの支払額との差額に年1割の利息を付けて支払う必要がある点には注意が必要です。
Q2.借地人から地代の値下げを要求することはできますか?
A.はい、借地人から地代の減額を請求することも法律で認められた正当な権利です。
周辺の地代相場や土地の価値が明らかに下落するなど、現在の地代が不相当に高いと感じる場合は、客観的な根拠を示して地主に交渉できます。
なお、契約書に「地代を減額しない」という特約があったとしても、法律上その特約は無効とされており、借地人は減額を請求することが可能です。
Q3.地主との地代交渉がまとまりません。この後はどうなりますか?
A.当事者間の話し合いで解決しない場合、法的な手続きに進むのが一般的です。
多くの場合、いきなり裁判ではなく、まずは簡易裁判所に「民事調停」を申し立てます。
調停とは、裁判官と民間の調停委員が中立な立場で間に入り、双方の事情を聞きながら、話し合いによる円満な解決を目指す手続きです。
もし調停でも合意に至らない(不成立となった)場合に、最終的な手段として「訴訟(裁判)」を起こすことになります。
裁判では、裁判官が法的な観点から適正な地代を判断し、判決を下します。
こじれてしまう前に、弁護士などの専門家に相談することも有効な手段です。
Q4.契約更新の際、更新料と地代の値上げを同時に要求されました。どちらも応じる必要がありますか?
A.「更新料」と「地代の値上げ」は法律上の性質が全く異なるため、それぞれ分けて考える必要があり、両方の要求に必ず応じる義務はありません。
まず更新料とは、契約を継続するための謝礼的な金銭で、法的な支払義務はないものの、契約書に定めがあれば支払うのが一般的です。
一方、地代の値上げは将来の賃料に関する交渉であり、あくまで双方の合意がなければ成立しません。
このように両者は全くの別問題ですので、「更新料は支払うので地代の値上げは見送ってほしい」というように、それぞれを切り離して交渉することが可能です。
この記事の監修者
社内弁護士
当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。





