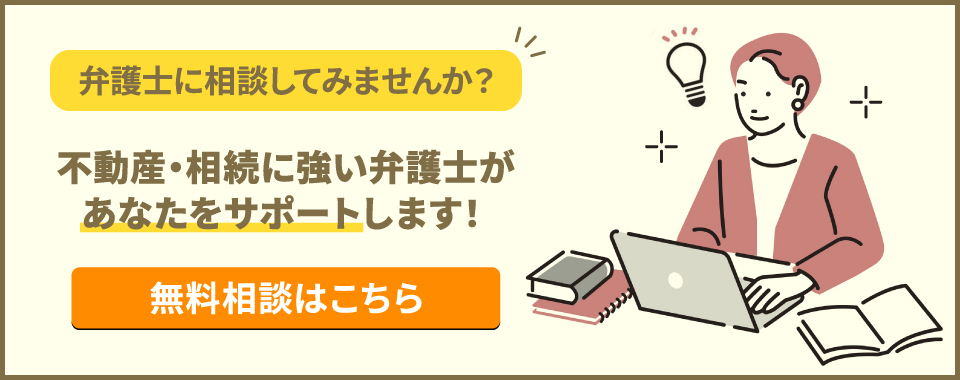借地権は売却可能!売却を成功に導く地主への交渉術・流れを徹底解説|借地権の売却・買取
借地権は売却可能!売却を成功に導く地主への交渉術・流れを徹底解説

目次
まず、大前提として借地権の売却は可能です。
ここでは、地主とのトラブルを避け、できるだけ高く売るために抑えておきたい売却の流れについてご紹介します。
1.借地権売却の流れ
借地権の売却の流れは、以下の通りです。
- 借地権の評価・査定を行う
- 地主に交渉し譲渡承諾を得る
- 地主と譲渡承諾の内容を協議する
- 販売活動開始
- 買主と地主間で契約条件の確認
- 売買契約の締結
- 借地権の引き渡し(決済)
借地権の売却を検討する場合、まずは借地権付き建物の査定を行いましょう。不動産会社によっては、市場価格よりも大幅に低い価格で査定額を提示してきます。言いなりにならないためにも、借地権売買の適正価格を把握しておきましょう。
また、借地権を売却する場合、地主の承諾が必要になります。
どのように交渉を進めるかによって、承諾がもらえる確率が変わりますので、まずは地主への交渉前に、借地権専門の不動産会社に相談し、方向性について相談に乗ってもらうのが良いでしょう。
2.借地権の売却時にかかる費用と税金
借地権の売却にかかる主な費用、税金は、以下の通りです。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡承諾料
- 譲渡所得税
- 土地測量費用
- 建物解体費用
- ホームインスペクション(住宅診断)費用
- 空き家片付け費用
- 借地非訟の際の弁護士費用
税金については、規定がありますが、仲介手数料をはじめとする不動産会社に支払う費用は、依頼する業者によって大きく異なります。
各社の情報を比較して、できるだけ手出しを少なく、借地権を手放せる手段を探しましょう。
センチュリー21中央プロパティーでは、仲介手数料をはじめとした売主様の費用負担をすべて0円で借地権の売却をサポートします。
3.借地権の売却時、地主とのトラブルに注意!
借地権の売却において、最大の難関は地主の承諾です。地主が借地権の売却に反対する理由は、様々ですが、過去の関係性の縺れから単純な嫌がらせのケースもあります。
まずは、日頃から地主との関係性を良好に保つことを心がけましょう。
また、借地権の売却については、地主にとっても借地人が変わることで、地代を滞納されたり、土地の使用をめぐってトラブルになるなど、リスクの高い出来事です。
地主への交渉は、借地人自ら行わず、借地権専門の不動産会社に代行してもらう方が、有利に進められる可能性が高いです。
特に、すでに地主との関係性が良くない場合は、交渉を持ちかける前に借地権専門の不動産会社に一度交渉の方向性について、相談してみると良いでしょう。
4.借地権はいくらで売れる?
借地権の売買価格は、誰に売るか、で大きく変わります。また、高く買い取ってもらうための交渉術もありますので、ご紹介します。
借地権の買い手は、基本的には、買取業者または不動産投資家のどちらかになります。
借地権の売却相談ができる不動産会社には、2種類あります。
- 買取専門業者
- 仲介専門業者
買取業者は、ブランド買い取りと同じで、安く買って高く転売する、というビジネスモデルです。つまり、高く売りたい借地人と安く買いたい買取業者は、利益相反の関係にあります。
一方で、仲介専門業者は、仲介手数料で利益を得ています。仲介手数料は、売買価格に比例するため、より高額での取引に向けて動いてくれます。
高く売りたいなら、借地権専門の仲介業者へ査定を依頼してみると良いでしょう。

5.借地権を高く売るには?交渉のコツ
売買価格の交渉のコツは、以下の通りです。
- 相場をもとに交渉する
- 値下げされる前提で希望の売却価格を伝える
- 値下げの下限額を決めておく
- タイミングを見計らう
- 値引き交渉された場合は、慎重に検討する
借地権の売却時には、「早く売りたい」というお気持ちもあるでしょう。
少々安くても、スピードを重視するか、時間は掛かっても、良い条件で購入してくれる買い手を待つかは、売主の戦略です。
借地権は、大切な資産ですので、時間が許されるのであれば、売り出すタイミング等も見計らい慎重に交渉しましょう。
5-1: 価格の交渉に関する注意点
借地権の交渉についての注意点は、前提として「借地権は買い手が見つかりにくい」ということを理解しておく必要があります。
借地権は、通常の所有権と比べて、何かと地主の承諾が必要になったり、やむを得ず立ち退きを迫られるケースもあります。そのため、完全所有権の不動産と比べて、購入希望者が少なく、売買価格も低くなりがちです。
価格交渉をするのは、売主の自由ですが、「買ってもらう」というスタンスで売買取引に望むことを心得ておきましょう。
借地権の売却相場については、以下の記事でも詳しく解説しています。
6: 地主の承諾を取り付けるための工夫
借地権の売却には、地主の承諾が必要です。ここでは、地主の承諾を取り付けるための工夫について紹介します。
6-1: 地主との関係構築が成功のカギを握る
交渉を取り付けるための最大のポイントは、借地人と地主との関係性です。
借地借家法では、借地権の契約期間は60年以上と、かなり長く設定されています。そのため、必然的に地主と借地人は、長いお付き合いになります。
その長いお付き合いの中で、例えば地代の滞納があったり、地主の承諾を得ずに建物の増改築をするなどの違反行為があった場合、どうしても借地人の心象が悪くなります。
また、最も地主とのトラブルが起きやすいのは、相続があったタイミングです。
借地人または地主が亡くなり、やり取りする相手が変わった場合、これまでは良好だった関係も、一気に変わってしまうケースも珍しくありません。
何をするにも地主の承諾が必要な借地権ですから、やはり地主と良好な関係を築くことで、スムーズに承諾を得ることができます。
6-2: 地主に「YES」と言わせる交渉をするには?
地主に「YES」と言わせる交渉をするためには、交渉は、借地権を熟知した専門家に任せるのが良いでしょう。
地主は、代々土地を引き継ぎ、契約等も管理している、いわゆる不動産の玄人です。一方、借地人は、借地借家法や不動産の知識に疎い方がほとんどで、大きな知識の差があります。
この知識の差は、交渉の有利・不利に大きく影響します。知識がない借地人が、無理な交渉を進めることで地主との関係性が悪化したり、地主に有利な条件で交渉が進んでしまうことがあります。
借地権の売却は、地主との交渉経験が豊富にある借地権専門の仲介業者に仲介を頼むようにしましょう。
6-3: 地主と良好な関係を築くコミュニケーション術
昔は、地主と借地人は、以下のようなコミュニケーションを取っていました。
- 地代は手渡し
- 近所で会ったら挨拶
- 年末年始は手土産を持って挨拶
- 介護施設への入居や相続が発生した際は迅速に情報を共有
今では、地主の顔も知らない、という関係性も珍しくありませんが、特に相続が発生した際などは、トラブルになりやすいため、しっかりとコミュニケーションを取っておくと良いでしょう。
また、地主がどんな人か、タイプを把握しておくことで、不動産会社も交渉をスムーズに進めることができます。
7.地主に譲渡承諾が得られない場合の対処法
地主が借地権の譲渡承諾を認めてくれない場合は、以下の方法を検討してみましょう。
7-1: 借地非訟手続きをする
地主から、借地権の譲渡承諾が得られない場合、借地非訟手続きを検討しましょう。
借地非訟手続きとは、地主に代わって裁判所に譲渡承諾を貰う手続きのことです。
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
借地借家法第19条
ただし、この借地非訟手続きは、借地権の買い手が決まっていなければ申し立てできません。そのため、通常は、不動産会社等に相談し、買い手を見つけた上で、借地非訟の手続きを行います。
借地非訟とは?手続きや費用、メリット・デメリットについて解説
7-2: 借地権の専門家に相談する
借地権の専門家には、弁護士や不動産会社が挙げられます。
借地権は、通常の不動産とは異なり、法律の知識や地主との権利調整など、複雑な対応が求められます。借地権の専門家に相談すれば、譲渡承諾が得られない場合の対処法について、アドバイスを貰えるでしょう。
7-3: 諦めて更地返還する
実は、ほとんどの方は、地主の承諾が得られない場合、借地権の売却を諦めてしまいます。
しかし、先述した通り、売却できる手段はありますので、まずは借地権に詳しい弁護士や不動産会社に相談をしてみましょう。
8.借地権の売却時に建物は解体すべき?
借地権の売却時に、建物の解体は必ずしも必要ではありませんが、建物が古い場合や交渉の結果によっては、売主負担で建物を解体する必要があります。
8-1: 建物の解体にかかる費用
建物の解体費用は、構造と面積によって変わります。
- 木造 3~4万/坪
- 鉄骨造 4~6万円/坪
- RC造 5~8万円/坪
例えば、30坪の木造の家を解体する場合、90万〜120万ほどかかります。また、アスベストが使われている場合は、除去費用が別途発生します。
解体にかかる期間は、2週間〜1ヶ月程度です。
詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
借地の家の解体費用が払えない場合の対応策と解体費用を抑える方法を解説
8-2: 建物の解体費用が不要なケース
建物の解体費用が不要になるケースは、以下の通りです。
- 建物の解体自体が不要なケース
- 買主または地主が解体費用を負担してくれるケース
借地権付き建物を解体するとなると、場合によっては、売却額よりも高い解体費用がかかってしまう可能性があります。建物の耐久性や安全性に問題がない場合は、建物を解体せず、そのままの状態で買ってくれる人が見つかる可能性があります。
また、地主との交渉が上手く言った場合や不動産会社によっては、売主の費用負担が発生しないケースもあります。
必ずしも、借地権の売却時に建物を解体しなければならないことはありません。
8-3: 解体せずに建物を売る方法
解体せずに、借地権付き建物を売却するには、ホームインスペクションを受け、耐久性や安全性に問題がないかを診断してもらうのが良いでしょう。
特に、相続によって取得した借地権付き建物は、築年数が古いことが多いです。ホームインスペクションを実施し、調査報告書を作成してもらうことで、解体せず、高値で売却できる可能性があります。
センチュリー21中央プロパティーでは、一級建築士によるホームインスペクションを無料で実施しています。
ホームインスペクションについては、以下の記事で、詳しく解説しています。
借地権の売却に一級建築士のホームインスペクションが必須な理由とは
9.借地権売却時のトラブルを回避する方法
借地権は、地主との権利調整が複雑なため、トラブルになりやすい特性があります。ここでは、借地権のトラブルを回避する方法を解説します。
9-1: 交渉力の高い専門業者に依頼する
借地権の売却は、地主への交渉が成功するか否かにかかっています。
中には、専門業者ではない不動産会社が地主に交渉し、余計に関係が悪化したり、うまく交渉を進められずお手上げ状態になったりすることもあります。
弁護士と連携しながら、法的な根拠を持って、円滑に交渉を進めてもらえる借地権専門の不動産会社を選びましょう。
9-2: 売買契約時の注意事項
無事に買い手が見つかり、売買契約を締結する際も、油断は禁物です。
特に、買い手が買取業者の場合は、売主にとって不利な条件が記載されていることもあります。
売買契約時には、売主にとって不利な条件が盛り込まれていないか、リスク対策はできているか、など弁護士同席のもと、リーガルチェックを行ってくれる業者がおすすめです。
センチュリー21中央プロパティーでは、契約時に弁護士が同席し、売主目線で契約書のリーガルチェックを行うことで、売却後のトラブル防止に努めています。
10.借地権売却における成功の秘訣
借地権の売却時に押さえておくべきポイントは、以下の通りです。
- 地主の交渉は、専門家に任せること
- 弁護士のサポートを受けること
- 誰に売るか、で売却価格が大きく変わること
- 借地権の購入希望者は少なく、売却相場は安くなること
借地権売却の成功ポイントは、地主に承諾を貰うこと、できるだけ高く売ることの2つです。
そのためには、借地権を熟知した専門業者に依頼するのが良いでしょう。

この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。