借地権付き建物とは?メリット・デメリットや購入時の注意点を解説

目次
借地権付き建物には、一般的な不動産売買とは異なるメリットとデメリットがあるため、その特性をよく理解し、慎重に検討しなければなりません。
当記事では、借地権付き建物の基本的な仕組みからメリット・デメリット、購入するときの注意点までを詳しく解説します。
購入に向いている方の特徴も紹介するため、通常の土地建物と借地権付き建物で迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
【仲介手数料0円】借地権の高額売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
借地権付き建物とは?
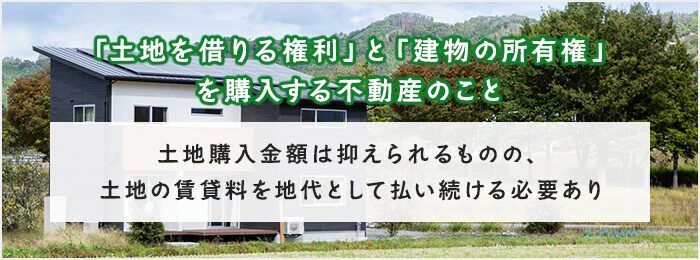
借地権付き建物とは、土地の所有権は地主が持ったまま「土地を借りる権利」と「建物の所有権」をセットで購入する不動産のことです。
土地の所有権自体は購入しないため土地取得にかかる金額は抑えられるものの、土地の利用料である地代を地主に払い続ける必要があります。
下記は、借地権付き建物にまつわる基礎用語です。
- 借地権:建物を所有する目的で、他人が所有する土地を借りる権利。「地上権」と「賃借権」に大別されます。
- 地上権:借りた土地を直接的・排他的に使用・収益できる強い権利(物権)であり、原則として地主の許可なく権利の売却・転貸も自由です。
- 賃借権:借りた土地を契約通りに使用する権利(債権)であり、売却・転貸には地主の許可が必要です。 世の中の借地権のほとんどが、この賃借権です。
- 借地権付き建物:借地権が設定された土地の上に建っている建物。
- 借地権者:土地を借りる人。 借地人とも呼ばれます。
- 借地権設定者:土地を貸す人。 地主や底地人とも呼ばれます。
- 底地:借地権が設定されている土地のこと。
- 底地権:借地権が設定されている土地(底地)の所有権のこと。地代を受け取る権利や、契約期間満了時に土地の返還を受ける権利などが含まれます。
- 底地人:底地権の所有者。 地主や借地権設定者とほぼ同義です。
借地権は借地借家法で認められた権利であり、現行法では「旧法借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類があります。
借地権は3種類に分類される
借地権は、以下の3種類に大別されます。
- 旧法借地権
- 普通借地権
- 定期借地権
種類①:旧法借地権
旧法借地権は、借地借家法が施行された1992年8月1日以前に結ばれた借地契約に適用される借地権です。
旧法借地権では、建物の構造によって下記のように存続期間が異なります。
| 構造 | 期間の定め | 存続期間 | 更新後の存続期間 | ||
| 初回 | 2回目以降 | ||||
| 旧借地権 | 堅固建物 (鉄筋コンクリート造) | あり | 30年以上 | 30年以上 | – |
| なし | 60年 | 30年 | – | ||
| 非堅固建物 (木造) | あり | 20年以上 | 20年以上 | – | |
| なし | 30年 | 20年 | – | ||
表の通り、それぞれの建物に、必ず上回る必要がある最低期間と、契約で期限を指定しなかった場合に自動的に適用される存続期間が定められています。
また、旧法借地権には下記のような特徴がありました。
- 地主が更新を拒絶するには「正当事由」が必要
- 借地人からの更新請求があれば、原則として契約は更新される
- 更新回数に制限がない
- 建物が老朽化などで朽ち(滅失し)た場合は借地権がなくなる
旧法借地権は、一度契約を結ぶと半永久的に土地を借り続けられるなど、借地人にとって非常に有利な内容となっていました。
これが原因で「土地を貸すと戻ってこない」という認識が広まり、土地活用の妨げになっているという社会問題がありました。
こうした状況を是正し、双方がより平等に利益を享受できるよう改定されたのが現在の新法借地権です。
1992年8月1日以降の契約は、すべて新法借地権となります。
現在も有効な旧法借地権の契約が、新法借地権へ自動的に切り替わることはありません。
新法借地権は、さらに普通借地権と定期借地権の2種類に分類されます。
種類②:普通借地権
普通借地権では、旧法借地権のように建物の構造によって契約期間に差は生じません。
普通借地権の主な特徴は下記の通りです。
- 存続期間:当初の契約では一律30年(これより長い期間を設定することも可能)
- 契約更新の条件:契約期間満了時に建物の現存があること
- 更新後の存続期間:初回の更新で20年・2回目以降の更新で10年
- 建物滅失後、再築による契約期間の延長:地主が承諾した場合に限り20年間延長される
- 契約終了による建物の買い取り請求:地主が更新を拒絶した場合、借地人は建物を時価で買い取るよう請求できる(建物買取請求権)
- 契約方法:特に定めなし(口頭でも可)
普通借地権でも旧法借地権と同じく、契約更新に際しては借地人の意向が優先されます。
ただし、地代の不払いや無断での増改築、建物が現存しないなど、地主側に「正当事由」があると判断されれば、地主が更新拒否することも可能です。
種類③:定期借地権
定期借地権は、あらかじめ定めた期間で契約が終了し、契約更新が行われない借地権です。
原則として、契約が満了したら更地にして土地を返却しなければなりません。
居住用の建物で利用できるのは、主に以下の2種類です。
| 一般定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
| 契約期間 | 50年以上 | 30年以上 |
| 契約終了時の建物 | 取り壊す | 地主が時価で買い取る |
| 契約方法 | 公正証書などの書面 | 口頭でも可 (書面が望ましい) |
一般定期借地権の場合、建物の取り壊し費用は原則として借地人が負担します。
建物譲渡特約付借地権では、契約から30年以上が経過した時点で地主が建物を買い取ることにより借地権は消滅するものの、その後は地主と建物の賃貸借契約へ切り替えて住み続けることも可能です。
なお、定期借地権には事業用の建物を建てるための「事業用定期借地権等」もありますが、こちらは用途が事業用建物に限定されており、居住用の家を建てることはできません。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
借地権付き建物を購入するメリット
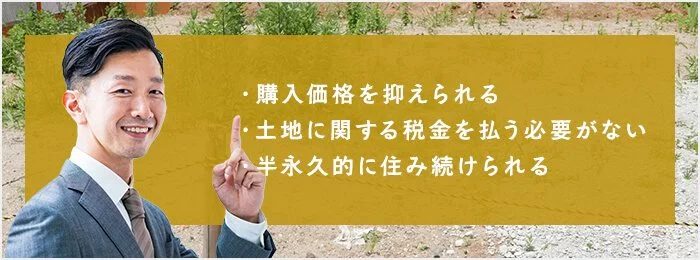
借地権付き建物を購入するメリットは、主に以下の通りです。
- 購入価格を抑えられる
- 土地に関する税金を払う必要がない
- 半永久的に住み続けられる場合がある
メリット①:購入価格を抑えられる
借地権付き建物は、家の初期費用を安価に抑えられることが大きなメリットです。
借地権付き建物では土地の所有権を購入しないため、土地と建物を同時に購入する場合(所有権付き物件)と比較して、総額を大きく抑えることができます。
地代を払い続ける必要はありますが、浮いた分の予算を建物の建築費用や設備の充実に回すこともできます。
所有権付き物件よりも安価に、こだわりのマイホームを手に入れられるでしょう。
借地権の価格は、その土地の更地価格に借地権割合を掛けて算出されることが多く、土地代の60~80%程度に設定されているケースが一般的です。
ただし、借地権の取引価格に関しては明確な相場があるわけではなく、土地のある地域や地主の意向などでも変動します。借地権付き建物
メリット②:土地に関する税金を払う必要がない
土地には、毎年、固定資産税や都市計画税といった税金がかかります。
ただし、課税されるのは土地の所有者である地主だけであり、土地を借りて住んでいる借地人に土地部分の支払い義務は生じません。
同じ広さの土地に住んでいても、毎年かかる土地の税金コストを抑えられることが借地権付き建物のメリットです。
しかし、借地権者であっても建物の取得や借地権の相続などに対しては、通常通り下記の税金がかかります。
- 不動産取得税(建物取得時)
- 固定資産税・都市計画税(建物部分のみ)
- 登録免許税(建物の所有権登記時)
- 相続税(借地権を相続した時)
- 贈与税(借地権を贈与された時)
メリット③:半永久的に住み続けられる場合がある
借地権契約には存続期間が定められており、定期借地権の場合は契約が満了したら土地は所有者である地主に返却しなければなりません。
しかし、借地権付き建物の契約が旧法借地権・普通借地権の場合、借地人は契約を更新できます。
これらの借地権の契約では基本的に借地人の権利が強く保護されており、更新を希望すれば一方的に契約解消される恐れはほとんどありません。
地主側から立ち退き要求や更新拒絶をするには、立ち退き料の提供なども含めた「正当事由」があると裁判所に認められる必要があります。
何をもって正当事由とするかは個々の事情にもよりますが、地主と借地人双方の土地を使用する必要性や利用状況などが重視される傾向です。
「今住んでいる土地にこれからも住み続けたい」という借地人の希望は強く尊重されるため、契約違反せず地代を払い、常識的に使用していれば、ほとんどのケースで契約更新が認められます。
このように、長期間住み続ける権利が保証されているため、安心して借りることができます。
【無料相談】相続した借地権の活用方法や売却でお悩みの方はこちら ≫
借地権付き建物を購入するデメリット
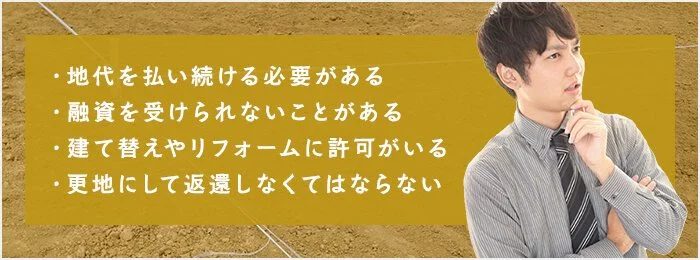
- 借地権付き建物を購入するデメリットは、主に以下の通りです。借地権付き建物地主に地代を払い続ける必要がある
- 銀行から融資を受けられないことがある
- 建て替えやリフォームに地主の許可がいる
- 定期借地権だと更地にして返還しなくてはならない
デメリット①:地主に地代を払い続ける必要がある
家を買う初期費用は抑えられるものの、ランニングコストとして地代の支払いが必要になることは借地権付き建物のデメリットの1つです。
借地権付き建物は土地を借りる権利を有しているだけであり、土地そのものは地主が所有し続けます。
あくまでも「対価を払って借りている」状態であるため、「地代」として毎月または毎年、使用料金を支払い続けなければなりません。
地代は地主との契約によって異なりますが、一般的には土地の固定資産税・都市計画税の年額の3~5倍程度が目安とされています。
また、地代は固定資産税の上昇や周辺の土地相場の変化によって見直されることが多く、地域の環境が充実したり利便性が上がったりした場合は値上げを要求される可能性もあります。
デメリット②:銀行から融資を受けられないことがある
金融機関によっては借地権付き建物を住宅ローンの担保として評価せず、融資を受けにくい場合があるため、注意が必要です。
借地権付き建物の場合、土地の所有者は地主です。
住宅ローンを組む際に金融機関が設定する抵当権は、原則として借地人が所有する建物部分のみとなり、土地は担保として見なされません。
法的には借地権そのものに対して抵当権を設定しても問題ありませんが、多くの金融機関がその条件として地主の承諾を求めます。
しかし、借地権への抵当権設定は地主にとってメリットがないため、承諾を得られる可能性は低いと言えるでしょう。
そのため、借地権付き建物は、土地と建物の両方に抵当権を設定できる所有権付き物件よりも担保評価が下がり、融資が受けられない、または融資額が下がる可能性があるため、注意が必要です。
ただし、近年ではフラット35や一部の金融機関で借地権付き建物に対応した住宅ローンも提供されています。
デメリット③:建て替えやリフォームに地主の許可がいる
建て替えや増改築、大規模なリフォームを行う際、地主の承諾が必要となり、別途承諾料の支払いが必要になるケースがほとんどです。
借地契約では土地の使用方法が細かく指定されている場合が多く、「増改築禁止特約」が盛り込まれていることも珍しくありません。
無許可で工事を行うと、契約解除に発展する場合があるため注意が必要です。
雨漏りの修理や壁紙の張り替えといった、建物の維持保全に必要な小規模な修繕であれば、承諾なしで行えます。
しかし、どこまでを「修繕」と見なすかは人によって基準が異なるため、後々のトラブルを避けるためにも、工事の前に地主に相談し、許可を求めたほうがよいでしょう。
【無料相談】地主から建て替え・増改築の承諾が得られずお困りの方はこちら ≫
デメリット④:定期借地権だと更地にして返還しなくてはならない
借地権付き建物の中でも、定期借地権は契約の更新ができません。
特に「一般定期借地権」の場合、契約期間が満了したら建物を解体し、更地に戻してから土地を返還する必要があります。
また、更地にするための解体費用などは原則として借地人の負担です。
一般定期借地権で契約している場合、居住期間の長さや建物の状態にかかわらず、期間満了とともに立ち退かなければならないことを覚えておきましょう。
建物譲渡特約付借地権で契約した場合、契約期間満了時に建物に資産価値があれば地主が時価で買い取るため、その後は賃貸契約に切り替えて住み続けられる場合もあります。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
借地権付き建物は売却できる?
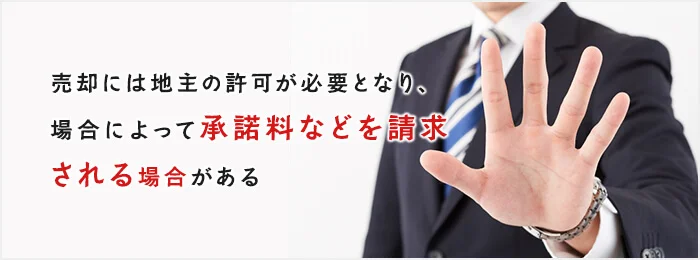
借地権付き建物が不要になった場合は売却が可能です。
ただし、借地権付き建物の売却は、「借地契約上の借地人としての地位と建物の所有権を売却する」ことになります。
そのため、借地権付き建物を第三者に売却する際は地主の承諾が必要となり、承諾にあたって譲渡承諾料などを請求されるのが一般的です。
- 借地権付き建物の売却方法は、主に下記の選択肢が考えられます。建物と借地権をセットで第三者に売却する
- 建物を取り壊し、借地権を第三者に売却する
- 借地権と建物を地主に買い取ってもらう
- 地主と協力し、借地権と地主の持つ底地権を合わせて土地そのもの(完全な所有権)として第三者に売却する
- 借地と底地を等価交換して完全な所有権を得た土地を第三者に売却する
また、譲渡承諾料の金額など契約内容の折り合いがつかなかった場合などは、地主からの承諾が得られないケースもあります。
売却の際、地主の許可が下りなかったら?
借地権付き建物の売却に地主の承諾が下りず、話し合いで解決する見込みがない場合は、「借地非訟」という手続きにより裁判所から承諾に代わる許可を得ることで売却が可能です。
裁判所に「土地賃借権譲渡許可申立」を行い、地主にとって著しく不利な条件がないと認められれば、地主の承諾に代わる許可が与えられます。
ただし、裁判所からの許可を得て借地権付き建物を売却する場合でも、譲渡承諾料に相当する金銭の支払いが必要となるケースがほとんどです。
また、地主が「介入権」を行使して自ら借地権を買い取ると主張した場合、借地人は売却相手を選べなくなる点も覚えておきましょう。
借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫
借地権付き建物を購入する際の注意点
借地権付き建物借地権付き建物は土地付きの建物より特殊な権利構造をしているため、購入して住む際には下記のような注意点があります。
- 更新料を支払うケースがある
- 相続税の対象になる
- 地主とのトラブルが発生しないよう注意する
注意点①:更新料を支払うケースがある
普通借地権の場合、契約更新時に地主から更新料を請求されます。
法律上、借地権の更新料について支払い義務を定めた規定はないため、双方の合意がなければ支払い義務は生じません。
ただし、下記の条件に該当する場合は支払う必要があります。
- 契約書に更新料の支払いが明記されている
- 借地人と地主の間に支払う旨の合意がある
なお、明確な合意がなくても過去に更新料の支払い実績がある場合は、「黙示の合意」があったとして裁判でも支払い義務ありと判断されるケースがほとんどです。
また、将来建て替えやリフォームが必要になった場合、地主の承諾が必要となるため、地主との関係性は良好に保つ必要があります。
金額が法外でなければ、円満な関係維持のために支払ったほうがよいでしょう。
一般的に、借地権更新料の相場は更地価格の3~5%程度と言われています。
万が一トラブルが発生した際に、裁判所が判断する更新料の目安は、更地価格の3%程度です。
【無料相談】地代の交渉や更新料の支払いでお悩みの方はこちら ≫
注意点②:相続税の対象になる
借地権は相続財産の1つであり、相続税の課税対象です。
これは普通借地権・定期借地権のどちらでも変わりません。
普通借地権の相続税評価額は、
| 自用地としての価額(更地評価額) × 借地権割合 |
で算出できます。
借地権割合は国税庁が路線価図などで設定しており、地域ごとに割合が異なります。
土地の評価額(路線価)や借地権割合は、国税庁のウェブサイトで確認が可能です。
定期借地権の場合、契約の残存期間や地代の額など複数の要因を絡めて計算するため、評価方法が非常に複雑です。
相続が発生した際は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
注意点③:地主とのトラブルが発生しないよう注意する
借地権は、土地の所有者と利用者が異なるため、地主とトラブルが起こりやすい傾向があります。
下記は、借地権付き建物に関して起こり得るトラブル事例です。
- 地代の値上げ・値下げ交渉
- 地代の滞納
- 更新料や各種承諾料の支払い
- 契約更新拒絶や借地の立ち退き要求
- 借地権の売買交渉
- 借地権の相続
地主とトラブルが発生した際、裁判所に申し立てて解決することも可能です。
しかし、「土地に長く住み続けたい」「将来、円満に譲り渡したい」と考えるのであれば、話し合いで解決するのが理想的です。
地主としっかり話し合い、双方がしこりを残さず納得するためには、普段から地主と良好な関係を築くように心がけることが何より重要であると言えるでしょう。
【社内弁護士が常駐】借地権のトラブル解決はお任せください! ≫
借地権付き建物の購入はどのような人に向いている?
借地権付き建物借地権付き建物にはさまざまなメリット・デメリットがあるため、購入にあたっては向いている人と向いていない人に分かれます。
借地権付き建物の購入に向いている可能性がある方の特徴は、主に以下の通りです。
- 初期費用を抑えて家を建てたい
- 好立地の場所に家を建てたい
向いている人①:初期費用を抑えて家を建てたい
所有権付きの土地を購入する場合に比べ、マイホーム購入の初期費用を抑えられることが、借地権付き建物の最大の魅力です。
「予算的に、希望のエリアで土地を買うと建物のグレードを下げざるを得ない」と感じる人や、定期借地権を利用して一定期間だけ住み、契約満了後は別の土地に新しく家を建て直すなど、ライフプランが明確な人には向いていると言えるでしょう。
また、将来的に土地の処分を考える必要がないため、お子様などがなく、誰かに建物を相続させる予定がない人にも向いています。
向いている人②:好立地の場所に家を建てたい
周辺環境や交通手段が整ったエリアの不動産は人気があり、土地価格も高額になりがちです。
特に都心部などの好立地の土地は、所有権付きの物件として市場に出ること自体が稀です。
しかし、地主の中には「手放す気はないが貸すなら構わない」と考える人もいるため、立地を優先して家を建てたい場合は借地権付き建物も候補に入れるとよいでしょう。
所有権にこだわらなければ、憧れのエリアに住むという選択肢が生まれます。
ライフステージの変化に伴った住み替えを考えている人にも向いた選択肢です。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫
まとめ
借地権付き建物は、地主から家を建てる土地の利用権を購入し、建物を所有する仕組みです。
初期費用や土地の税金を抑えられる一方、地代や更新料・承諾料といった特有の支払いが発生するため、総額のコストについては十分な検討が必要です。
借地権付き建物を購入するか否かは、自分自身のライフスタイルや将来設計を踏まえて検討することをおすすめします。
借地権付き建物が不要となった場合は、借地権を地主や第三者に売却することも可能です。
ただし、売却や建て替えなど、重要な局面では地主の承諾が必要となります。
このように、借地権は権利関係が複雑で、地主との良好な関係が不可欠です。
借地権付き建物の購入・売却を検討している人は、トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ一度借地権に詳しい不動産会社や専門家にご相談ください。
当社センチュリー21プロパティーは、借地権専門の不動産仲介会社です。
これまでに4万件を超えるご相談・売却実績があり、借地権のトラブル解決や高額売却のノウハウにつきましては業界随一です。
また、借地権専門の社内弁護士が常駐しているため、法的な課題をクリアしながらスムーズにお手続きを進めることが可能です。
ご相談から売却まで、料金は一切頂かないシステムとなっておりますので、借地権トラブルや売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫

地主とのトラブル、借地権の売却にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役/宅地建物取引士
都内金融機関、不動産会社での経験を経て、2011年に株式会社中央プロパティーを設立。長年にわたり不動産業界の最前線で活躍するプロフェッショナル。
借地権の売買に精通しており、これまでに1,000件以上の借地権取引や関連する不動産トラブル解決をサポート。底地や借地権付き建物の売却、名義変更料や更新料の交渉など、複雑な借地権問題に従事。
著書に「地主と借地人のための借地権トラブル入門書」など多数の書籍を出版。メディア出演やセミナー登壇実績も豊富で、難解な相続不動産問題も「わかりやすい」と説明力に定評がある。





